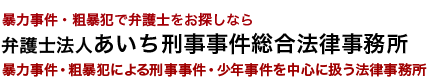未分類
洗濯機の中に子どもを入れて監禁
洗濯機の中に子どもを入れて監禁
千葉県千葉市に住むV君(1歳)の父親のAは、V君を洗濯機の中に入れ、洗濯機を回してV君に怪我を負わせたとして千葉県警千葉東警察署に監禁致傷罪で逮捕されました。
洗濯機の中でぐったりしているV君を見つけたV君の母親がAに問い詰めたところ、Aが「洗濯機の中で遊んだ。」「おもしろいからやった。」などと言ったことから、母親が110番通報し、本件が発覚したようです。
Aは警察の取調べでは、「Vが勝手に洗濯機の中に入り込んだ。」「おれはやってない。」などと言って犯行を否認しているようです。
(フィクションです。)
~ 監禁罪とは ~
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、一応脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁に当たるとされています。
また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。
したがって、物理的には監禁に該当するとしても、必ず犯罪となるわけではありません。
「不法」かどうかは、社会通念に従って判断されます。
以前、子どものころ、父親に叱られ反省させる意味で押し入れなどに閉じ込められた、という経験をお持ちの方もおられると思います。
この行為も立派な「監禁」に当たりますが、しつけが「不法」ではなかったことから監禁罪は成立しませんでした。
しかし、社会通念は時代とともに変化していくものですから、以前は許されていたとしても今も許されるとは限りませんから注意が必要です。
~ケガや死亡させた場合は~
さらに、監禁によって人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は監禁致死傷罪に問われます。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「前条の罪を犯し」というのは、監禁罪が成立した場合、ということです。
「よって」とは監禁行為と人の負傷、死亡との間に因果関係が必要であることを意味しています。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とは、負傷の場合は傷害罪(刑法204条)、死亡の場合は傷害致死罪(刑法205条)と比較して、上限も下限も重い方を採用する、という意味です。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
まず、負傷の場合ですが、刑法9条により、罰金刑は懲役刑よりも軽い罪とされますから、負傷の場合の下限は3か月以上の懲役です。
そして、監禁罪の7年以下の懲役と傷害罪の15年以下の懲役を比べた場合、15年以下の懲役の方が重いことは明らかです。よって、監禁致傷罪の法定刑は
3か月以上15年以下の懲役
です。
次に、死亡の場合ですが、監禁罪の7年以下の懲役(下限は1か月)と、傷害致死罪の3年以上の有期懲役(上限は20年)を比べると、上限も下限も傷害致死罪の方が重いです。
したがって監禁致死罪の法定刑は、傷害致死罪と同様、
3年以上20年以下の懲役
となります。
~ 余罪にも注意 ~
本件のような事案は児童虐待が疑われる事案です。
児童の身体などから日常的な児童虐待が疑われる場合は、傷害罪などでも立件されるおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
謝罪を強要し、強要未遂罪で逮捕
謝罪を強要し、強要未遂罪で逮捕
謝罪を強要し、強要未遂罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
AさんとVさんは、さいたま市浦和区の繁華街で肩がぶつかりあったことをきっかけに、トラブルになっています。
初めは口論でしたが、次第にトラブルはエスカレートし、AさんはVさんがわざと自分に肩をぶつけてきたと決めつけ、Vさんに土下座を要求しました。
Vさんが拒絶したので、Aさんはついカッとなり、Vさんの胸倉をつかんで「土下座しろって言っているだろう」と大声で怒鳴りつけました。
AさんとVさんのトラブルは周囲の人に通報されてしまっており、かけつけた埼玉県浦和警察署の警察官はAさんを強要未遂の疑いで逮捕しました。(フィクションです)
~強要罪とは?~
強要罪とは、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する犯罪です(刑法第223条1項参照)。
強要の手段として脅迫・暴行に着手したが、義務のないことを行わせ、あるいは権利の行使を妨害するに至らなかった場合には、強要未遂罪が成立します(刑法第223条3項)。
Aさんが行った、Vさんの胸倉を掴んで土下座を要求した行為が強要罪あるいは強要未遂罪に該当するか検討してみましょう。
Vさんの胸倉を掴む行為は、「暴行」と評価されるでしょう。
また、Vさんには、Aさんに対して土下座をする義務はありません。
そしてVさんに実際に土下座させるところまではいきませんでした。
したがって、Aさんの行為は暴行により、人に義務のないことを行わせようとし、これを遂げなかったものと評価されると思われます。
以上より、Aさんに強要未遂罪が成立する可能性は高いでしょう。
~Aさんは今後どうなるか?~
警察署に連れて行かれた後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明され、弁解を録取されます。
その後、取調べがなされます。
留置の必要があると認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求は検察官から裁判官に対して行われます。
裁判官が勾留請求に対して勾留決定を出すと、Aさんは10日間勾留されることになります。
これに加えて、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間、勾留が延長されることになります。
以上を合計すると、逮捕・勾留された場合、捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束を受けるということになります。
~早期の身柄解放を実現する~
Aさんの行った行為が強要未遂罪を構成する可能性は高いと思われますが、Vさんに怪我をさせたわけではありませんし、また、犯行に至ったきっかけも些細なトラブルということができるかもしれません。
勾留されると長期間の身体拘束を受けることになりますが、逮捕された以上はどのようなケースであっても勾留される、というわけではありません。
被疑者を勾留することが法律上許されるのは、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることなど、勾留の要件を満たしている場合です。
早期に弁護士を選任することによって、裁判官や検察官に勾留の要件を満たしていないことを主張し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけることが考えられます。
~不起訴処分を目指す~
検察官には、犯罪が成立していると判断しても、Aさんを必ず起訴するのではなく、不起訴にすることもできます。
起訴されてしまうと、無罪判決を獲得するのは非常に困難です。
一方、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることもなく、前科が付くこともありません。
不起訴処分を考慮する要素の一つとして、犯罪が悪質ではないことが挙げられます。
たとえば、Aさんの発言は喧嘩の際に流れで出てしまった言葉に過ぎないということで、悪質ではないと主張することが考えられます。
また、Vさんと示談することができれば、Aさんにとって有利な犯罪後の事情の一つとして考慮され、不起訴処分を獲得することができる可能性が高まります。
強要未遂事件を有利に解決するためには、弁護士を付け、被害者と示談交渉を進めることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強要事件の解決実績も豊富です。
ご家族が強要未遂事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非ご相談ください。
犯行を中止して減刑?【中止犯】
犯行を中止して減刑?【中止犯】
殺人未遂事件を起こしたが、途中で犯行を止めた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
神奈川県川崎市に住むAさん(75歳)は、妻のBさん(80歳)の認知症が進行してしまったため、5年ほど前からBさんの介護を続けていたが、先の見えないBさんの介護に限界を感じていた。
ある日、Aさんは、これ以上Bさんの介護を続けられないと感じ、Bさんを殺害することを決意した。
そこで、Aさんは、就寝中であったBさんに対し、殺意をもって、その左胸部を包丁で突き刺した。
しかし、Bさんが激しく苦痛を訴えるのを見たAさんは、自らの行為を後悔し、Bさんを助けようと思い、救急車を呼んでBさんを病院に搬送させた。
病院での医師らの救命措置により、Bさんは一命をとりとめることが出来た。
その後、Aさんは、殺人未遂の被疑事実で神奈川県麻布警察署の警察官により逮捕された。
(上記の事例はフィクションです)
~中止犯とは~
殺意をもってBさんの左胸部を包丁で突き刺して殺そうとしてしまったAさん。
まずは殺人未遂罪が成立することになるでしょう。
その上で、途中で後悔して救急車を呼んでいることから、「中止犯」というものが成立し、刑が軽くならないかが問題となります。
条文を見てみましょう。
(未遂減免)
刑法第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
この条文をまとめると、犯罪が未遂に終わった場合には、刑罰を軽くすることができる(軽くしなくてもいい)が、偶然にも未遂に終わったのではなく、自ら犯罪を途中でやめて未遂になった場合には、中止として必ず軽くしなければならない旨が規定されていることになります。
したがって中止犯が成立するためには、
①犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者であること
②自己の意思により
③犯罪を中止したこと
が必要となります。
まず今回の事例では、Aさんは殺害をしようとしましたが、Bさんが一命をとりとめ、殺人まではとげていません。
したがって、Aさんは①「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」にあたるといえます。
~自己の意思で?~
次に、②「自己の意思により」といえるためには、外部的な事情により犯行を中止せざるを得なくなったのではなく、やろうと思えばできたが、やらなかったと言える必要があります。
今回の事例では、AさんはBさんが激しく苦痛を訴えるのを見て、殺人をしようとしたことを後悔して救急車を呼ぶなどの行為をしています。
このように刺された人が激しく苦痛を訴えるのは通常のことですので、それだけで殺害を中止させるような外部的事情とはいえないとされることが多いです。
つまりAさんは、Bさんを殺そうと思えば殺すことが可能であったといえますが、救急車を呼んだことになります。
したがって、②「自己の意思により」という要件を満たすといえるでしょう。
~犯罪を中止した?~
次に、③「犯罪を中止したとき」といえるためには、(ア)自己の行為を中止すれば結果が発生しないと言える場合には行為の中止だけで足りますが、(イ)自己の行為によってすでに結果が発生しつつある場合には真摯な結果回避のための措置を講じることが必要となると考えられています。
(ア)の場合とは、ピストルで相手を殺そうとしたが弾丸が命中しなかったときに、まだ弾があるにもかかわらず殺害を中止するような場合のことをいい、この場合には単に殺害行為を止めれば足りると考えられています。
他方、(イ)の場合とは、今回の事例のように、すでに包丁で突き刺すという自らの行為によって被害者の死亡結果が発生しようとしているような場合を指します。
ここでの真摯な結果回避のための措置とは、単にそれ以上に包丁で突き刺す行為を止めるだけでは足りず、犯罪結果(死亡結果)の発生を防ぐための積極的な行為が必要となります。
今回の事例では、Aさんは、救急車を呼び医師らに救命措置を講じさせていることから、真摯な結果回避のための措置を講じたと評価でき、「犯罪を中止したとき」にあたる可能性が十分にあります。
このように、犯罪成立後の救命行為などにより①②③の要件を満たして中止犯が成立し、刑罰が減刑されたり免除されたりする場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件専門の弁護士が多数在籍しております。
弊所では、24時間、無料相談のご予約、初回接見サービスを受け付けておりますので、刑事事件についてお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
自宅に放火すると
自宅に放火すると
自宅への放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~今回のケース~
ケース①
東京都立川市に在住のAさん(55歳)は22歳の息子と一戸建ての住宅に住んでいます。
ある日、Aさんは息子を道連れに焼身自殺しようとして、深夜、自宅に火を放ち全焼させました。
火事に気付いた近所の人の助けによって、2人は逃げ出し怪我はありませんでした。
翌日、Aさんは、放火の疑いがあるとして東京都立川警察署の警察官によって取調べを受けることになりました。(フィクションです。)
ケース②
東京都武蔵野市に在住のAさん(55歳)は1人で一戸建ての住宅に住んでいます。
ある日、Aさんは焼身自殺しようとして、深夜、自宅に火を放ち全焼させました。
火事に気付いた近隣住民の助けによって、Aさんは逃げ出し怪我はありませんでした。
翌日、Aさんは、放火の疑いがあるとして東京都武蔵野警察署の警察官によって取調べを受けることになりました。(フィクションです。)
~現住建造物等放火罪にあたる可能性~
ケース①もケース②も、自宅に放火しています。
このような場合、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
刑法 第108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
以下、現住建造物等放火罪が成立するための条件を順に検討していきます。
〇放火
「放火」とは、目的物の焼損を起こさせる行為のことを言います。
目的物に点火する行為、目的物を燃やすために媒介物(たとえば新聞紙など)に点火する行為だけでなく、消火義務があるにもかかわらず消火をしない場合も「放火」に当たる可能性があります。
〇焼損
「焼損」の意味については、争いがありますが、裁判所は一貫して「独立燃焼説」という考え方を採用しています。
「独立燃焼説」とは「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったこと」を言います。
新聞紙などの媒介物が無くても建物などが燃える状態になれば「焼損」したと判断されるでしょう。
〇現に人が住居に使用し
「現に人が住居に使用し」ている状態とは、「犯人以外の者が起臥寝食(きがしんしょく)の場所として日常使用している状態」のことをいいます。
その建物で、寝たり起きたり食べたりなど、つまりは生活しているということです。
「犯人以外の者」には、共犯である場合を除き、家族や同居人も含まれます。
また、日常、起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現にいる必要はありません。
たまたま外出中に放火をした場合でも、現住建造物等放火罪に該当します。
〇今回のケースの場合
ケース①では、Aさんが自宅に火を放つ行為は「放火」にあたり、その結果自宅は全焼しているので「焼損」しているといえるでしょう。
また、今回の事件で疑いを掛けられているAさん以外にAさんの息子も日常的にこの住居を使用しているので、「現に人が住居に使用し」ているということが出来ます。
そのため、Aさんには現住建造物等放火罪が成立するでしょう。
一方ケース②では、ケース①と異なり、Aさんは一人暮らしです。
そのため、「現に人が住居に使用し」ているということはできません。
そこで、Aさんには現住建造物等放火罪は成立せず、非現住建造物等放火罪(刑法第109条)が成立することになるでしょう。
刑法 第109条 非現住建造物等放火罪
1 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
自己所有の家なのか、また、公共の危険(不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険)が生じたかによって、刑罰が変わってきますが、現住建造物放火罪よりは軽いものとなります。
~ご相談ください~
このように放火事件では、様々な法律判断がされることになり、今回のケースのように、人が1人いるかいないかによって適用する法律が変わってくる場合があります。
そのため、一度弁護士に状況を整理してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談や初回接見サービスを行っております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
被害者の同意ある傷害
被害者の同意ある傷害
被害者の同意を得て傷害行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都世田谷区に住むAは,友人のBに協力してもらい,交通事故を装って自動車保険金をだまし取ろうと考えた。
A,Bらは相談の結果,だまし取った保険金を半分ずつ分け合うことにし,この計画を実行に移すことにした。
AはBに対し,Aの運転する車の後部から、Bの運転する車を追突させるよう指示した。
またAは軽度の頸部捻挫を負うことも承諾していた。
結果的にAは加療約2週間を要する頸部捻挫の傷害を負った。
AはBから傷害を受けることに同意していたのだが,こういう場合にも傷害罪として罰せられるのか。
(この事例はフィクションです。)
被害者の同意~傷害罪の成否~
まず,BがAの車に追突させた行為は法律上,傷害罪に該当しうるものといえます。
条文を確認してみましょう。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし,Aは怪我をさせられることや、車を損壊させることについて同意しています。
このような場合,実質的には被害者がいないとして、加害者を処罰する必要はないという考え方もありえます。
しかし刑法などの法律には、社会的相当性を欠く行為を罰しようとする目的があります。
そこで、被害者の同意が社会的相当性を有していなければ違法となる可能性があります。
社会的相当性の有無は、承諾を得た動機,目的,身体傷害の手段,方法,損傷の部位,程度等,諸般の事情を照らし合わせて決せられます。
今回の事例はどうでしょうか。
まず,BがAからの承諾を得た目的,動機は保険金詐欺という、それ自体詐欺罪が成立する違法なものです。
また、身体傷害の手段・方法を見ると、車を使って後部から追突するというのは予期せぬ大きな事故にも発展しかねない危険な行為です。
たしかに損傷の程度を見ると、加療約2週間程度のものであり重症とまでは言いづらく、また、軽度の頸部捻挫を負うことを承諾していたAの予想の範囲内でもあります。
しかし、損傷の部位は頸部という神経の多く通う部位であり多少の損傷によっても身体麻痺等の重大な後遺症を与えかねない危険な部分です。
これらの事情をふまえると,Aが承諾していたとしても,この承諾は社会的に相当なものとは言えず,Bには傷害罪が成立することになるでしょう。
被害者が同意していても,犯罪は成立しうるということなので注意しましょう。
~詐欺罪も~
当然ではありますが、AとBは、保険金を請求した時点で詐欺未遂罪が、その後、保険金を受け取ることに成功してしまった時点では詐欺罪が成立することになります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
~弁護士にご相談を~
傷害罪や詐欺罪などで逮捕されたり、取調べを受けると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
タクシーで凶器を示して暴力行為等処罰に関する法律違反
タクシーで凶器を示して暴力行為等処罰に関する法律違反
タクシーで凶器を示して暴力行為等処罰に関する法律違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
京都市右京区に住むAさんは、夜間、タクシーを利用して帰宅しました。
しかし、Aさんは、タクシーが自宅付近に到着し、運転手Vさんからタクシー料金の支払いを求められるとその額に不満で、ポケットに入れていたアイスピックをVさんに示しながら、「お前俺をなめるとんのか。」と言いながらVさんを脅しました。
この怒号を聞きつけたAさんの妻がVさんにタクシー代金を支払い何とかことは収まりましたが、Aさんは後日、京都府右京警察署から暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。
Aさんは、今後どう対応していけばよいか困り、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 暴力行為等処罰に関する法律 ~
人を脅す行為というのは、一般に、刑法の脅迫罪(刑法222条)を思い浮かべる方も多いかと思います。
刑法222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
しかし、Aさんのように「兇器(凶器)」を示して脅迫すると暴力行為等処罰に関する法律に規定される罪に問われる可能性もあります。
~ 暴力行為等処罰に関する法律とは? ~
では、暴力行為等処罰に関する法律とはどんな法律なのでしょうか?
暴力行為等処罰に関する法律(以下、法律)は、集団的、常習的あるいは兇器を用いて行われる暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、傷害罪(刑法204条)について刑法の刑を加重する(法律1条関係(2条関係の説明は省略します)などした法律です。
大正15年4月に制定された古い法律で、第一次世界大戦後の社会的、経済的不満がまん延する大正末期に続発した集団的・常習的な暴力行為、面会強請、強談威迫などに対処するために制定されたと言われています。
法律1条【集団的にまたは兇器を示して行う暴行、脅迫、器物損壊罪】には、
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
と規定されています。
この規定を分解すると、
(手段) (方法)
①団体の威力を示し
②多衆の威力を示し ア 暴行
③団体を仮装して威力を示し イ 脅迫
④多衆を仮装して威力を示し ウ 器物損壊
⑤凶器を示し
⑥数人共同し
となり、いずれかが組み合わされば法律1条の罪に問われる可能性があります。
本件は、このうち「⑤・イ」の組み合わせに当たります。
なお、「凶器」とは、人の生命・身体に害を加えるのに使用されるような器具をいいます。
鉄砲、刀剣のように本来の性質上人を殺傷するために作られた器具はもちろん、鉄棒、こん棒のように本来用途においては人を殺傷すべきものではありませんが、使い方によっては殺傷のために使いえる道具も含まれます。
ただし、使い方によっては人を殺傷しえる道具であっても、社会通念上、人をしてただちに殺傷のために使いえると感じさせないもの(たとえば、縄、手ぬぐいなど)は「兇器」には含まれません。
なお、本件のアイスピックは「兇器」に当たると判示した裁判例があります(大高判昭和39年9月4日など)。
~ 常習犯の場合はさらに重い罪にも! ~
法律1条の3は、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪を犯した場合に関する規定です。
法律第1条の3
常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪を犯した者が人を傷害した場合は「1年以上15年以下の懲役」、その他の場合は「3月以上5年以下の懲役」とするとしており、法律1条より刑が重くなっています。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
この種事件においても示談交渉が、今後の刑事処分や量刑を決める上で大切になってきます。
お困りの方は弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
器物損壊事件を起こし取調べ
器物損壊事件を起こし取調べ
器物損壊事件を起こし取調べを受けるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは友人と兵庫県川西市にある居酒屋へ遊びに行っていた際、些細なことで口論となり、居酒屋の店長が仲裁に入りました。
すると、Aさんは店長に対しても怒りをあらわにし、店長にも因縁をつけるなどして暴れてしまいました。
そしてAさんはついカッとなり、テーブルの上にあった注文用の端末を床にたたきつけ、破壊してしまいました。
店長は兵庫県川西警察署に通報して警察官を呼び、Aさんは駆け付けた警察官により、器物損壊罪の容疑で話を聞かれるため、兵庫県川西警察署まで連れてこられてしまいました。
(フィクションです)
~器物損壊事件について~
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
器物損壊罪の客体となる「物」とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれ、さらに、他人の動物も含まれます。
そして器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、物を嫌がらせ目的で隠匿する行為も「損壊」に該当します。
なお、器物損壊罪のいう「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指し、他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為がこれに該当します。
動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。
今回のケースにおける「注文用の端末」は、明らかに居酒屋や店長の「物」であり、床に叩きつけて使用不能にする行為は、「損壊」に該当しますから、Aさんの行為には器物損壊罪が成立することになるでしょう。
器物損壊罪について有罪が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
~器物損壊事件で在宅捜査を受ける場合~
Aさんは器物損壊事件を起こしたとして話を聞かれるようですが、警察署では犯行に至った経緯、どのように端末を破壊したかなどについて詳しく尋ねられることになるでしょう。
器物損壊事件を起こしてしまったとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
適切な身元引受人を用意し、帰宅できる場合もあります。
逮捕されずに帰宅できた場合は、すぐに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
今回のケースの場合は、被害者と示談を行い、先方に生じさせた損害を賠償することが重要です。
器物損壊罪は「親告罪」であり、被害者による告訴がなければ、起訴されません(刑法第264条)。
したがって、告訴されてしまっている場合に、被害者に対して謝罪を行い、損害を賠償することによって、起訴される前に告訴を取り消してもらうことができれば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
~器物損壊事件で逮捕されてしまった場合~
警察署で取調べを受けた後、逮捕されてしまう可能性は否定できません。
器物損壊事件を起こして逮捕されてしまった場合においても、上記の示談を行うことが重要です。
ただし、逮捕されてしまった本人は外に出ることができませんので、弁護士が外で活動することが不可欠です。
示談が成立すれば、釈放される場合もありますし、告訴が取り消されれば、釈放される可能性が高くなります。
逮捕されている場合には、身柄解放活動を行う必要もあります。
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間もの間留置場や拘置所に入らなければなりません。
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰が難しくなります。
そのため、一刻も早く外に出ることができるように、弁護士に活動してもらう必要があります。
上記の示談交渉も身柄解放活動の1つということができますが、他にも、「勾留をさせない活動」、「勾留後の釈放を目指す活動」など、様々な身柄解放活動があります。
特に「勾留をさせない活動」は、なるべく早い段階で弁護士を付けることにより、初めて可能となる身柄解放活動です。
在宅捜査で事件が進行する場合も、逮捕されてしまった場合であっても、Aさんにとってより有利に事件を解決するためには、弁護士のサポートが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件につき、初回無料で法律相談を受けていただくことができます。
事件を起こしてしまった方が逮捕されている場合には、初回接見(有料)のお申込みにより、弁護士がご本人のもとまで伺い接見を行います。
器物損壊事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害罪とDV法違反
傷害罪とDV法違反
傷害罪とDV法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪府豊中市に住むAさんは、妻Vさんに日常的に暴力を繰り返していたとして、裁判所からDV法に基づく保護命令を受けました。
その措置に関して納得のいかなかったAさんは、知人つてでVさんの居場所を特定し、大阪府豊中市の自宅から出てきたVさんを待ち伏せして、Vさんに「なんで保護命令など申し立てたんか。」「話し合おうって言ったじゃないか。」などと言って、Vさんの顔面や腹部等を足蹴にするなどの暴行を加え、Vさんに加療約1か月間を要する傷害を負わせてしまいました。
その後、Aさんは大阪府豊中警察署に傷害罪とDV法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は
① 暴行の故意+暴行行為
② 傷害の故意+傷害行為
の2パターンから成立する可能性があります。
暴行の故意とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。
この暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われ得ることになります。
他方、傷害の故意とは、傷害させるつもりだったという場合です。
傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われ得ることになります。
そして、傷害罪の成立には、暴行行為又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。
この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。
よって、例えば、暴行行為により被害者に骨折を負わせたとされても、暴行行為の前に、被害者が別の原因で骨折したということが判明した場合は、「その行為がなくても結果は発生していた」といえますから因果関係は否定されることになり、傷害罪は成立しないことになります。
~ DV法違反 ~
DV法とは、正式名称、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律といいます。
DV法では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等に関する規定を設けており、平成26年1月3日から施行されています。
DV法では、配偶者に対する暴力そのものを処罰する規定は設けていません。
しかし、保護命令に違反した場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処すとの規定は設けています。
「保護命令」とは、相手方(Aさん)からの申立人(Vさん)に対する暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対して出す
①接近禁止命令
②退去、はいかい禁止命令
③電話等禁止命令
④子への接近禁止命令
⑤親族等への接近禁止命令
の総称をいいます(なお、③から⑤の命令は、必要な場面に応じて被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で発令されることはなく、申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます)。
①接近禁止命令とは、6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
②退去命令とは、申立人と相手方とが同居している場合で、申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために、相手方に対して、2か月間家から出ていくことを命じ、かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。
③子への接近禁止命令とは、子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
④親族等への接近禁止命令とは、相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
⑤電話等禁止命令とは、6か月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。
DV事案では、逮捕される可能性が非常に大きいです。
お困りの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
傷害致死罪と嘱託殺人罪との区別
傷害致死罪と嘱託殺人罪との区別
傷害致死罪と嘱託殺人罪との区別について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
埼玉県新座市に住むV女と懇意になったA男は,真実死ぬ意思があることを秘した状態で,Vから気絶するまで水面に顔を沈めてほしい旨を懇請された。
Aは,Vが死んでしまうのではないかと考えたが,Vがこれは「自殺ごっこ」にすぎず,助けを呼べばすぐに警察や救急車等がくるから大丈夫だと説得を繰り返した。
納得したAは,Vが死ぬことはないという認識の下で,Vが気絶するまで水面に顔を沈めた結果,Vは死亡するに至った。
通報を受けて駆け付けた埼玉県新座警察署の警察官は,捜査の結果,Aを傷害致死罪の疑いで逮捕した。
なお,Aに殺意がなかったこと自体には争いはない。
Aの家族は,暴力・粗暴事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~傷害致死罪と嘱託殺人罪~
刑法には,殺人罪(刑法199条)が規定されていることは,誰もが知るところです。
さらに刑法の同じ章(26章)には,続けて「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者」を処罰する自殺関与罪や同意殺人罪等を処罰する規定(202条)が置かれていることは,あまり知られていないかもしれません。
この点,本件Aは,Vとともに「自殺ごっこ」などと称し,客観的にはVの殺人の承諾を得て,Aを死亡させています。
この行為に関しては,上記で紹介した202条のうち「人をその嘱託を受け……殺した者」(同条後段)として,同意殺人の中でも「嘱託殺人罪」が成立するようにも思われます。
では,なぜAは嘱託殺人罪ではなく,傷害致死罪(205条)で逮捕されているのでしょうか。
この点に関しては,近年出された裁判例が参考になります。
札幌高裁平成25年7年11日判決は,まず,殺意こそ認めなかったものの殺意がない場合にも上記「人をその嘱託を受け……殺した者」(202条後段)として嘱託殺人罪が成立するとした1審(地裁)判決を破棄しています。
その上で,高裁判決は,被害者による殺人の承諾を知らないまま,暴行・傷害の故意で行った嘱託に基づく行為にはあくまで傷害致死罪(205条)が成立する旨を判示しています。
加害者に殺意がない以上は,被害者による承諾という形で人を殺害することの認識を前提とする嘱託殺人罪が成立するとの判断には無理があり,傷害致死罪(刑法205条)が成立するとしたのです。
~傷害致死罪における弁護士の弁護活動~
上記地裁判決が嘱託殺人罪を成立させたことには,法定刑の問題が関連しています。
嘱託殺人罪(刑法202条)の法定刑が「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」であるのに対し,傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は「3年以上の有期懲役」とされており,法定刑が不均衡なのではないかとも思われるからです。
しかし,法定刑だけを考慮するのは妥当ではなく,仮に後者の罪を問われたとしても,裁判所が量刑面で不均衡にならないように考慮するのが通常であると考えられています。
したがって,弁護士としても単純に法定刑の問題のみから嘱託殺人罪が成立するとの主張を行うべきではないとも考えられるところでしょう。
もっとも,殺意こそなかったものの,人を故意行為によって,死亡させている以上は起訴される(刑事裁判になる)ことはやむを得ないとも考えられます。
また,傷害致死罪は,裁判員裁判対象事件であることから,この点も弁護士としては考慮を要するといえます。
起訴された場合,弁護士としては,実刑判決を避け,執行猶予を得るための弁護活動を行うことになると考えられます。
執行猶予を得れば,被疑者・被告人にとって最も不利益ともいえる刑務所等への収監という自体を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死罪を含む暴力事件などを専門に扱う刑事事件専門の法律事務所です。
傷害致死事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐにお電話することをおすすめいたします。
タクシー強盗で強盗致傷罪、窃盗罪
タクシー強盗で強盗致傷罪、窃盗罪
タクシー強盗で強盗致傷罪、窃盗罪となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
神奈川県秦野市に住むAさんは、ギャンブルやお酒にお金を使い果たし、自宅へ帰るまでの交通手段に困っていました。
そこで、Aさんはタクシーを無賃乗車して自宅まで帰ろうと考え、Ⅴさんが運転するタクシーを停車させて乗車しました。
Aさんは、タクシーが自宅付近に近づくと、Ⅴさんに対し「ちょっと、小便がしたくなった。」「降ろしてほしい。」と言い、Vさんがタクシーを停車させたことからタクシーから降りました。
Aさんは草むらまで行き、小便をするふりをして後方を振り返るとVさんがタクシーに乗ったままだったことから「逃げるのはいまだ。」と思い、その場から逃走しました。
すると、酔って足取りが悪かったAさんは、逃走に気づいたVさんにあっという間に追いつかれてしまいました。
Aさんは、Vさんから「お客さんお支払いがまだですよ。」などと言われたとたん、Vさんの顔面を右手拳で1回殴りました。
その後も、AさんはVさんの顔面や腹部を拳で殴り、Vさんがひるんだ隙にタクシーに向かい、売上金5万円を奪ってその場から逃走しました。
その後、神奈川県秦野警察署の捜査の結果、Aさんは強盗致傷罪、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
タクシーの無賃乗車、その後のVさんに対する暴行、売上金の盗難につきいかなる罪が成立しうるのか見ていきます。
~ 詐欺利得罪 ~
まず、Aさんが無賃乗車をする意図がありながらその意図を秘しタクシーに乗り込み、Vさんに目的地付近までタクシーを運転させた行為につき詐欺利得罪が成立することが考えられます。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
このうち2項が、いわゆる詐欺利得罪に関する規定です。
詐欺利得罪は、「前項の方法(人を騙すこと)」により、「財産上不法の利益を得」ることで成立します。
具体的には、料金を支払う意図がないにもかかわらず、タクシー内で運転を依頼する言動、目的地を指定する言動が騙す行為に当たるでしょう。
また、「不法の利益」とは利益の不法、ではなく、利益を得るための手段が不法であることを意味します。ここで「利益」とは、タクシーで目的地まで送り届けてくれること、でしょう。
AさんはVさんを騙してタクシーを運転させ、目的地まで送り届けさせていますから「財産上不法の利益を得」たことに当たります。
~ 強盗利得罪 ~
次に、AさんがVさんを殴った行為につき強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
このうち2項が強盗利得罪に関する規定です。
強盗利得罪は、「前項の方法(暴行又は脅迫)」により、「財産上不法の利益を得」た場合に成立します。
「暴行又は脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りるものでなければならないとされています。
・被害者に債務を免除させる
・被害者に一定のサービスを提供させる
・被害者に債務の負担を口頭で約束させる
などがその典型でしょう。
なお、強盗利得罪の場合、詐欺利得罪と異なり、被害者の処分行為は不要とされています。
人に怪我をさせたり、死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され同罪で処罰される可能性があります。
同罪の罰則は、怪我(負傷)させた場合は「無期又は6年以上の懲役」、死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」です。
~ 窃盗罪 ~
最後に、Aさんが暴行後に売上金5万円を持ち去った行為については、Aに窃盗罪の成立する可能性があります。
AさんはⅤさんを殴った上で売上金を持ち去っていますから強盗罪が成立しそうです。
しかし、この暴行は、売上金を奪うためではなく、あくまでタクシーの料金支払いを免れるためになされたものにすぎません。
よって、強盗罪ではなく窃盗罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等のご予約・お申込を24時間受け付けております。