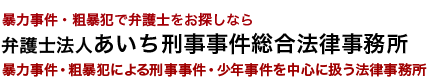未分類
無形的方法による傷害事件
無形的方法による傷害事件
~今回の事件~
東京都武蔵野市のアパートに住んでいるAさん(30歳)は、ゴミの出し方を巡ってアパートの隣人女性とトラブルになっていました。
Aさんは、しつこくゴミの出し方について文句を言ってくる女性に腹が立ち、1年ほど前から、女性の部屋と接している壁を夜中に大きく叩いたり、女性の部屋のインターフォンを鳴らしたりする嫌がらせを毎晩のように続けました。
女性が警視庁武蔵野警察署に相談して、これまで何度か警視庁武蔵野警察署の警察官に「止めるように」と注意を受けましたが、Aさんは警察官の注意を無視して嫌がらせを続けました。
するとある日、Aは、傷害罪で警視庁武蔵野警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
~問題となる条文~
刑法 第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
~「傷害」とは~
傷害罪でいうところの「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加える」ことを意味します。
これを簡単に言いかえると、生活状態や健康状態に変化が生じてしまう場合を意味します。
一時的な精神的苦痛やストレスは「傷害」になりませんが、一定期間持続するPTSD(外傷後ストレス障害)は傷害にあたるとされています。
~「傷害」の方法~
一般的な傷害事件は、加害者の暴行によって、被害者が打撲や、骨折、挫傷といった傷害を負うことによって成立します。
殴る、蹴るなどといった有形力を用いることでなされるものですが、刑法では傷害の方法が限定されていません。
そのため、暴行によらない無形の方法によるものでも傷害罪にあたる可能性があります。
裁判所の判例によると、「嫌がらせの無言電話をかけ続け、相手を精神衰弱症にかからせた事案」や、「嫌がらせにより抑うつ状態に陥れた事案」において傷害罪にあたるとされています。
Aさんのように、深夜に部屋の壁を叩き続けたり、インターフォンを鳴らすことで、被害者に日常的に精神的ストレスを感じ、そのストレスが原因で、耳鳴り症や睡眠障害に陥れば、傷害罪が適用されて逮捕される可能性が十分に考えられます。
~「傷害」の故意~
傷害罪の成立に傷害の故意は必要とされておらず、暴行の故意があればよい、とされています。
被害者を殴って傷害を負わせたような傷害事件ですと、被害者を殴る故意があれば、その暴行によって被害者が傷害を負うというところまで故意は必要ないのです。
しかし、今回の事例のような、暴行を加えない無形の方法による傷害事件の場合には、暴行の故意にあたるものがないため、傷害の故意を必要とされています。
そのため、相手を精神障害に陥れること、相手が精神障害になっても構わないと思っていることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで様々な刑事事件を扱い、解決に導いてきました。
同じ傷害事件でも、暴行の程度や、傷害の程度、被害者感情等によって、刑事処分は様々で、被害者と示談する等して不起訴処分となり前科を回避した事件も少なくありません。
東京都武蔵野市の傷害事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
DV、児童虐待の被害で悩むあなたへ
DV、児童虐待の被害で悩むあなたへ
東京都千代田区に住むAさんは、夫Bが娘Vちゃん(10歳)に日常的な児童虐待を目の当たりにしながら、それを傍観する毎日を送っていました。
実は、Aさん自身も、夫Bから日常的な暴力を受けるDVの被害に遭っていたため、夫Bの行為を止めることができなかったのです。
ところが、ある日、夫BがVちゃんへ暴力を振るったことによりVちゃんを死亡させた傷害致死罪で警視庁万世橋警察署の警察官に逮捕されたところ、Aさんも傷害罪の幇助犯で逮捕されてしまいました。
(千葉県野田市での事例を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
「お父さんにぼうりょくを受けています。夜中に起こされたり起きているときにけられたりたたかれたりしています。せんせいどうにかできませんか。」
これは、先日より報道されていた千葉県野田市の児童虐待事件で亡くなられた女児が書いた文章です。
小学4年生の子供がここまでSOSを発信しているのに助けることができなかったのかと心が痛みます。
先日、5月16日、千葉地方裁判所では、亡くなった女児の母親の初公判が開かれました。
母親は傷害罪の幇助犯の罪に問われています。
裁判所には多くの傍聴希望者が詰めかけたとのことで、社会的関心の高さがうかがえます。
また、同じ子を持つご家族、お母さんなどにとっても注目すべき裁判だったのではないでしょうか?
今回は、そうした方々のためにも、なぜ、自らもDVの被害に遭っていたのに夫の児童虐待を傍観していた母親が罪に問われたのか、について考えてみたいと思います。
~ 何もしなくても罪に問われることがある ~
法律上は、「何かした」ことに対して罪を与えることが基本です。
例えば、殺人罪でいえば、包丁で人の胸を刺す、ロープでクビを絞めるなどの行為です。
ところが、殺人は、「何もしない」ということでも実現可能です。
児童虐待の例でいえば、親が重病にかかっている子供を病院に連れていかない、衰弱している子どもに食事を与えない(必要な保護をしない)などです。
この「何もしない」ことを法律上は「不作為」と呼んでいます。
~ 幇助犯とは実際の犯行を容易にすること ~
では、幇助犯とは何かというと、「実際の犯行(今回の例でいえば、夫BのVちゃんに対する暴行(児童虐待))を容易にすること」をいいます。
大きな括りでいうと幇助犯も「共犯」なのですが、一般的にイメージされる「共同正犯」「共謀共同正犯」とは性質を異にします。
~ 不作為の幇助犯が成立するための要件 ~
ところが、あらゆる不作為を処罰できるとすると、Vちゃんを保護できなかった(あるいはしなかった)おじいちゃん、おばあちゃん、はたまた児童の職員まで処罰されうることになります。そこで、実務では、
① 行為者が保証人的地位にあること(→母親であれば通常認められるでしょう)
② 保証人(母親)か゛一定の犯罪阻止行為に出ることか゛可能・容易て゛あること
③ 保証人(母親)の不作為によって正犯の犯罪実行を容易にしたといえること(→報道によれば、母親は、DV被害をかわす代わりに、児童虐待を黙認していたとのことです)
という要件を設けて不作為犯の適用が無限に広がることを制御しています。
~ DV被害を受けていても…?? ~
裁判例の中には、仮に、DV被害を受けていても、「母親は体を張って子供への暴行を阻止する方法のほかにも、夫が子供に暴行を加えないように監視したり、夫の暴行を言葉で制止したりするなどして、夫の暴行を阻止することは可能であった」として不作為による幇助犯を認めている事例もあります(札幌高裁平成12年3月16日)。
しかし、これはずいぶん前の裁判例で参考になるかは疑問です。
また、仮に、「母親へのDVが余りにも酷く母親が完全に意思を抑圧されていた、あるいは母親が物理的に監禁されていたなどの極限的な状況だった場合」には、上記②の要件を満たさず、不作為の幇助犯は成立しないでしょう。
~ おわりに ~
今回の裁判ではどう判示されるか注目すべきです。
もし、この記事をお読みになり、同様のことでお悩みの場合は、厚生労働省が児童虐待でお悩みの方のための専門のダイヤルを設けていますからそちらに相談されてみてはいかがでしょうか?(児童相談所全国共通ダイヤル:189)
また、DV被害でお悩みの場合の相談窓口は「内閣府男女共同参画局 DV相談ナビ:0570-0-55210」となっていますので、ご参考ください。
さらに、Aさんと同様、被害者ではなく、
・刑事事件に発展しそうだ
・被疑者として捜査を受けそうだ
・逮捕されるか不安
などという方は、ぜひ、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問い合わせを24時間受け付けております。
監禁致死傷罪とは
監禁致死傷罪とは
福岡県うきは市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさんと性交等をする目的でしたが、Vさんに「夜景を観にいこう」などと嘘を言って車の助手席に乗せました。
そして、Aさんは福岡県うきは市の人気のない山奥に向かうため高速道路に乗りました。
そして、Aさんは車を走行中、Vさんに睡眠薬入りのジュースを飲ませ眠らせました。
Aさんは、Vさんが眠っている間、パーイングエリアでVさんの両手に手錠をまし、再び車を走らせました。
しかし、睡眠薬の量が少なかったのかVさんが起きてしまいました。
Aさんは、Vさんから「何これ?」「どういうこと?」「話が違うじゃない」と言われました。
さらに、AさんはVさんから「次のSAで降ろしてよ」と言われましたが、そのまま通過し車を時速約130キロで走行させました。
そうしたところ、Vさんが無施錠だった助手席のドアを開け外に飛び出しました。
しかし、Vさんは頭や全身を路面に強く打ち付けた影響などにより死亡してしまいました。
その後、Aさんは福岡県うきは警察署に監禁致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 監禁致死傷罪 ~
監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、監禁致死傷罪は、①前条の罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
以下、詳しく解説いたします。
~ 「前条の罪」 ~
「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。
刑法220条の規定を確認すると、
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
とあります。
* 監禁とは *
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
本件では、確かに、助手席のドア鍵は無施錠であったことから、Vさんの自由の拘束は完全だったとはいえません。
しかし、時速130キロで走る車から飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為です。
Vさんはその危険を冒してまで脱出せざるを得なかったのですから、AさんがVさんを助手席に乗せる行為は「監禁」に当たるでしょう。
* 不法に *
監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。
したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。
親子間では「しつけ」と称して、親が子供を鍵のかけた物置小屋などに閉じ込める、というケースも耳にします。
通常、親には子に対する監護権が認められていますから、直ちにそれが「不法」な監禁とされることはありませんが、社会通念上許容される範囲を超える行為は違法とされ監禁罪で処罰される可能性もあります。
~ 「よって人を死傷させた」 ~
監禁致傷罪の成立には、人の「傷害」「死」という結果の発生と、その結果と監禁そのもの、少なくともその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
また、過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
~ 「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」 ~
つまり、監禁致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい、「3年以上の有期懲役」、監禁致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
監禁致傷事件・監禁致死事件などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問合せを24時間受け付けております。
傷害罪か暴行罪か?
傷害罪か暴行罪か?
京都府木津川市に住むAさんは,職場の同僚であるVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。
その際、Vさんの鼻などから出血は確認できず、Vさんも病院には行かなかったようです。
ところが、それから1週間後、Aさんは京都府木津警察署の警察官に呼び出され、取調べで「Vさんから医師の診断書が出た」「診断名は歯牙破折だ」ということを聞かされ、傷害罪の被疑者として捜査すると言われました。
Aさんとすれば、暴行自体は認めているものの、事件当時、Vさんから歯が折れたなどとは聞かされていなかったため、怪我の点については納できずにいます。
そこで、Aさんは、今後どう対応すればいいのか刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
Aさんは、Vさんの顔面を1回殴打したこと自体は認めていますから、本件は暴行罪が成立するのか傷害罪が成立するのかの問題です。
そこで、両罪の違いからご紹介いたします。
~ 暴行罪 ~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
もっとも典型なのが、殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど、直接人の身体に触れる行為が挙げられます。
もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
~ 傷害罪、暴行罪との違い ~
傷害罪の規定は以下のとおりです。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。
したがって、
・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合
は傷害罪は成立しません。
ただし、「暴行」の事実自体は存在しますから暴行罪は成立します。
この点が、暴行罪と傷害罪の違いの一つといっていいでしょう。
~ 本件の刑事弁護 ~
本件で、Aさんは、「暴行」の事実自体は認めているものの、「暴行」と「傷害」との因果関係について疑問を持たれているようですから、まずは「暴行罪」での処分を主張していかなければなりません。
具体的には、Aさんはもちろん、周囲に直接の目撃者あるいはVさんの様子を知る人がいなかったかどうか調べ、その方たちからもお話を聴く必要があるでしょう。
そして、その聴取した結果を意見書という形にまとめ、処分を決める検察官に提出するといったことが考えられます。
それと同時に、「暴行」の事実に限っての示談交渉を進めていく必要があります。
仮に、傷害罪で起訴され裁判になった場合は、裁判で診察をした医師を尋問するなどして作成した診断書の証明力を減退させる必要も出てくる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪、傷害罪等の刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
兵庫県尼崎市で強盗・銃刀法違反事件
兵庫県尼崎市で強盗・銃刀法違反事件
【事件】
Aさんは兵庫県尼崎市にあるV銀行の窓口担当の行員に対して,刃体16センチメートルの包丁を突きつけ,「金を出せ」と脅迫しました。
行員はAさんに現金を渡し,Aさんが逃亡したのを確認したところで兵庫県尼崎北警察署に通報しました。
後日,兵庫県尼崎北警察署の捜査によってAさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【強盗罪】
強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法第236条第1項)。
強盗罪の法定刑は,5年以上の有期懲役です。
強盗罪における暴行・脅迫は,反抗を抑圧するに足りる程度の強さがなければなりません。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている暴行が,端的に人に向けられた有形力(物理力)であればよいとされているのに比べて,それが客観的に見て反抗を抑圧する程度のものであると認められる必要があることを意味します(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
強盗罪の成立に必要な暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります。
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。
そして,強盗罪で用いられる暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られません。
例えば,過去の判例の中には,留守番をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときであっても強盗罪が成立するとされた事例があります(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。
強盗罪のいう強取とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配状況のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。
また,相手方の反抗が抑圧されなかった場合について,財物を取得することができなかった場合は強盗未遂罪に問われる可能性があります。
暴行・脅迫を行ったものの被害者の反抗は抑圧されてはおらず任意に財物を差し出した場合について,学説上の争いはありますが,判例によれば強盗罪の既遂が認められるようです(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
【Aさんのケースと強盗罪】
今回の場合,Aさんは刃体16センチメートルの包丁を突きつけて「金を出せ」と脅迫しています。
一般的に包丁を突き付けられた状態で「金を出せ」と脅迫された場合,お金を差し出さなければ包丁によって危害を加えられると考え,犯人に反抗することはできないでしょう。
よってAさんによる脅迫は行員の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったと認められる可能性が高いです。
その脅迫の結果,行員は現金をAさんに差し出しており,Aさんは現金を強取しています。
以上より,起訴されればAさんは強盗罪の罪責を負うことになる可能性が非常に高いです。
【銃刀法違反】
銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)は第22条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定しています。
違反した場合は同法第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし例外があって,刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第37条に以下のものが挙げられています。
・刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
・折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
・法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
・法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
Aさんは刃体16センチメートルの包丁を強盗の手段とするために所持しており,銃刀法第22条に違反していることになります。
逮捕されてしまった場合,その後の身体拘束が長期に及ぶことが予想されます。
逮捕されている場合,当然仕事にも行けず,家族と面会することすらままならない場合があります。
しかし,弁護士は立会人なくして被疑者・被告人と面会することができます。
逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合は,可能な限り早い段階で弁護士に相談・依頼すべきといえます。
弁護士を呼ぶことができる時期には制限はありませんので,安心して逮捕直後に呼んで構いません。
弁護士は,被疑者に対して取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点,捜査機関に対してとるべき態度,今後の刑事手続きの流れや見通し等について必要なアドバイスをします。
家族や知人等から被疑者への伝言,被疑者から家族や知人等への伝言等の伝達をしたり,早期の被害弁償や示談交渉などできる限りの弁護活動をしてくれます。
銃刀法違反の容疑をかけられてしまった方,強盗罪の容疑をかけられてしまった方,ご家族やご友人が兵庫県尼崎北警察署に逮捕されて困っている方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお早めにご相談ください。
腹いせの業務妨害事件で逮捕
腹いせの業務妨害事件で逮捕
~ケース~
Aさんは埼玉県朝霞市内のコンビニを利用したところ、店員の態度が悪く感じ、これに因縁をつけたところ、口論になりました。
その場は収まり、Aさんは帰宅したのですが、怒りをしずめることができませんでした。
後日、Aさんは先日の腹いせにと画びょうを3000個用意し、コンビニを再訪した後、床にばらまいてしまいました。
店員は埼玉県朝霞警察署に通報し、Aさんは駆け付けた埼玉県朝霞警察署の警察官に威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
コンビニは画びょうが撤去されるまで2時間ほどの間、営業を中止する事態になりました。
(フィクションです)
~威力業務妨害罪について~
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪であり、威力業務妨害罪で起訴され、有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法第234条)。
お店や団体に嫌がらせや、腹いせを行った結果、威力業務妨害罪の疑いで検挙されるケースがあります。
(「威力」とは?)
威力業務妨害罪の「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいい、暴行・脅迫よりも広い概念です。
「威力」と認められた裁判例として、①客が満員のデパートの食堂配膳部に蛇をまき散らした場合(大審院昭和7年10月10日判決)、②競馬場の最も重要な本馬場に、幅約2メートル、長さ約120メートルにわたり平釘1樽分をまいた場合(大審院昭和12年2月27日判決)などがあります。
今回のケースの場合について検討します。
コンビニの床に画びょうが3000個もまかれている場合、これを踏みつけたり、あるいは転倒した際、体に刺さるおそれがあることから、安全確保のため営業をいったん中止せざるを得なくなると思われます。
以上のことから、コンビニに画びょうをまく行為は、人の自由意思を制圧するに足る勢力と考えられるので、「威力」に該当する可能性が高いでしょう。
(「業務」について)
「業務」とは、人(自然人、法人その他の団体を含みます)が職業その他社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務をいいます。
今回のコンビニの場合、通常、法人である株式会社か、自然人である個人が営利目的で営業しています。
コンビニの営業は、経営者である自然人又は法人が職業その他社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務と考えられるので、「業務」に該当するものと思われます。
なお、コンビニの営業は営利目的で行われますが、「業務」に該当するために営利性が必要というわけではなく、政党の結党大会のようなものであっても、「業務」に該当しえます。
(「妨害した」について)
判例によれば、威力業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害された結果の発生は必要ではなく、業務を妨害するに足りる行為が行われればよいとされています。
今回のケースのコンビニは画びょうが撤去されるまで2時間程営業が不能となっていますので、明らかに「妨害」されたものと考えられます。
以上のことから、Aさんがコンビニの床に画びょうをまいた行為が、威力業務妨害罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。
~逮捕されたら、まずは初回接見を検討~
弁護士に事件について話し、今後の手続きの進行、処分の見込み、取調べの対応方法につきアドバイスを受けることをおすすめします。
取調べでは、取調官からかなりきつい態様で質問され、負担に感じることがあるかもしれません。
弁護士に事件について話をすることにより、心理的な安心感を得られる効果も期待できます。
当番弁護士は、逮捕されている場合に、初回の1回だけ無料で接見にやってきます。
ただし、身柄解放活動、より有利な処分(不起訴、軽い量刑の判決)の獲得に向けた活動を行うことはできません(私選弁護人として選任すればこの限りではありません)。
国選の弁護士は、接見後の活動を行うことができますが、一定の要件を満たした上で、勾留決定が出ている段階でないと付けられないので、逮捕当日に接見を受けることは通常できません。(逮捕から勾留まで2~3日かかることが通常です)
また、自分で弁護士を選ぶことができないため、しばしば付けられた弁護士と相性が合わない、やる気が感じられないといった不満を持つ方もおられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、有料で初回接見を行っております。
弁護士のスケジュールが空いていれば、逮捕当日に接見を受けていただくこともできます。
また、弁護士費用等の条件が折り合えば、接見を行った弁護士を私選弁護人として選任していただくことも可能です。
ご家族、ご友人が威力業務妨害事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
脅迫罪と強要罪
脅迫罪と強要罪
神奈川県横須賀市に住むAさんは,スマートフォンを使って,ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており,攻撃される準備が行われている,逃げたまえ」などというメールを送信し,Vさんに引っ越しを余儀なくさせたという強要罪の容疑で,神奈川県田浦警察署から呼び出しを受けています。
Aさんは,脅迫罪と強要罪の違いや今後の対応などに暴力事件を含む刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)
~ はじめに ~
上の事例をみて脅迫罪?強要罪?と判断に迷われた方おられるのではないでしょうか?
そこで,まずは,脅迫罪,強要罪の内容について解説したいと思います。
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
= 害を加える旨の告知(害悪の告知) =
害悪の告知は,一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。
人を畏怖させるに足りるものであったか否かは,告知に至るまでの経緯,告知した人(年齢,性別など),告知内容,告知された相手(年齢,性別など)などの状況から判断されます。
したがって,同じ内容でも人,相手などによっては「害悪の告知」と認められることもあれば,認められないこともあります。
過去の判例(昭和35年3月18日)では,「出火御見舞申上げます,火の用心に御注意」が害悪の告知と認定されましたが,これは暴力団組員から同じ暴力組員への脅迫行為に関する事例判断です。
* 「夜道を歩くときは気をつけろよ」 *
例えば,企業のSNSアカウントに「(企業をを運営する)社長さん,夜道を歩くときは気を付けろよ」等書き込みをしたらどうでしょうか。
あくまで企業のSNSアカウントに対しての行為なので,社長に対して「告知した」とは言いづらそうですが,例えば,この文言を社長自身のSNSアカウントに投稿したら脅迫罪となる可能性は高いでしょう。
SNSでの軽率な発言であっても,脅迫罪に当たり得ることは肝に銘じておいた方がよさそうです。
~ 強要罪 ~
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。
ただし,強要罪は,結果として相手方に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害したことが必要ですから,強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
~ 脅迫罪と強要罪の違い ~
脅迫罪と強要罪は大きく,以下の違いがあります。
= 犯罪の性質,要件の違い =
以上からもお分かりいただけますように,脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪,強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。
また,脅迫罪の「害悪の告知」は,それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し,強要罪の「害悪の告知」は,結果として相手方に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
= 法定刑の違い =
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で,強要罪は3年以下の懲役です。
両者を比べてみるとよく分かりますが,強要罪には罰金刑がありません。
つまり,強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。
裁判所は,土日は開廷してくれませんから,会社員の方であれば休暇を取る必要があります。
また,慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。
判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。
対して,脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから,そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪,強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強要罪については特に,検察官が起訴する前に被害者と示談を成立させ,不起訴処分獲得を目指すことが重要です。
お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,無料相談,初回接見サービスをお申し付けください。
警視庁福生警察署で逮捕~正当防衛
警視庁福生警察署で逮捕~正当防衛
【事件】
仕事から帰宅途中のAさんは、東京都羽村市にある公園に差し掛かったところで若者に因縁をつけられました。
「睨んだだろう」と言う若者に対して、全く身に覚えのないAさんは「睨んでいない」と主張しましたが、その態度に若者は激高しました。
若者が手に持っていたサバイバルナイフを振りかざし今にも襲い掛かろうとしたので、Aさんは手に提げていた通勤バッグで若者の頭を殴りました。
走って立ち去ろうとしたAさんでしたが、騒ぎを聞きつけた警視庁福生警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その時、若者は脳震盪で病院に搬送されていました。
Aさんは、「自分は正当防衛をしただけなのに犯罪になってしまうのか」と不安になり、家族が接見を依頼した弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【正当防衛】
急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為を正当防衛といいます。
正当防衛が認められれば、違法性がないとして仮に起訴されても無罪になります。
以下、少し細かく正当防衛が成立するための要件についてご紹介します。
・急迫不正の侵害があること
自分や他人に危険が今まさに差し迫っており、その危険の発生原因が正当な理由に基づかない場合に、急迫不正の侵害があると言うことができます。
・自己又は他人の権利を防衛するためにとられた行為であること
ここでいう権利とは、広く一般的に法律等で保護されている権利を意味します。
危険が自分自身や、あるいは他人のこれらの権利を脅かそうとしている際に、その権利を守る目的でなされた行為である必要があります。
・やむを得ずにした行為であること
防衛者がその行為を行わなければ、危険にさらされた権利が守れないものであったといえなければなりません。
また、攻撃内容に対して、反撃内容がその強さに応じた相当なものでなくてはなりません。
例えば、素手で殴りかかってきた相手に対してけん銃で反撃したような場合には相当であるとは言えず、そうした場合、過剰防衛であるかどうかが問題となりえます。
・侵害者に向けられた行為であること
防衛行為と認められるためには、反撃が侵害者に向けられていなければなりません。
もし反撃行為が全く関係のない第三者に当たった場合には、その第三者との関係では緊急避難の問題となり、侵害者との関係では、反撃行為が各種未遂罪の行為に該当する場合に正当防衛の問題として扱われる場合があります。
ドラマなどでよく正当防衛という言葉を耳にすると思いますが、これらの細かい条件をそれぞれクリアしないと、法律的には正当防衛と認められるのは難しくなります。
逆に、正当防衛が認められれば、その行為については犯罪が成立しないことになります。
【Aさんの場合】
Aさんは若者を殴って気絶させていますので、客観的にはAさんは暴行罪あるいは傷害罪の容疑で警察の捜査を受けることになります。
ここで、Aさんがバッグで若者を殴って気絶させたことについて正当防衛が成立するかどうかみていきましょう。
まずAさんは若者にナイフで襲われており、侵害の急迫性が認められます。
また、若者のナイフで襲い掛かる行為は正当行為等で正当化されるものではなく、不正性も認められます。
Aさんのバッグによる攻撃(反撃)は、ナイフで襲い掛かろうとしている若者から身を守るためにとられたもので、そうしなければAさんの身体が傷つけられたでしょう。
したがってAさんの反撃は自身の身体ないし生命という自己の権利・利益を守るためにとられた行為であるといえます。
Aさんは逃げる余裕もないまま、他に身を守る方法もなく若者をバッグで殴っています。
殺傷性のあるナイフに対してAさんの武器はバッグであり、反撃手段の強度も相当であると考えられ、そうすると「やむを得ずにした行為」の要件は満たされると考えられます。
また、この反撃はAさんを襲った若者に対してとられた行為で、侵害者に向けられた行為です。
以上より、Aさんがバッグで殴った行為が正当防衛であると認められる可能性は非常に高いといえます。
しかし、警察官の厳しい取調べ等、捜査の過程で自分にかけられた暴行や傷害の容疑内容を認めるような発言をしてしまった場合、起訴されてしまったり、最悪の場合前科がつくことになってしまうかもしれません。
もし身を守るためにとった行為に暴行や傷害の容疑がかけられてしまった場合は、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
早い段階で適切な対応をすることにより、不起訴処分や無罪を得られる可能性が高くなります。
正当防衛の状況下でとられた行為について逮捕されてしまった方、ご家族やご友人が警視庁福生警察署に逮捕されてしまった方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円
福岡県直方市の落書き事件
福岡県直方市の落書き事件
~ケース~
福岡県直方市在住のAさんは市民団体に所属しており,熱心な活動家であった。
ある年,福岡県直方市の市長選に所属する市民団体と政治思想を相いれないXが当選した。
AさんはXが市長となったことに抗議するために福岡県直方市内のX氏の後援会事務所の外壁にスプレーで抗議の声明を大書した。
その後,防犯カメラや目撃者の証言などによりAさんは福岡県直方警察署に建造物損壊罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
~落書き~
今回のケースでAさんは建造物損壊罪で逮捕されています。
建造物損壊罪は刑法260条で次のように規定されています。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ここで,軽犯罪法1条33号の次のような規定も確認しておきましょう。
軽犯罪法1条33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
他人の建造物へ落書きする行為は軽犯罪法1条33号の「汚した者」に該当するといえますので,落書き行為は軽犯罪法違反となると考えられます。
ところで,今回のケースではAさんは建造物損壊罪の疑いで逮捕されています。
外壁などに落書きをすることは建造物損壊罪のいう「損壊」に当たるのでしょうか。
損壊とは客体の用法に従って使用することを事実上不可能にする行為をいいます。
物理的に破壊し,またはその形態を変更することは必ずしも必要ではなく,本来の目的に使用することができない状態にする行為も含まれます。
裁判所(東京地判平成16・2・12)は刑法260条の「損壊」について以下のように述べています。
建造物の本来の効用を滅却あるいは減損させる一切の行為をいい,物理的に建造物の全部又は一部を毀損する場合だけではなく,その外観ないし美観を著しく汚損することによっても,建造物の効用を実質的に滅却ないし減損させたと認められる場合があり,このような場合には,たとえその建造物の本質的機能を害するには至らなくても,その行為は「損壊に」当たるとするのが相当である。
軽犯罪法1条33号との関係では,建造物の外観ないし美観を汚損する行為が建造物損壊罪所定の損壊にまで当たるといえるか否かについては,建造物の性質,用途ないし機能との関連において,汚損行為の態様,程度,原状回復の難易度等,諸般の事情を総合考慮して,社会通念に照らし,その汚損によってその建造物の効用が滅却ないし減損するに至ったか否かを基準として判断すべきである。
裁判となった事件は,区立公園の公衆便所の外壁にラッカースプレーで外壁をほとんど埋め尽くすような形で「反戦」「戦争反対」などと書いたものです。
この事件では落書きを洗剤やシンナーなどで消去することが出来ず,壁面の再塗装でしか消去できず,再塗装には7万円の費用がかかるということで,建造物損壊罪のいう「損壊」であると認定されました。
~Aさんの場合~
Aさんの行為が建造物損壊罪となるかどうかはAさんが行った行為が上記の「損壊」の要件に当たるかどうかによります。
たとえば,水で簡単に消せるというような場合には原状回復が容易ですので軽犯罪法違反にとどまるといえます。
しかし,裁判になった事件のように,シンナーなどを使っても消すことが出来ず,再塗装が必要であるような場合には建造物損壊罪が成立してしまうでしょう。
建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑のみですので,起訴されてしまった場合には刑事裁判が開かれることになります。
しかし,建造物損壊罪は危険が生じるような物理的な損壊の場合や今回のケースのような損壊というように事案によって犯行態様が異なります。
今回のケースのような落書きが損壊とされた場合,損壊の認定は原状回復の困難さ等が要件となっています。
そのため,再塗装の費用などを被害弁償として被害者の方に支払うことで検察官が事件を不起訴とする可能性もあります。
被害弁償などをして不起訴を目指す場合または建造物損壊罪となるか軽犯罪法違反となるかを争うような場合には刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼するのをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
建造物に落書きをしてしまい逮捕されてしまった方,警察に呼ばれお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
【虐待】傷害罪の幇助で逮捕・無罪主張
【虐待】傷害罪の幇助で逮捕・無罪主張
京都市左京区に住んでいるAは、夫Bが自らの子であるV(8歳)に対し、虐待行為をし怪我を負わせていたにも関わらず、これを止めることもせず黙認し続けていた。
近所の人からの通報により、虐待行為が発覚し、京都府下鴨警察署の警察官は、AをVに対する傷害罪の容疑で逮捕した。
これに対し、Aは一貫として犯行を否認している。
Aの家族は、暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~虐待事例と共犯~
本件では、BがVに対して傷害行為をしたことは明らかですが、A自体は何もしていません。
刑法が原則として(明文のない限り)作為による犯罪行為のみを処罰していることからすると、Aは何ら刑事責任を負うことはないとも思えます。
刑法204条に規定されている傷害罪も、「人の身体を傷害した者」は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、「人の身体を傷害」するという積極的な行為の処罰を前提とした規定となっています。
まず、犯罪を直接的に実行していない者が第1次的な刑事責任を負う場合として(共謀)共同正犯(刑法60条)があります。
もっとも、これが成立するには、共犯者間での共謀のほか、自己の犯罪として何らかの積極的な役割を果たしたことが求められるため、本件のようなケースでは(共謀)共同正犯の責任まで負わせることは難しいと考えられます。
仮に共同正犯としての責任を問うことは難しいとしても、幇助犯(62条1項)として犯罪の成立が考えられます。
幇助犯とは、正犯の犯罪の実行を容易する者をいいます。
これは、不作為による場合でも成立すると考えられており、具体的には本件のように夫(や妻)が子に対する虐待をしている場合に、妻(や夫)がこれを止めない場合に犯罪阻止義務違反として問題になることになります。
すなわち、犯罪を阻止しないことが、正犯の犯罪を容易にしているという点で不作為による幇助行為として刑事責任の対象になってくるのです。
したがって、本件では、AにBの子Vに対する傷害行為(虐待)を阻止する義務があったのか等が争点になってくると考えられます。
~家族内の虐待事件と刑事弁護活動~
まず、弁護士としては、Aのような何ら作為を行っていない者に刑事責任を負わせていいのか、本人の言い分も含めしっかりと検討する必要があるでしょう。
特に虐待事件では、家庭内環境など様々な要因を調査・分析する必要があります。
例えば、虐待事件においては、Aが恒常的にBから暴力(ドメスティック・バイオレンス等)を受けていた等、犯罪被害者である側面を有することも多く、本当に虐待を止めることができたのか具体的な検証が必要になります。
したがって、弁護士としては、Aに幇助犯を含め刑罰を伴う刑事責任を負うべき事案なのかを慎重に判断し、場合によっては無罪主張をしていくことも考えられるでしょう。
こういった虐待事件が報道などで耳目を集めると、どうして子どもを守れなかったのかという批判が世間からなされることも少なくありません。
しかし、そういった感情的批判と、当該行為が刑罰によって処罰されるべきものであるかは、全く別物であるというべきであり、被疑者の言い分に真剣に耳を傾けるのが弁護士としての重要な職務となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、虐待による傷害事件を含む暴力事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
正犯事件のみならず、(従属的な)共犯事件についても経験が豊富な弁護士が刑事事件についての弁護活動をうけたまわります。
無罪主張を含め、不起訴や無罪獲得といった被疑者のための弁護活動を行ってまいります。
傷害事件(虐待)で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)