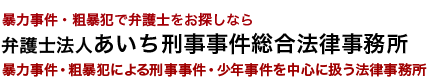未分類
家庭内暴力で逮捕
家庭内暴力で逮捕
夫の妻に対する暴力や、親の子に対する行き過ぎたしつけ等の家庭内暴力により、傷害罪などの暴力犯罪へつながるケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
東京都立川市在住の主婦Vさんは、会社員である夫Aの暴力的な言動に悩まされており、ある日、Vさんが作った夕食について会社から帰ってきたAは「冷めていて不味い。こんな飯を食わせるのか」と急に怒り出し、Vさんの顔を3度ほど平手で殴る暴行を行いました。
Vさんの顔が腫れて病院に行くと、医師はVさんの鼻骨が骨折しているとして全治2か月の重傷と診断しました。
Aの家庭内暴力に耐えきれなくなったVさんは、怪我の診断書を持って警視庁立川警察署に夫の暴力被害の相談に行き、警察は傷害罪の疑いでAを逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月16日、愛知県名古屋市の男性(75歳)が妻(64歳)の顔を殴り、大けがをさせたとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
具体的には、16日午前、名古屋市の集合住宅の被疑者男性から「妻の意識や呼吸がない」と119番通報があり、女性は病院に運ばれたものの、その後間もなく死亡が確認されました。
死亡したのは女性は顔が腫れていたため、不審に思った病院が、刑事事件の可能性があるとして警察に通報し、警察は被害者を殴って鼻を骨折させるなどした傷害の疑いで、被害者の逮捕に踏み切りました。
警察の調べに対し、被疑者「ご飯の支度をしてくれなかった」と動機を語っており、警察は傷害致死罪での立件を視野に、死亡した経緯などくわしく調べています。
昨今では、千葉県野田市において父親による家庭内暴力によって10歳の娘が暴行の果てに死亡してしまった事件を中心に、家庭内暴力に対する厳しい処罰を求める意見と家庭内暴力が顕在化する前に事前に第三者による介入を強く求める意見が主張されるようになっています。
従来、家庭内で発生した刑事事件については、家族間特有の緊密な人間関係に基づく関係の破綻などが動機となっていることが多く、特に被害者が加害者(被疑者)が家族同士であることもあって、被害の申告によって事件が公開されることを嫌がる傾向が強く、警察等の捜査機関も家庭内での紛争に基づく刑事事件では、特に被害が深刻な場合にのみ介入し、その程度を超えないものについては極めて介入に消極的であるのが通常でした。
しかし、昨今では、家庭内暴力を規制する特別法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されたり、平成29年の刑法改正によって、親などの監護者による子に対する性的行為を処罰する規定(刑法第179条、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪)が新設される等の動きがあり、閉鎖的な家庭環境ゆえに被害の声を上げられない被害者の救済に向けた取組みが進んでいます。
このような事情を背景に、刑事弁護分野においても、家庭内暴力によって刑事事件化した場合には、迅速な逮捕に踏み切るケースが多くなってきている印象があり、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任となった家庭内暴力による傷害被疑事件でも、被疑者が逮捕された段階で、被疑者のご両親からお話が寄せられました。
家庭内暴力による傷害罪の刑事事件では、被疑者の身柄を拘束しなければ、家庭という密室ゆえに罪証(証拠)隠滅が図られる可能性が高く、また、再犯によって更なる深刻な被害が生じる可能性もあるため、延長を含めて最大20日間の勾留が決定される見込みが非常に強いです。
それゆえ、刑事事件化した場合には、早期に刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、複雑な家庭内の人間関係の整理と、被疑者が捜査妨害や再犯を行わないよう環境調整を行い、在宅での事件が進められるよう被疑者の身柄釈放に向けた活動を早期に行ってもらうことが重要となるでしょう。
家庭内暴力による傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
夫婦・カップルの喧嘩で逮捕
夫婦・カップルの喧嘩で逮捕
夫婦やカップルなど、同居や同棲したり、生活状況が極めて密接な関係における暴力行為で刑事事件化した場合の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例1>
東京都昭島市在住の自営業の男性Aさんは、交際中の女性Vさんとドライブの途中、ささいな口論から大喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんが激しく抵抗したため、Aさんはさらに力を込めて制止したところ、Vは「痛い」と大声で悲鳴を上げて、周囲の通行人に対して助けを求めたため、通行人が警察に110番通報し、駆けつけてきた警視庁昭島警察署にの警察官によって、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事件例2>
東京都昭島市在住の会社員男性Aさんは、その妻Vとの些細な口論から激高してしまい、Vを突き飛ばす暴行を行ってしまいました。
Vは壁に頭をぶつけて出血してしまったため、市内の病院に行って医師に負傷の原因を伝えたところ、病院は家庭内暴力の可能性があると警視庁昭島警察署に通報を行いました。
警察は、家庭内暴力の可能性があるとして、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕し、慎重に捜査を進めています。
(※上記いずれの事件例もフィクションです)
【夫婦・カップル間の暴力犯罪は身柄拘束の可能性が高い?】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務に寄せられるご相談の中で、若いカップルの喧嘩や20代から40代の夫婦間の暴力から刑事事件に発展してしまった例がしばしばあり、特に頭に血が上りやすい男女関係においては、相手を許せないという気持ちから警察を呼んで刑事事件に発展してしまう事例も見受けられます。
カップルの喧嘩による暴力事件では、多くの場合、相手に対する行き過ぎた感情や嫉妬心などを原因としており、場面としては、カップルが二人だけの状況(例えば自家用車の中)で、片方が別れ話を切り出す等、一方が感情的になって他方に食い下がった結果、刑事事件化してしまうというケースが多く見受けられます。
他方、夫婦間の暴力事件の場合、男性による一方的な暴力やあまりに悪質な暴行などでは被害者の処罰感情が高い事案も見られますが、事案としては比較的稀なケースであり、どちらかというと、双方に原因がある口論からカッとなって暴力に発展してしまい、負傷の怪我を病院に見せたところ、意図せず病院が警察に通報して刑事事件化してしまい、これほど大事になるとは思わなかったとして、被害者が処罰を求めず早急な事態の鎮静化を望む場合も多く見受けられます。
ただし、上記いずれの暴力事件の場合でも、弊所に寄せられた、痴話喧嘩から発生した暴行罪または傷害罪のすべての刑事事件について、被疑者の方が逮捕にされている確率が非常に高いことに注目する必要があります。
これは、被疑者と被害者が非常に密接な関係にある場合、同居(同棲)している場合はもちろんのこと、お互いが相手の住所や連絡先などを知っている場合がほとんどであり、捜査機関側からすると、逮捕して被疑者の身柄を拘束しなければ、さらに加害行為を行ったり、被害者を威迫して被疑者に有利になるような証言を強要する等、罪証隠滅の恐れがあるからと思われます。
それゆえ、夫婦やカップルの喧嘩から発生した暴力事件では、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放に動いてもらうことが必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、このような暴力事件の逮捕事案に迅速に対応し、数々の勾留阻止に成功しています。
夫婦やカップルの喧嘩で傷害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
運転中カッとなって傷害罪で逮捕
運転中カッとなって傷害罪で逮捕
交通マナー等のトラブルで逆上し、暴行をふるって相手を負傷させてしまった傷害罪等の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、東京都目黒区在住の会社員Vさんが、町内の道路を自動車で走行していたところ、車道にはみ出して歩行している若者3人組が道路を塞いでいました。
Vさんがクラクションを鳴らして道路から退くように合図したところ、クラクションに逆上した若者らがVさんの自動車を取り囲み、自動車の運転席ガラスを破壊してドアを開け、座席からAさんを引きずりだして殴る蹴るの暴行を加えました。
暴行を受けたAさんはすぐに110番通報をし、警視庁碑文谷警察署が捜査を開始し、間もなく自称自営業者Aら3人の男性を傷害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、後ろからクラクションを鳴らした車に数百メートル並走し、相手の運転手を引きずり降ろして暴行を加えたとして、熊本県警八代警察署が令和元年11月7日、八代市のアルバイト男性と同市の農家の男性の2被疑者を傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕容疑は、同年9月16日午前0時半ごろ、八代市新町の県道で熊本市の会社員男性が運転する車のドアを開けて男性を引きずり降ろし、顔面を殴ったり腹部を蹴ったりして約2週間のけがをさせたとしている。
被疑者2名とも「手は出していない」と暴行の事実を否認しているとのことです。
昨今、あおり運転による刑事事件化の報道が盛んであり、その原因として、追い越されて腹が立ったとか、クラクションの音で威嚇されたように感じて逆上した等の動機が供述されることが目立ちます。
あおり運転の厳罰化の流れの中で、捜査機関は悪質なあおり運転に対して、道路交通法違反、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して厳正な捜査を行うよう通達を出しており、中には殺人罪で立件されたあおり運転の刑事事件も見受けられます。
とは言え、あおり運転のような悪意ある行為とは別に、他ドライバーの危険運転や交通マナー違反を注意を促すためにクラクションを鳴らす等の遣り取りは日常的に行われているところ、頭書刑事事件例のように、ここからさらに刑事事件に発展してしまうケースもあるようです。
このような公道での暴力犯罪は、監視カメラや多くの目撃者、ドライブレコーダー等に記録されるため、多くの場合、犯人の特定が迅速で、速やかに逮捕される可能性が高いと言えます。
上記実際の刑事事件では、被疑者らは暴行の事実を否認していますが、捜査機関が防犯カメラ等の証拠を収集した結果、有罪の見込みが強い有力な証拠が集められた場合には、被疑者らは検察官によって起訴され、公開の刑事裁判の末に有罪判決を受ける可能性もあるでしょう。
このような傷害罪の刑事事件では、当事者間に感情のわだかまりが強く、示談交渉が難航する可能性もあり、被害者が厳罰を望む結果、検察官によって起訴されてしまうケースも考えられますので、逮捕後すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、弁護士から刑事事件の手続きと処罰の見込みを聞くことが大切です。
逆上して暴行し傷害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
電車内の暴力で刑事事件化
電車内の暴力で刑事事件化
電車内の口論などから暴力沙汰に発展し、暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪に発展した場合の刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
東京都小平市在住の会社員Aさんは、会社通勤のため混雑した電車に乗車していた際、インフルエンザ対策のためのマスクをつけていない高齢男性Vが大きな音を立てて咳をしていたため、AさんはVに対して「マスクをつけてください。そうでなければ電車に乗らないでください」と言ったところ、VがAの胸倉を掴んできたため、電車内で殴り合いの暴力沙汰に発展し、乗客の一人が警察に通報したため、二人は次の駅で待ち構えていた駅員に下ろされ、警視庁小平警察署に事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取を終えた後で解放されましたが、また次回呼び出すと警察に出頭要請を受けたため不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、新型コロナウイルスの感染拡大で不安が広がる中、電車内でのマスクをめぐるトラブルが増えているとの報道を受け、いくつか報道された電車内でのトラブルを組み合わせて創作したフィクションです。
報道されたトラブル事例によれば、電車で「マスクをしていないなら降りろ」と咳をしている人に怒鳴って降りるよう迫ったという事例が紹介されました。
また、令和2年3月25日、北海道旭川市のスーパーにおいて、マスクを買うために列を作っていた79歳の男性が、一度列を離れ、また同じ場所に戻り、並ぼうとしたところ、それを見ていた35歳の女性が「割り込みだ」と指摘すると、男性が逆上し、女性に対して体当たりをする、腕を叩くなどの暴力を振るったため、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されたと報道されました。
コロナウイルスの感染拡大の以前から、電車内などの人が密集する密閉空間においては乗客のストレスが高まりやすく、乗客同士のいざこざから暴力沙汰に発展し、刑事事件化または逮捕される例は頻繁に発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、法律相談や、逮捕されてしまった被疑者の家族の方による初回接見依頼をいただくことがあります。
その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。
このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。
また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。
上記刑事事件程度の暴行による傷害罪の刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。
このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。
ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。
電車内における暴力事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
子供の虐待事件で逮捕が不安
子供の虐待事件で逮捕が不安
子供の虐待事件で逮捕が不安だというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
大阪府高石市に住んでいるAさんは、夫であるBさんと、Bさんとの子供であるVさん(小学3年生)と暮らしていました。
Aさんは、Vさんが言うことを聞かないことに苛立っており、たびたびVさんに暴力を振るってしまっていました。
ある日、Vさんが通う小学校でVさんの体のあざが発見され、VさんがAさんから暴力を受けていたことが判明。
Vさんは児童相談所に保護されることになりました。
児童虐待の疑いがあると伝えられたAさんは、今後自分が大阪府高石警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童虐待事件
厚生労働省のまとめによると、2019年度に全国の児童相談所が児童虐待として対応した件数は19万3,780件であり、過去最多であったそうです。
児童虐待は、今回のAさんのケースのような暴行などによる身体的虐待のほか、育児放棄(ネグレクト)、性的虐待、心理的虐待の4種に分けられるとされていますが、2019年度に対応された児童虐待では、心理的虐待が10万9,118件、身体的虐待が4万9,240件、ネグレクトが3万3,345件、性的虐待が2,077件となったそうです。
児童虐待というと身体的虐待を思い浮かべる方も多いでしょうが、2019年度では心理的虐待が半分以上を占めることとなっています。
こういった児童虐待行為は、まとめて「児童虐待罪」とされるわけではなく、児童虐待行為自体がそれぞれ当てはまる犯罪になります。
例えば、今回のAさんはVさんに対して暴力を振るっているようです。
こうした場合、刑法の傷害罪や暴行罪の成立が考えられます。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
子供へのしつけと考える方もいるかもしれませんが、しつけとして相当な程度を超えていきすぎてしまえば児童虐待となり得ますし、当然犯罪に問われることとなります。
他の児童虐待の態様であっても、育児放棄(ネグレクト)をすることで刑法の保護責任者遺棄罪などが成立する可能性がありますし、心理的虐待をすることで侮辱罪や傷害罪になることも考えられます。
性的虐待では監護者わいせつ罪・監護者性交等罪や児童福祉法違反などの成立も考えられます。
児童虐待といってもその態様によって成立する犯罪は様々ですから、児童虐待事件の当事者となった場合には、まずは弁護士に容疑をかけられている犯罪やその見通しについて詳しく聞いてみることが必要でしょう。
・児童虐待事件で逮捕が不安
今回のAさんの事例では、まだ警察などの捜査機関が介入しておらず、刑事事件化される前のようです。
しかし、児童虐待があったとなった場合、警察が介入して児童虐待事件として刑事事件化される可能性は否定できません。
そうした場合、被害者である子供と加害者である親が同じ家庭内にいるという児童虐待事件の特性から見ても、被疑者であるAさんが逮捕される可能性があります。
逮捕される可能性がある場合、前もって弁護士に相談・依頼し、逮捕されてしまった場合の準備をしておくことが重要です。
例えば、Aさんの両親などに協力してもらい、Aさんの行動の監督や家庭での行動の改善指導をしてもらうよう準備し、その主張をするための証拠づくりをすることや、Aさんが同じことを繰り返さないために原因や改善策を探れるようカウンセリングへ通うようにするといったことをしておき、それを証拠化しておくことなどが考えられます。
子供のケアや再発防止のためにも、刑事事件の専門家からアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行なっています。
逮捕が不安だという方もお気軽にご相談いただけます。
逮捕前に専門家である弁護士の話を聞くことで、具体的にすべきことが明確になり、不安の軽減にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。
痴漢行為と強制わいせつ事件
痴漢行為と強制わいせつ事件
痴漢行為と強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪市中央区にある駅構内の女子トイレに好みの女性であったVさんが入っていくのを見計らい、Vさんについて行きました。
そしてAさんは、Vさんに抱き付いて個室に連れて行き、服の上からVさんの臀部を撫でまわすなどしました。
Vさんが悲鳴をあげて助けを呼んだことで駅員が駆けつけ、通報を受けた大阪府南警察署の警察官によってAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士から強制わいせつ罪の法定刑等を聞き、予想以上に重い刑罰であったことに驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢行為で強制わいせつ事件
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、日本には「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
一般によく言われる「痴漢」とは、体を触ったり下半身を押し付けたりといったわいせつな行為を電車や道路、施設などでする行為や人を指すものであり、それ自体が罪名であるわけではないのです。
ですから、痴漢行為をして成立する犯罪は、すでにある法律の中からその痴漢行為が該当する犯罪となります。
すなわち、痴漢と一言に言っても、事件ごとに成立する犯罪は異なるということになるのです。
痴漢行為によって成立する犯罪としてよく取り上げられるのは、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反する迷惑防止条例違反と、今回のAさんの逮捕容疑でもある強制わいせつ罪です。
大阪府迷惑防止条例第6条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
大阪府迷惑防止条例第17条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2号 第6条の規定に違反した者(第15条の規定に該当する者を除く。)
※注:「第15条」では、第6条第1項2号・第3号、第2項・第3項に関わる部分を規定。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ご覧の通り、この2つの犯罪の刑罰は大きく異なるため、どちらの犯罪が成立するかによって予想される刑事手続や処分も異なってきます。
条文から読み取れる迷惑防止条例と強制わいせつ罪の大きな違いとしては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」と手段が限定されているのに対し、迷惑行為防止条例は「公共の場所又は公共の乗物」と犯行の場所が限定されているという点が挙げられます。
よく「服の上から触る痴漢行為は迷惑防止条例違反、服の下から直接身体に触る痴漢行為は強制わいせつ罪」と言われますが、このように2つの犯罪は手段や場所によって違いが出てくるため、直接体に触れたか否かは絶対的な基準ではありません。
今回のAさんの事例を考えてみましょう。
Aさんの起こした痴漢事件の犯行場所は駅構内の公衆トイレであり、Vさんの服の上から触っているため、迷惑行為防止条例違反が適用されるように見えます。
しかし、AさんはVさんを個室のトイレに連れて行った上で抱き着いています。
この行為がVさんの犯行を押さえつけるほど強い「暴行」であると判断されれば、「暴行」を用いて痴漢行為=「わいせつな行為」をしていることになるため、強制わいせつ罪が成立することも考えられます。
今回の事例ではそのように判断されたため、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
なお、今回の事例のAさんは女子トイレにも無断で入っていることから、建造物侵入罪(刑法第130条)にも問われる可能性があります。
痴漢というと具体的な犯罪名がわからないためか、簡単に考えてしまう人もいるようですが、強制わいせつ罪などの重い犯罪が成立することも考えられます。
もしも当事者となってしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、サポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件などの性犯罪・暴力事件にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
自殺関与罪を弁護士に相談
自殺関与罪を弁護士に相談
自殺関与罪を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、千葉県八千代市に住んでいる友人のVさんが交際相手との関係や家族関係にひどく悩んでいることを聞き、その都度相談に乗っていました。
VさんはAさんに相談する際、たびたび「生きているのが苦しいからもう死んでしまいたい」と言うようなことを話していました。
ある日、Vさんが「もう耐えきれない。死んでしまおうと思う」といったことを繰り返していたことから、AさんはVさんを不憫に思い、「練炭なら苦しくないらしい。道具は用意してあげる」と言って、煉炭などを購入し、Vさんに渡しました。
その後、VさんはAさんの用意した練炭等の道具を使って自殺してしまい、千葉県八千代警察署の捜査が始まりました。
捜査の結果、Aさんが練炭等の道具を準備していたことがわかり、Aさんは自殺幇助罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・自殺関与罪と自殺幇助罪
日本では、自殺という行為自体が罰されることはありません。
自殺自体が違法な行為ではないという説や、自殺という行為が違法な行為だとしても処罰するほど大きな違法性はないという説、自殺という行為は違法な行為ではあるものの自殺する状況にまである人を非難することはできないという説など様々な説がありますが、総じて自殺すること自体を罰することはできないと考えられているためです。
ですから、自殺をした人が自殺をしたことによって何か犯罪に問われるということはありません(自殺をしたことで別の犯罪に触れる可能性はあります。)。
しかし、その自殺に別の人が関与していた場合は話が変わってきます。
自殺した本人ではなく、その自殺に関わっていた人がいた場合、その人については自殺関与罪と呼ばれる犯罪が成立する可能性が出てくるのです。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
ここで、自殺に関わった人を違法だということに違和感をもつ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自殺するという行為自体が違法であろうとなかろうと、自殺に関与するということは処罰すべきであると考えられています。
例えば、そもそも自殺する行為は違法な行為であるとする立場に立って考えてみましょう。
自殺に関与するということは、その違法な行為に関わる共犯者となるため、違法なことと考えられます。
対して自殺する行為は違法ではないという立場に立った場合でも、自殺に関与するということは、本人のみがすることのできる生命に関する意思決定に他人が影響を及ぼして生命を害する行為をすることになります。
こうしたことから、どういった立場に立ったとしても、自殺に関与する行為は違法なものであるとと考えられているのです。
今回のAさんの逮捕容疑である自殺幇助罪は、先ほど条文を挙げた自殺関与罪と呼ばれる自殺に関連した犯罪のうちの1つです。
刑法第202条の条文のうち、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」たという部分に当たるのが自殺関与罪であり、自殺を「教唆」した場合には自殺教唆罪、自殺を「幇助」した場合には自殺幇助罪と呼ばれます。
なお、刑法第202条後段の「人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した」という部分にあたる場合には、嘱託殺人罪または同意殺人罪に問われることになります。
自殺幇助罪の「幇助」とは、簡単に言えば手助けをすること、その行為をすることを容易にすることを指します。
つまり、自殺をしようと思っている人に対して自殺をすることを容易にする手助けをすると、自殺幇助罪が成立するのです。
ここで重要なのは、自殺幇助罪はあくまですでに自殺を決意した人に対して自殺をする手助けをした際に成立する犯罪であるということです。
自殺を考えていない人に自殺をする意思を持たせた場合は、自殺幇助罪ではなく、自殺教唆罪や、状況によっては殺人罪が成立する可能性が出てきます。
さらに、たとえ手助けの気持ちでしたといえど、自殺をしたいという人に対して直接手を下すようなことをすれば、自殺幇助罪ではなく嘱託殺人罪が成立する可能性が出てくることになるでしょう。
今回のAさんは、Vさんが自殺するための練炭を用意してVさんに渡しているようです。
Aさんが練炭を用意したことで、Vさんの自殺はすることが容易になったと言えます。
そして、Vさんは元々自殺をする決意を持っていたところにAさんがそういった手助けをしているわけですから、今回Aさんには自殺幇助罪が成立すると考えられるのです。
自殺関与事件では、人の生命に関わる犯罪であることも関連して刑罰も重く、そして捜査も厳しいものになることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から丁寧にフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
噂話が名誉毀損事件に?
噂話が名誉毀損事件に?
噂話が名誉毀損事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、埼玉県さいたま市中央区にある会社に勤めている会社員です。
ある日、Aさんは会社の近くで痴漢事件が起きたことを知り、その時間に同僚のVさんが現場近くにいたところを目撃していたことから、Vさんが痴漢事件の犯人に違いないと思い込みました。
そしてAさんは、会社の休憩室で、同僚のXさんやYさんの2人に「Vさんが痴漢事件を起こした」という話をしました。
その後もAさんは上司のZさんと休憩時間が重なった時にも「Vさんが痴漢事件を起こした」という話をしました。
こうしたことが重なり、Aさんは会社の上司や同僚、後輩合わせて7人に同じ話をしました。
その結果、「Vさんは痴漢魔だ」という噂が会社に広まってしまいました。
Vさんは困ってしまい、埼玉県浦和西警察署に相談。
Aさんは名誉毀損罪の容疑で埼玉県浦和西警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは噂話程度のつもりでいたため、突然刑事事件の当事者になったことで今後の手続きに不安を感じ、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・噂話程度でも名誉毀損罪になる?
名誉毀損罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
昨今、SNSでの誹謗中傷などでも話題に登ることのある名誉毀損罪ですが、今回の事例のAさんは会社で噂話をして名誉毀損罪に問われているようです。
名誉毀損罪が成立する条件として「公然と」事実を示すことが必要ですが、今回の事例のAさんは休憩室などで合計7人に対して噂話程度に話しただけです。
こうしたケースでも名誉毀損罪の「公然と」という条件に当てはまるのでしょうか。
名誉毀損罪のいう「公然と」とは、不特定又は多数人が知り得る状態を指します。
昨今話題になることの多いSNSでの誹謗中傷は、SNSという不特定多数の人が閲覧可能な場で行われることから名誉毀損罪の「公然と」という条件を満たすことになります。
今回の事例では、確かにAさんが話した場所としては、会社の休憩室という個室であり、話した相手も少数といえます。
しかし、たとえAさんが直接話した相手が特定の人で少数しかおらず、また場所が限定的だったとしても、それが他の人に伝播し、結局不特定又は多数人が知り得る可能性がある以上、公然性は認められると考えられます。
さらに、Aさんが話した相手はAさん・Vさんと同じ会社に勤務する人たちですから、噂話として不特定又は多数人に伝播する可能性は十分に考えられるため、Aさんに名誉毀損罪が成立する可能性はあるということになります。
似たような事例で、近所の人を含む計7人に「あの人は放火犯だ」と話した結果、その伝播可能性から名誉毀損罪が認められた判例も存在します(最判昭和34.5.7)。
ここで注意しなければいけないのは、「話した相手が7人だから名誉毀損罪」「話した相手が2人だから名誉毀損罪にならない」といったことではないということです。
話した人数によって名誉毀損罪の成否が左右されるのではなく、あくまで伝播可能性の有無などの詳しい状況を含めて判断しなければなりません。
名誉毀損罪に当たるか否かの判断は難しいケースが多く、事件の態様も多岐にわたりますから、名誉毀損事件の当事者になってしまったら、弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名誉毀損事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
噂話から名誉毀損事件に発展してしまった、名誉毀損事件への対応に困っているという方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご近所トラブルから暴力行為処罰法違反に
ご近所トラブルから暴力行為処罰法違反に
ご近所トラブルから暴力行為処罰法違反に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
神奈川県逗子市に住んでいるAさんは、マンションの隣室に住んでいるVさんの騒音に悩まされていました。
Aさんは、度々Vさんに騒音を注意するなどしていましたが、Vさんの騒音が収まる気配はなく、Vさんと顔を合わせては小競り合いのような形になっていました。
ある日、どうしてもVさんの騒音に耐えきれなくなったAさんは、自宅にあった包丁を手にVさん宅へ向かい、玄関先でVさんに向かって「うるさいぞ。いい加減にしないと殺してやるぞ」などと言いました。
驚いたVさんが神奈川県逗子警察署に通報したことにより警察官が駆けつけ、Aさんは銃刀法違反と暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、どうにかAさんの力になれないかと神奈川県の刑事事件の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴力行為処罰法違反
今回のAさんの逮捕容疑は、銃刀法違反と暴力行為処罰法違反です。
包丁を持ち出していることから、銃刀法違反については成立することも納得するという方が多いかもしれませんが、暴力行為処罰法違反についてはわかりづらいという方もいらっしゃるかもしれません。
暴力行為処罰法とは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、集団での犯罪行為や凶器を用いての犯罪行為など、刑法に定められている犯罪をより重く処罰する場合について規定している法律です。
元々はストライキなどに対応するために定められた法律ですが、現在では暴力団による犯罪行為や学生運動の取り締まり、いじめ行為などにも適用されています。
この暴力行為処罰法には、以下のような条文があります。
暴力行為処罰法第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
つまり、刑法第208条の暴行罪、刑法第222条の脅迫罪、刑法第261条の器物損壊罪について、集団でその罪を犯したり凶器を示してその罪を犯した場合、この暴力行為書罰法違反によって処罰されるということになります。
例えば、今回のAさんはVさんに包丁という凶器を示して「殺すぞ」と脅している=脅迫罪に当たる行為をしています。
この場合、Aさんには脅迫罪ではなく暴力行為処罰法違反という犯罪が成立するということになるのです。
暴力行為処罰法は、刑法よりも重く処罰するように刑罰が設定されています。
実際に、今回のAさんの事例で比較してみると、脅迫罪の刑罰が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と設定されているのに対し、暴力行為処罰法違反となった場合は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と刑罰の上限が引き上げられて=重くなっています。
・ご近所トラブルから刑事事件へ
今回の事例のAさんのように、騒音などによるご近所トラブルはそう珍しくありません。
ご近所トラブルというと、単にご近所同士の小競り合い、大したことはないと考えられる方もいらっしゃいますが、今回の事例のようにご近所トラブルによる対立・嫌がらせがエスカレートした結果刑事事件となってしまうこともあります。
そして、ご近所トラブルから刑事事件となった場合、当事者だけで被害者対応をすることが困難である場合が多いです。
というのも、そもそもご近所トラブルによって被疑者やその周辺の人たちと被害者の関係性が悪化していたところに刑事事件が起こってしまったというケースが多く、被害者の被害感情や処罰感情が大きい場合が多いためです。
また、ご近所トラブルの延長で刑事事件が起こっているケースでは、加害者である被疑者がすぐ近くに住んでいるという状況から、被害者側の恐怖が大きいことも考えられます。
こうした事情から、直接当事者が被害者への謝罪や弁償をしようと思っても断られてしまったり、そもそも連絡をすること自体ができなかったりということが考えられるのです。
だからこそ、ご近所トラブルに関連した刑事事件では、弁護士を挟んで被害者対応をすることをおすすめいたします。
弁護士という第三者かつ専門家が間に入ることで、被害者としても被疑者と直接やり取りをせずに済むというメリットが出て来るため、連絡の許可をもらえる可能性があるのです。
そのため、早い段階で弁護士に相談・依頼することが望ましいと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご近所トラブルから派生した刑事事件や暴力行為処罰法違反事件にも、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
東京都府中市に住むAさんは、傷害致死事件を起こして警視庁府中警察署に逮捕されました。
そのまま捜査を受けていたAさんですが、どうやら傷害致死罪で起訴されそうだということを耳にしました。
Aさんの家族は、傷害致死事件は起訴されれば裁判員裁判になるという話を聞き、「裁判員裁判は特殊だと聞いたがどういった部分が特殊なのか。Aさんはどうなるのか」と心配に思い、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
弁護士への相談によって、Aさんの家族は、裁判員裁判には公判前整理手続という手続きがあることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・裁判員裁判と公判前整理手続
死刑又は無期の懲役・禁錮が刑罰に含まれている犯罪(裁判員法第2条第1項第1号)、又は裁判を合議体で行う犯罪であって、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた犯罪(裁判員法第2条第1項第2号)は裁判員裁判の対象となります。
今回のAさんが問われることになる傷害致死罪の刑罰は「3年以上の有期懲役」(刑法第205条)とされているため、死刑や無期の懲役・禁錮は刑罰に含まれていません。
しかし、傷害致死罪は傷害罪に当たる犯罪行為=傷害行為によって被害者を死なせてしまう犯罪ですから、先ほど挙げた後者の条件(裁判員法第2条第1項第2号)に当てはまり、裁判員裁判対象事件となるのです。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、被告人の有罪・無罪や刑罰の重さを決定します。
そのため、裁判員裁判では裁判員の負担を軽減するため、通常の刑事裁判とは違う手続きや日程が取られます。
その1つが、公判前整理手続という手続きが必ず取られるという点です。
公判前整理手続とは、裁判(公判)の前に予定されている主張や証拠を整理して争点を絞り込んでおく手続きのことを指します。
公判前整理手続は、裁判員裁判の導入を見据えて2005年に刑事訴訟法の改正によって導入された手続きです。
裁判員裁判では、先ほど触れたように法律や刑事裁判の専門家ではない裁判員が参加します。
ですから、公判前整理手続によって裁判員が裁判に参加する前に争点を絞り込んでおくことで、専門知識のない裁判員にとっても裁判で何が争われているのか分かりやすくする必要があるのです。
裁判員法第49条
裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
なお、この公判前整理手続は、通常の刑事裁判であれば「することができる」手続きであり、必ずしもしなくてよいものです。
刑事訴訟法第316条の2第1項
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
裁判員裁判以外の刑事裁判で公判前整理手続が取られる例としては、証拠や共犯者の多い刑事事件や、被告人が容疑を否認しているいわゆる否認事件などが多いです。
・公判前整理手続も重要
公判前整理手続は、あくまで裁判の前の準備段階といえます。
被告人は公判前整理手続に参加しなくてもよいとされていますし、裁判員も公判前整理手続には参加しません。
また、公判前整理手続は裁判(公判)とは異なり、非公開でもよいとされており、多くの場合が非公開で行われます。
こうしたことから、「裁判本番ではないのだから気にしなくてもよいのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公判前整理手続後には基本的には新しい証拠を出すことができない等、公判前整理手続を蔑ろにしてしまうと、その後の裁判で十分に被告人の主張を主張し切れないということが起こりかねません。
裁判本番でないからと軽く考えず、公判前整理手続の段階から主張や証拠をよく検討・準備しておかなければならないのです。
だからこそ、裁判員裁判では刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、各種手続きに柔軟かつ迅速に対応してもらうことが必要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判対象事件のご依頼も受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、裁判員裁判の複雑な手続きの中でもご依頼者様の不安・負担の軽減のために弁護士がフルサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。