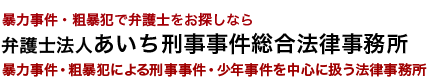未分類
名誉棄損罪と告訴取消し
名誉棄損罪と告訴取消し
名誉棄損罪と告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市北区に住むAさんは長年交際していたVさんから突然の分かれを告げられたため、報復するつもりでSNSの掲示板にVさんに対する誹謗中傷する事実を掲載したところ、大阪府曽根崎警察署に名誉棄損罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は名誉棄損に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~名誉棄損罪~
近年は、ツイッター、インスタグラムやフェイスブックなどのSNSで誰でも簡単に、しかも匿名でも書き込みできる時代です。
ですから、自分の投稿が名誉棄損罪にあたり警察沙汰になるなど思わぬ事態に発展する可能性も考えられます。
そこで今回は名誉棄損罪について詳しく見ていきましょう。
名誉棄損とは、文字通り、他人の名誉を傷つけることをいいます。名誉棄損を行うと刑事上の責任と民事上の責任に問われる可能性があります。
刑事上の名誉棄損罪については刑法230条に規定されています。
刑法230条
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘時することによってした場合でなければ、罰しない。
「名誉」とは、人に対する社会的な評価などをいうと解されています。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態と解されています。
「事実を摘示する」とは、人に対する社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示することをいいます。
似たような犯罪としては侮辱罪があります。
刑法231条
事実を摘示なくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪と侮辱罪との違いは「事実を摘示」したかどうかです。
単なる意見や暴言にすぎないときは侮辱罪に問われます。
~告訴を防ぐ~
告訴とは、告訴権を有する者(被害者等)が、捜査機関(警察等)に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を言います。
犯罪の中にはこの告訴がなければ起訴できない犯罪があります。
これを親告罪と言います。
刑法で定められている例を挙げれば、名誉棄損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、過失傷害罪(刑法209条)、器物損壊罪(刑法261条)などがあります。
刑法以外の法律でも親告罪とされている犯罪がありますから、ご自身が行った犯罪が告訴が必要な親告罪か否かは弁護士に確認するとよいでしょう。
親告罪では、ご自身が罪を認めているのならば、被害者と話し合いや示談をすることが賢明でしょう。
示談が成立すれば、そもそも被害者が捜査機関に告訴状を提出しないということもありえるでしょう。
また、すでに提出していたとしても告訴を取下げてもらえるかもしれません。
そうすれば有罪となって刑罰を受けたり前科が付く可能性がなくなります。
ただし、示談を何と言ってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書はいくらにしたらよいかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
逮捕時に令状なしで押収
逮捕時に令状なしで押収
今回は、逮捕時の令状なしの押収・差押えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県船橋市に住むAさんは、護身用と称して特殊警棒をカバンに隠して携帯していたところ、千葉県船橋警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは警察官らの質問に対する回答を拒んだ挙句、「違法な職務質問を行う警察官に対して加害行為を行っても、正当防衛が成立する」などと叫び、特殊警棒で警察官を殴打しました。
殴られた警察官は頭蓋骨を骨折し、入院したことが後にわかりました。
応援にやってきていた警察官5名でAさんを制圧し、公務執行妨害および傷害の疑いで現行犯逮捕しました。
特殊警棒はその際に警察官によって押収されました。
Aさんは「逮捕されたとはいえ、令状なしで警棒を押収したのは、警察権力の横暴である」と考えています。
警棒の押収手続の適法性について、Aさんは弁護士に尋ねてみようと考えています。(フィクションです)
~公務執行妨害および傷害罪について解説~
【公務執行妨害罪】
この犯罪は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪です(刑法第95条1項)。
公務執行妨害罪の客体は「公務員」です。
よくニュースで見聞きするのは、警察官を殴打するなどして検挙される場合ですが、当然ながら、職務中の市役所職員などに暴行・脅迫をした場合であっても、公務執行妨害罪が成立します。
「暴行」は、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りるとされていますが、公務員の身体に対して直接なされる必要はなく、間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響を与えるようなものでも構いません。
判例で有罪になったものとしては、
・税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為(最高裁昭和33年10月14日判決)
・逮捕現場で警察官が押収した覚せい剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為(最高裁昭和34年8月27日決定)
などがあります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となっています。
【傷害罪】
文字通り、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
警察官に生じさせた頭蓋骨骨折は、明らかに「傷害」に該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
上記に加え、軽犯罪法違反にも問われる可能性も十分あります。
~特殊警棒の押収手続は適法か?~
本来、捜査機関が証拠品等を押収するためには、裁判所の許可が必要です(令状が必要という言い方もします)。
しかし、刑事訴訟法220条に例外規定があります。
刑事訴訟法
第220条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
2項 省略
3項 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
4項 省略
Aさんは、司法警察職員たる警察官により、現行犯逮捕されています。
このような場合において必要があるときは、刑事訴訟法第220条1項2号により、「逮捕の現場で差押」をすることができ、同条3項により令状は不要です。
したがって、Aさんが特殊警棒で警察官を殴打し、傷害を負わせるなどして現行犯逮捕された場合においては、令状なしで凶器の特殊警棒を押収しても、適法ということになります。
~まずは弁護士を呼ぶ~
Aさんは警察官に比較的重い傷害を負わせており、重い処分がなされることが十分見込まれます。
一刻も早く弁護士を呼び、善後策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公務執行妨害・傷害事件などを起こし逮捕されてしまった方は、ぜひご相談ください。
会社の同僚に嫌がらせをして取調べ
会社の同僚に嫌がらせをして取調べ
今回は、会社の同僚に対し嫌がらせをした場合に成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
埼玉県草加市に住むAさんは、会社の同僚Vさんとの関係が悪化しており、電子メールで「会ってこれまでのことにケリをつけようや」などと執拗に迫ったり、Vさん宅に大小便や動物の死骸などを送りつけるなど、悪質な嫌がらせを繰り返していました。
腹に据えかねたVさんは警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に埼玉県草加警察署から連絡があり、「空いている日に出頭して聞かせてほしいことがある」とのことです。
正直、Aさんとしては出頭したくありません。
どうするべきでしょうか。(フィクションです)
~成立しうる犯罪は?~
今回のAさんのようなことをすると、埼玉県迷惑行為等防止条例違反となる可能性が高いと思われます。
関係する条文を抜粋して紹介します。
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの…を反復してしてはならない。
3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
まずAさんの行為は、同僚との関係が悪化した原因が何であれ、真っ当な方法を用いているとは言えませんから、「正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為」に当たる可能性が高いでしょう。
また、電子メールを使い、「会ってこれまでのことにケリをつけようや」などと迫る行為は、3号に該当すると思われます。
また、「V宅に大小便や動物の死骸などを送りつける」行為は、6号に該当すると思われます。
したがって埼玉県迷惑行為等防止条例違反となる可能性が高いわけです。
上記行為に対する法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております(12条1項)。
常習性が認められる場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(12条3項)。
~Aさんはどうするべきか?~
Aさんは出頭したくないとのことです。
しかし警察の出頭要請に応じない場合、Aさんに「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断されてしまい、逮捕されてしまう可能性を高めてしまうことになるでしょう。
また、犯罪の内容にもよりますが、一般的に、被害者と加害者が鉢合わせをする可能性が低ければ、逮捕しなくてもいいという判断になる可能性も上がることがあります。
なぜなら、被害者を脅して供述を変えさせるなど、証拠隠滅の一種とされる行為をする可能性が低いと判断される傾向にあるからです。
しかし今回は会社の同僚同士であり、毎日顔を合わせる可能性があるので、逮捕されるリスクが高まる事情の1つが元々あるといえます。
したがって、少しでも逮捕の可能性を下げるために出頭には応じた方が賢明といえます。
~まずは弁護士と相談~
まだAさんは逮捕されていないので、いつでもAさんは弁護士と相談することができます。
できれば出頭前に弁護士と会い、取調べの対応方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
また、Vさんと示談をすることにより、不起訴処分などの軽い処分を目指す必要もあります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動
今回は、器物損壊事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
神奈川県横浜市に住むAさんは、会社の同僚女性Vのバッグに体液をかけるなどしていました。
Vはこれに気付き、上司と警察に相談しました。
Vは警察に告訴状を提出し、神奈川県磯子警察署は器物損壊被疑事件として捜査を開始しました。
社内の監視カメラにより、Aさんの犯行であることが判明すると、警察はAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
会社をクビになるのは仕方ないとしても、前科を付けることを避けたいAさんはどうするべきでしょうか。(フィクションです)
~器物損壊事件とは?~
器物損壊罪とは、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊する犯罪です(刑法261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、それぞれ別の犯罪が成立します。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
物を物理的に壊す行為はもちろん含まれますが、事実上使えなくすることも、物の効用を害する行為として「損壊」に該当する可能性があります。
たとえば、裁判でも、食器に放尿する行為(大審院明治42年4月16日判決)などが「損壊」に該当するとされています。
Vのバッグに体液をかけた行為についても、「損壊」と判断される可能性が高いでしょう。
~今回の弁護活動~
一般的な器物損壊事件など比較的軽い犯罪では、逮捕されずに捜査が進められ、自宅から警察署等に出向いて取調べを受けるといったケースも多いです(在宅事件といいます)。
しかし今回のケースの場合は、器物損壊事件の中でも、自身の性的な満足を得るためになされた犯行と考えられます。
このような事件の場合、被疑者が被害者になお接触を試みたりするおそれが高いと判断され、逮捕されることも多く、また身体拘束の期間も長くなることが考えられます。
身体拘束が長引くと、Aさんにも負担がかかるので、なるべく早期の釈放を目指す必要があります。
今回のケースでは逮捕された直後なので、弁護士に、勾留がつかないよう活動してもらう必要があります。
勾留とは、逮捕後に最大3日間身体拘束されて取調べ等を受けた後、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に引き続きなされる身体拘束のことを言います。
弁護士としては例えば、Aさんがすでに会社をクビになっていれば、釈放したとしても、再び会社に出勤する必要がないので、Vと会う可能性はなく、被害者を脅して供述を変えさせるなどの証拠隠滅の一種の行為をする可能性は低いと主張することが考えられます。
また、AさんとVの居住地が離れていれば離れているほど、やはり証拠隠滅のおそれが低いと判断される可能性が高まり有利です。
さらに、Aさんの行動を監督できる身元引受人を用意できれば、勾留が付かずに済む可能性がより高まります。
この勾留は、検察官による勾留請求があり、これに対して裁判官が勾留決定をした場合になされます。
弁護士は、検察官や裁判官に対し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけていくことになります。
勾留されてしまった後は、勾留決定に対する不服申し立て制度を用い、釈放を求めて活動することが考えられます。
~示談して告訴状を取り下げてもらう~
器物損壊事件は、告訴がなければ絶対に刑事裁判にかけられません(親告罪)。
ということは、誠心誠意、Vへの謝罪と賠償を尽くして示談を結び、告訴を取り下げてもらうことがとても重要です。
Aさんは逮捕されているので、外で活動することができません。
したがって、Aさんが依頼した弁護士に、外でVと接触してもらい、示談交渉を行うことになります。
Vと示談が成立すれば、釈放される可能性も高まります。
弁護士からアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
強盗事件を起こし緊急逮捕
強盗事件を起こし緊急逮捕
今回は、刑事手続としての逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都小金井市にあるコンビニエンスストアで、刃物を示す等して店員を脅迫し、現金15万円を奪って逃走しました。
警視庁小金井警察署は直ちに捜査を開始し、犯行時刻から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所においてAさんを発見したので、職務質問をしました。
Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子でしたが、説得を重ね、車内を点検することができました。
その結果、車内から現金15万円、及び犯行に使われた刃物や覆面マスクが発見されました。
Aさんは強盗の疑いで緊急逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕される際「令状がないのになんで逮捕できるんだ」と不満を募らせました。
接見にやってきた弁護士に、逮捕手続は適法であったのか尋ねてみようと考えています(フィクションです)。
~「逮捕」とは何か?~
「逮捕」とは犯罪をしたと疑われている被疑者の身柄を拘束する強制処分です。
「逮捕」するには原則として裁判所が発行する令状(逮捕状)が必要です。
「逮捕」には以下の3種類があります。
・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕
以下、1つずつ解説いたします。
【通常逮捕】
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①逮捕の理由、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。
※ ①逮捕の理由について
ある人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることをいいます。
※ ②逮捕の必要性について
正確には、「明らかに逮捕の必要がない」とき、逮捕の要件を満たさないことになります。
したがって、逮捕の必要性が「不明」の場合は、実務上、令状発付が可能とされています。
【緊急逮捕】
①死刑または無期もしくは上限(長期)が3年以上の懲役・禁錮にあたる罪であり、②その人がこの犯罪をしたことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。
今回のケースでは緊急逮捕がなされているので、①②③の条件を満たすのか検討してみます。
まず、強盗罪の刑罰の上限(長期)は20年の懲役ですから、3年以上という①の条件をみたします。
また、手配された犯人の容貌とAさんの容貌が類似していること、Aさんの車内から強取された現金と同じ金額の現金、犯行に用いられた刃物、覆面マスクが発見されたことから、②も満たしているでしょう。
そして、Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子だったので、③も満たしているでしょう。
したがって、緊急逮捕の条件を満たしている可能性が高いと思われます。
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」逮捕状を請求しなければなりません。
逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
【現行犯逮捕】
現に罪を行い、あるいはまさに今行い終わった者を現行犯人といいますが、この現行犯人は、誰でも、逮捕状なく逮捕することができます。
誰でも逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。
民間人による現行犯逮捕がなされたと扱われるケースはしばしば見受けられます。
緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、犯罪をしたことがが明白な場合なので、裁判官による逮捕の適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないため、逮捕状は不要とされているのです。
また、犯罪をまさに今行い終わった者とまでは言えなくても、犯人として追いかけられているといったの場合であり、罪を行い終わってそれほど間がないと明らかに認められる場合も、「準現行犯」として、現行犯人とみなされることになります。
~今後の弁護活動~
Aさんが逮捕の手続の適法性について弁護士に尋ねたとしたら、概ね上記の様な説明をされるでしょう。
もちろん、緊急逮捕の条件を満たしていないのに逮捕されてしまったのであれば、即、釈放するよう求めて活動しなければなりません。
場合によっては、逮捕後に捜査機関が取得した証拠(たとえば取調べの記録である供述調書など)の証拠能力を否定できる場合もあります。
証拠能力が否定されると、その証拠は刑事裁判において事実の認定に使うことができなくなります。
たとえば、犯罪を自白している供述調書が裁判で使えなくなると、裁判にかけられている人に有利になります。
弁護士はこのような弁護活動をしていくこともできますので、一刻も早く、弁護士を相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強盗事件などを起こして逮捕されてしまった方は、ぜひ初回接見サービスをご依頼ください。
公務執行妨害事件・逮捕されたらどうなる?
公務執行妨害事件・逮捕されたらどうなる?
公務執行妨害罪で逮捕されたらどうなるのか,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
東京都港区内の居酒屋で飲食し酔っ払ったAは,過去に警察官に冷たい対応されたことから恨みを持っており,停車していた警ら中のパトカーを蹴るなどの行為をした。
警視庁赤坂警察署の警察官は,Aを公務執行妨害罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は,暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~公務執行妨害罪における「暴行」とは~
刑法95条1項は,「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」を公務執行妨害罪として処罰する旨を定めています。
Aはこの公務執行妨害の容疑で逮捕されているわけです。
もっとも,Aはパトカーを蹴ってはいるものの,「公務員」である警察官自身には直接の危害は加えていません。
このような場合でも,公務執行妨害罪が成立してしまうのでしょうか。
問題となるのは,公務執行妨害罪における「暴行」の意義です。
「暴行」と聞いて一般的に想起するのは,特定人に対する殴る蹴るなどの暴力でしょう。
実際,このような行為は刑法208条における暴行罪にいう「暴行」として処罰されうる行為です。
しかし,刑法95条1項とは,個人たる「公務員」を保護する規定ではなく,広く公務という国家作用を保護するための規定と解されています。
したがって,ここにいう「暴行」とは,公務に影響を与えるようなものが広く含まれることになり、「公務員」の補助者や物に対してなされた物であっても、間接的に「公務員」に物理的・心理的影響を与えるような行為も該当すると考えられています。
そうすると、Aのようにパトカーを蹴った場合でも、その場にいる「公務員」である警察官は対応を余儀なくされますし、恐怖心も感じるでしょうから、物理的・心理的影響を受けているといえます。
したがって公務執行妨害罪における「暴行」に該当することになる可能性が高いといえます。
なお,Aがパトカーを蹴った行為には,器物損壊罪(刑法261条)も成立しうることにも注意が必要です。
~逮捕されたらどうなる?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判が行われることになります。
この逮捕・勾留の期間,逮捕された被疑者(容疑者)は,警察署に備え付けられた留置場に入れられることになります。
留置場では,警察署にもよりますが、通常は見知らぬ被疑者(容疑者)と過ごすことになります。
勾留まで含めると、刑事裁判が始まるまでの期間だけでも最大23日間の身体拘束が待っていることになります。
検察官の勾留請求に対し、裁判官が勾留を却下する確率は約5%(2018年)です。
近年微増しているものの,未だに逮捕され勾留請求されれば,勾留されるのが原則という状況に大きな変化はないと言わざるを得ません。
したがって,逮捕直後から弁護士を付けることによって,勾留を阻止するための活動を行うことが重要になってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害などの暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
公務執行妨害事件などで逮捕された方のご家族等は,いますぐ弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
保護責任者遺棄致死罪で逮捕・弁護士の役割
保護責任者遺棄致死罪で逮捕・弁護士の役割
保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまった事例における,弁護士の役割などについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
福岡県宗像市に住むAは,実の子であるV(3歳)が言うことを聞かないことにいら立ち,Vを真冬のベランダに放り出した。
数十分後,AがVの様子を見ると全く動かなくなっており,慌てて119番通報するも,のちに病院でVの死亡が確認された。
福岡県宗像警察署の警察官は,Aを保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕した。
Aの家族は,刑事事件に強いと言われる弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)
~保護責任者遺棄致死罪とは~
Aは,我が子であるVが言うことをきかないという理由で,真冬のベランダに放置してVを死亡させてしまっています。
刑法218条は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定しています。
さらに,刑法219条は「前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者」を保護責任者遺棄致死(致傷)罪とすることを定めています。
この罪は、死亡させるつもりがなかったとしても成立します。
もし死亡させるつもりがあったり、死亡するかもしれないと思っていた場合、つまり殺人の故意がある場合には、殺人罪が成立する可能性があります。
もっとも,ちょっとベランダに出したくらいで死亡や負傷はしないと考えていたなど、危険な状態に置くことの認識すらなかった場合には,より軽い過失致傷罪(刑法210条)や重過失致死罪(211条後段)にとどまる可能性もあります。
したがって,死亡させるつもりだったか、危険な状態に置く認識があったかなどの故意の有無が、保護責任者遺棄致死罪の成立にとって一つの争点となりうるものと考えられます。
なお,殺人罪や保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象事件となります。
~人質司法の問題点・弁護士の役割~
日産のゴーン元会長の国外逃亡などを受け,現在わが国でも改めて「人質司法」の問題について議論を呼んでいます。
人質司法とは,取調べにかたよった捜査と逮捕・勾留による身体拘束期間の長期化という,わが国の刑事司法・捜査実務の問題を表した言葉です。
戦前において(治安維持法などの下に置いて)被疑者や被告人に対して,厳しい取調べなどが行われていました。
しかし戦後も、諸外国に比べると被疑者・被告人の権利が弱いままであるのが実情です。
弁護士が従うべきものとして、弁護士会が自ら定めている弁護士職務基本規程は,47条において「弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める」ものとし,また48条では「弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、必要な対抗措置をとるように努める」ことを定めています。
これらの規定は,まさに人質司法によって被疑者・被告人が被る不利益を,弁護士ができるだけ軽減しその改善に向けて努力していくことを刑事弁護士の倫理・役割として定めたものといえます。
弁護士はこの役割を全うし、被疑者・被告人の権利を守るすべく活動しておりますので、あなたやご家族が犯罪をした、あるいはしたと疑われている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,保護責任者遺棄致死を含む刑事事件専門の法律事務所です。
保護責任者遺棄致死事件などで逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル
0120-631-881
まで、お電話お待ちしております。
刃物を携帯し銃刀法違反
刃物を携帯し銃刀法違反
今回は、刃体の長さが10センチメートルのサバイバルナイフを携帯した場合に成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都府宇治市に住むAさんは、護身用と称して、刃体の長さが10センチメートルのサバイバルナイフをカバンに入れて外を歩いていたところ、京都府宇治警察署の警察官から声をかけられ、所持品検査を受けました。
Aさんは、護身用だから堂々を携帯してもよいと考えていたので、快く所持品検査に応じましたが、上記サバイバルナイフが発見されてしまったので、警察署へ任意同行を求められました。
警察官は「護身用である、というのは、『正当な理由』にならないぞ」と告げ、Aさんは在宅で捜査を受けることになってしまいました。
Aさんは今後どうなってしまうのか不安に感じています。(フィクションです)
~成立しうる犯罪~
銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法は、第22条において、
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
と規定しています。
これに違反すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(第31条の18第3号)。
「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のものをいいます。
文化包丁、出刃包丁、刺身包丁などは「刃物」に該当しますし、サバイバルナイフも「刃体の長さ」などの要件を満たす限り、銃刀法で携帯が禁止される「刃物」になります。
「携帯」とは、自宅以外の場所で、所持者自身が手に持つか、又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で、ある程度継続して、これを直ちに使用しうる状態で身辺に置く場合をいいます。
裁判例では、斧を紙で包んで自己が運転する自動車の運転席足元に置いて運搬した行為(東京高等裁判所昭和58年9月19日判決)などの行為が、「携帯」に該当するとされています。
これによれば、カバンにサバイバルナイフを入れていたAさんの行為は「携帯」に該当する可能性が高いと思われます。
また、護身用として持ち歩いたという点は、「業務その他正当な理由による場合」に通常は該当しません。
したがって、Aさんの行為は銃砲刀剣類所持等取締法違反となる可能性が高いと思われます。
~今後の弁護活動~
【逮捕されるか?】
Aさんが帰宅を許され、素直に警察の出頭要請に応じているのであれば、今後逮捕されてしまう可能性は低いでしょう。
ただし、家を捜索されるなどして、余罪が発覚してしまった場合はこの限りではありません。
この場合も、逮捕されないように適切な弁護活動を行うことにより、逮捕されてしまう可能性を低減させることができます。
【処分の見込み】
Aさんの行為が銃刀法違反となる可能性は高いですが、Aさんは誰かを直接傷つけるなどの行為をしたわけではありません。
したがって、起訴され、有罪判決を受けてしまう場合であっても、初犯であれば、懲役刑を言い渡される可能性は低いでしょう。
【不起訴処分を目指す】
検察官は、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を判断します。
不起訴処分は、犯罪をした証拠が不十分(嫌疑不十分)の場合のほか、犯罪をしたことは確実でも比較的軽い罪の場合には、今回は大目に見るということでなされることもあります(起訴猶予)。
弁護士としても検察官に対し、初犯であること、被害者がいないこと、反省していること、他の刃物を処分したことなどを主張して、不起訴処分を行うように働きかけることが考えられます。
~ご相談ください~
銃砲刀剣類所持等取締法違反の嫌疑をかけられてしまった場合、まずは弁護士に相談し、善後策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談のほか、万が一、逮捕されている事件では初回接見サービスをご利用いただけます。
お早めのご連絡をお待ちしております。
恐喝罪で逮捕【強盗罪との違い】
恐喝罪で逮捕【強盗罪との違い】
恐喝罪で逮捕されてしまった事件に関し,詐欺罪や強盗罪との違いなどについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
Aは,大阪府松原市にある雑貨店に訪れた際、店員Vに因縁をつけ,「客に対する対応が悪い」「お前は俺を怒らせてしまった」「詫びの品を用意しなければどんなひどい目にあってもしらんぞ」などと告げた。
Aの威勢に恐怖を覚えたVは,店内にあった品物(数万円相当)をAに対して交付した。
後日、被害届の提出を受けた大阪府松原警察署の警察官は,Aを恐喝罪の疑いで逮捕した。
なお,逮捕されたAは,おおむね上記の犯行事実を認めている。
Aの家族は,暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです)。
~恐喝罪と強盗罪の共通点と相違点~
刑法249条1項は,「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
この恐喝罪は,上記条文からは必ずしも明確ではありませんが,一般に「恐喝行為→畏怖(恐怖を感じる)→被害者の財物交付行為→加害者の受領行為」という因果経過を予定している犯罪です。
このうち「恐喝行為」とは,財物を交付させる手段としての暴行・脅迫のことをいうと解されています。
したがって,暴行・脅迫を手段とする財産犯であるといえ,この点において強盗罪(刑法236条)と共通点を有しているのです。
もっとも,強盗罪と恐喝罪における暴行・脅迫は,恐喝罪の方が軽度のもので足りるとされています。
すなわち、強盗罪の成立には相手方(被害者)が反抗不可能になるような強い程度の暴行・脅迫が必要です。
たとえば、ナイフを突き付けられるような場合が典型的です。
一方、恐喝罪の成立には、相手方が反抗出来なくもないけど畏怖する(怖がる)程度の暴行・脅迫があれば足りると解されています。
ここで本事例についてみてみるに,Aは「どんなひどい目にあってもしらない」などと害悪を告知することによって一般人が畏怖するに足りる脅迫行為をおこなっており,「恐喝」に当たる行為があったといえるでしょう。
そして,これに基づいて店員Vさんが店の品物という「財物を交付」し,Aさんが「受領」しているので、恐喝罪(刑法249条1項)が成立する可能性が高いといえます。
~恐喝事件における弁護士の弁護活動~
本件のように,逮捕されたAが犯行を認めている場合,弁護士としてはどのような弁護活動として、まずは被害弁償を行うことが重要となります。
被害者との間で示談まで成立させることができれば,被疑者にとっては有利な情状事実となることは間違いありません。
特に逮捕されて身柄拘束が続いている事件では,一気に手続が進んでいきます。
したがって弁護士としては,一刻も早くVさんとの示談を成立させることで,Aを不起訴とするための弁護活動を行うことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。
特殊警棒の携帯で軽犯罪法違反
特殊警棒の携帯で軽犯罪法違反
今回は、特殊警棒を携帯していた場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府池田市在住のAさんは、護身用と称して、カバンの中に特殊警棒を入れて外を歩くなどしていました。
ある日、大阪府池田警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査を求められたので、カバンを開けてみせると、特殊警棒が発見されてしまいました。
警察官はAさんに、
「特殊警棒の携帯は軽犯罪法違反になるから、警察署で話を聞かせて欲しい」と告げました。
Aさんは罪に問われていることに不服です。
特殊警棒の携帯は罪になるのでしょうか。
(フィクションです)
~軽犯罪法違反の可能性がある~
軽犯罪法第1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯」することを禁じています。
特殊警棒もこれに該当する可能性があります。
ただし、携帯することに「正当な理由」があれば犯罪とはなりません。
「正当な理由」とは、第2号所定の器具を隠して携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいいます。
この定義だけでは意味が少しわかりづらいので、裁判所の判例も見てみましょう。
最高裁平成21年3月26日判決は、
『「正当な理由」があるというのは、本号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解される』
と判示しています。
結局は総合判断ということですので明確な線引きがあるわけではありませんが、上記のような諸事情をしっかり考慮した上で、判断するということになります。
この判例は、有価証券や多額の現金をアタッシュケースに入れて運搬する仕事をしていた被告人が、サイクリング中に催涙スプレーをズボン左前ポケットに携帯していた事件です。
最高裁判所は結論として、
『職務上の必要から、専門メーカーによって護身用に製造された比較的小型の催涙スプレー1本を入手した被告人が、健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し、専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて隠匿携帯したなどの事実関係の下では、同隠匿携帯は、社会通念上、相当な行為であり、上記「正当な理由」によるものであったというべきである』
として、「正当な理由」があると認められました。
この判例に従えば、今回のAさんの場合も、職業、特殊警棒の使用目的等によっては、特殊警棒を携帯していたことに「正当な理由」が認められる可能性があります。
そのため、まずは弁護士と相談し、「正当な理由」の有無について助言を受け、今後の弁護活動の方針を立てて行きましょう。
~より有利な事件解決を目指して行動する~
逮捕されずに、在宅事件として刑事手続が進行する場合は、警察の要請に応じて警察署に出頭し、取調べを受けることになります。
警察での捜査が終わると、検察へ事件が送致されます。
検察においても、検察官の取調べを受けることになります。
最終的に、検察官によりAさんが起訴されるか、あるいは不起訴になるかが決められます。
上記のように、「正当な理由」があると認められる場合には、犯罪の嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分として、不起訴処分となることも考えられます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
特殊警棒を携帯してしまい、軽犯罪法違反の疑いをかけられたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
軽犯罪法違反などの嫌疑をかけられてしまった方は、ぜひ無料法律相談をご利用ください。