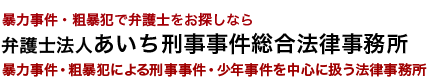未分類
傷害事件で幇助犯に問われたら
傷害事件で幇助犯に問われたら
傷害事件で幇助犯に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、福岡市博多区に住んでい女性会社員で、Bさんという恋人がいます。
ある日、AさんはBさんから「Vというやつが気にくわないからヤキを入れてやろうと思っている」「Vは一度痛い目に合わないといけない」などと、Vさんに暴行を加えるつもりであることを打ち明けられました。
そこでAさんはBさんに対し、メッセージアプリで「やるんなら思いっきり痛い目を見せてやらないと」「男ならやらなきゃいけない時がある」「やってやれやってやれ」等とAさんを後押しするメッセージを送りました。
その後、BさんはVさんに対する傷害事件を起こして福岡県博多警察署に逮捕されたのですが、Aさんも傷害罪の幇助を行ったとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、どうして傷害事件に直接かかわっていない自分も逮捕されてしまったのか詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・直接かかわらなくても幇助犯に?
ご存知の方も多いように、人に暴力をふるって怪我をさせれば傷害罪となります。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回の事例の傷害事件では、Aさんの恋人のBさんが被害者Vさんに怪我をさせたものであって、Aさん自身はVさんに暴力をふるって怪我をさせたわけではありません。
傷害罪の条文を見ると「人の身体を傷害した者」が傷害罪に問われるわけですから、Aさんが今回の傷害事件に関して罪に問われることは不自然に思えるかもしれません。
しかし、今回のAさんが逮捕されているのは傷害罪の「幇助犯(ほう助犯)」としての容疑をかけられているためです。
幇助犯とは、「正犯を幇助(ほう助)した者」、つまり、簡単に言えば犯罪を実行しやすくするために手助けをした人を言います。
幇助犯については、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第62条第1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
つまり、幇助犯となった場合、正犯の刑=犯罪をした人に科される可能性のある刑罰よりも軽い範囲で刑罰を科されることになるということになります。
例えば今回の事例にある傷害罪の場合、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円の罰金」ですから、これが「正犯の刑」となります。
ですから、傷害罪の幇助犯となった場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」よりも軽い範囲で刑罰が決められるということになります。
刑の減軽については、刑法の以下の条文に規定があります。
刑法第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
第3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
第4号 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
すなわち、傷害罪の幇助犯となった場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」という範囲で刑罰が決められることになるのです。
では、そもそも幇助犯とは具体的にどのようなことをした場合に成立するのでしょうか。
犯罪行為を容易にするというと、例えば殺人行為をしようという人に凶器を渡すような物理的に犯行を手助けするケースが思い浮かびやすいかもしれません。
たしかに、凶器など犯行に使用するものを準備したり提供したり、犯行のための資金を準備・提供したりすることは幇助犯として問われうる行為です。
しかし、今回の事例のAさんは、BさんがVさんを殴るための凶器を渡したわけでもありませんし傷害行為をする場所や環境を提供したわけでもありません。
このような場合でも、AさんはBさんの傷害行為を手助けしたとして傷害罪の幇助犯に問われてしまうのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
ここで、幇助犯の場合、手助けする方法は、物理的(有形的)方法に限らず精神的(無形的)方法でもよいとされていることに注意が必要となります。
例えば、Aさんのように傷害行為をしようとしている人(今回の事例であればBさん)に激励をして、その傷害行為をするという意思を強固にすることも、犯罪をすることをたやすくした=手助けをしたと認められ、幇助犯であると判断される可能性があるのです。
ですから、今回のAさんが、BさんがVさんに対して暴行をふるうことを知っていながらそれを後押しするようなメッセージを送っていたことは、傷害罪の幇助犯となる可能性があるということになるのです。
このように、直接傷害事件にかかわっているわけでなくとも幇助犯の容疑がかかり、刑事事件の当事者となってしまうケースが存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスにて、逮捕が不安な方や逮捕されてしまった方のご相談をお受けしています。
幇助犯等、刑事事件にはなかなか理解しづらい規定が多く存在します。
刑事事件に困ったら、まずは専門家の弁護士に相談をしてみましょう。
出頭要請を無視して逮捕?
出頭要請を無視して逮捕?
出頭要請を無視して逮捕されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府向日市に住んでいる会社員です。
ある日、Aさんは駅で暴行事件を起こしたとして、京都府向日町警察署から出頭要請を受けました。
しかしAさんは、「任意での取調べなら行かなくてもよいだろう」と考え、警察からの出頭要請を無視し続け、再三の警察からの連絡にも応答することはしませんでした。
するとしばらくした後、Aさんは京都府向日町警察署に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、急いで弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・出頭要請を無視したら逮捕される?
Aさんは、暴行事件の被疑者として出頭要請を受けたところ、任意出頭だからと無視していました。
その結果、Aさんは逮捕されるまでに至っています。
出頭要請を無視したら逮捕されてしまうのでしょうか。
ご存知の通り、逮捕は刑事事件の被疑者全てになされるわけではありません。
逮捕せずとも逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には、身体拘束を伴わない在宅事件として捜査が行われます。
在宅事件として捜査が行われる場合、取調べの際に出頭要請があり、その都度警察署や検察庁に出頭するという形式で捜査が進められます。
つまり、在宅事件はいわゆる任意捜査の形で進められますから、確かに出頭を断ることはできることになります。
しかし、Aさんのように、再三にわたる出頭要請を無視し続け連絡も返さない状態が続いたような場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまう可能性が出てきます。
出頭要請を無視したから必ずしも逮捕されるというわけではありませんが、逮捕して身体拘束をする必要があると判断される可能性は高まってしまいます。
・出頭の前に弁護士に相談
当然、逮捕されてしまえばその時点で家族や会社等に連絡する手段もなくなります。
逮捕されるのを回避したいという場合であれば、何度も出頭要請があるにもかかわらず無視を続けるということは避けるべきでしょう。
しかし、出頭要請に応えて出頭し、警察の取調べを受けるということ自体に不安が多いという方も多いというのも事実でしょう。
被疑者の権利や刑事事件の手続きはなかなか一般に詳細が浸透していませんし、自ら出頭しても逮捕されてしまう可能性がゼロになるというわけではありません。
だからこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士は、ご相談者様の刑事事件ごとの見通しや手続きの流れ、被疑者の権利や取調べを受ける際のポイントをアドバイスすることができます。
何も知らずに刑事事件の手続きに入るよりも、弁護士からの専門的なアドバイスをあらかじめ知った上で出頭や取調べに臨むことで、不安の軽減や本意ではない自白の防止などの効果が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が出頭要請が来て不安という方、これから出頭して取調べを受ける予定だという方、逮捕されるのではないかと不安の方のご相談をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご利用いただきやすいよう初回無料法律相談をご用意しています。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
恐喝事件で少年院回避を目指す
恐喝事件で少年院回避を目指す
恐喝事件で少年院回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神戸市須磨区に住んでいるAさん(18歳)は、高校3年生の受験生です。
Aさんは、受験勉強でアルバイトもできず、勉強ばかりで自分が自由に使えるお金が少ないことに悩んでいました。
そしてついに我慢ができなくなったAさんは、ある日、たまたま通りかかった通行人の中学生であるVさんに目をつけました。
そしてAさんは、Vさんに近づくと、Vさんのことをを小突きながら「金を渡さないと痛い目を見せてやるぞ」等と言うと、Vさんからお小遣いを渡させました。
Vさんが帰宅してこのことを両親に相談し、Vさんは両親と兵庫県須磨警察署に被害届を提出。
捜査の結果、Aさんは兵庫県須磨警察署の警察官に、恐喝罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが少年院に行ってしまうのではないかと心配になったAさんの家族は、少年事件に強い弁護士に少年院を回避する活動はどういったものなのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処されます(刑法249条)。
また、財物の交付を受けなくとも、恐喝によって財産上不法な利益を得たり、他人に得させたりした者も同様に、恐喝罪として処罰されます。
刑法第249条
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪の「恐喝」するとは、脅迫又は暴行を手段として相手の反抗を抑圧しない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することを指します。
上記の事例では、AさんはVさんを小突いたり痛い目に合わせるぞと脅したりして(=脅迫又は暴行を手段として)、Vさんのお金を渡すように要求しています(=財物の交付を要求しています。)。
そして、その結果、AさんはVさんからお金を引き渡させている(=財物を交付させている)ことから、Aさんには恐喝罪が成立するといえるでしょう。
なお、Aさんの用いた暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけるほどのもの(例えば凶器を用いるなど)であった場合、恐喝罪ではなく強盗罪に問われる可能性が出てくることにも注意が必要です。
・少年院回避
Aさんのような未成年の者が犯罪をしてしまった場合は、少年事件として扱われます。
少年事件では、原則的に少年が刑罰を受けることはなく、例えば先ほど確認していた恐喝罪の「10年以下の懲役」という刑罰も、Aさんが受けることは基本的にはないということになります。
では、少年事件でどういった処分がなされるのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所で審判が開かれ、その結果少年院送致や保護観察といった保護処分がとられることが原則となっています。
保護処分とは、少年の更生のための処分であり、例えば保護観察の場合は保護司や保護観察所の職員といった人に定期的に報告や連絡をしながら更生を目指すことになりますし、少年院送致となれば少年院の中で矯正教育や職業訓練を受けながら更生を目指すことになります。
少年が少年院に入っている期間は様々で、半年程度で出てくる少年もいれば、長くなると2年を超える期間少年院にいることもあります。
少年院に入れば、当然自由に外と行き来できるわけではなくなりますから、学校や就職先、家族とは切り離されて生活することになります。
もちろん、この少年院送致は少年の更生のための処分ではありますが、こうした社会からの隔離を避けたいと考える方も少なくありません。
少年院送致を回避するためには、環境整備や被害者への謝罪など、少年の周りのや事件についてことこまかに考えていく必要があります。
少年院に入らず、社会内での生活でも少年の更生に適切であることを示し、少年を少年院送致する必要はないと主張することになるでしょう。
例えば、事件に至った経緯や原因、再犯防止策を少年本人だけでなくその周囲の家族も一緒に考え、具体的な対策や行動に移していくことが考えられます。
こうした活動を行う際に、第三者的立場からアドバイスが可能な少年事件に詳しい弁護士にサポートを受けながら環境調整活動等を行っていくことが効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件と少年事件を専門に扱っています。
少年事件を起こしてしまい少年院が不安な方、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
少年による傷害事件と示談
少年による傷害事件と示談
少年による傷害事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
高校1年生のAさんは、大阪府堺市北区に住んでおり、近所の高校に通っています。
ある日Aさんは、自身の通う高校の近くで、近隣の高校の生徒であるVさんとささいなことから喧嘩となり、Vさんを殴ってしまいました。
それを目撃していた人が大阪府北堺警察署に通報し、大阪府北堺警察署の警察官が臨場。
Vさんは全治1週間のけがを負っていることが判明し、Aさんは傷害罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、どうにか示談をして事件を終息できないかと弁護士に相談しましたが、そこで成人の刑事事件と少年事件の手続の違いについて詳しく聞き、少年事件と示談の関係について知ることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・喧嘩から傷害事件に
喧嘩で手が出てしまった場合、成立が考えられる犯罪の代表例としては、今回のAさんが調べられている傷害罪と暴行罪が挙げられます。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
簡単にいえば、傷害罪も暴行罪も人に暴力をふるった場合に成立する犯罪ということは共通していますが、相手に暴力をふるった場合に相手がけがをしてしまえば傷害罪、けがをしていなければ暴行罪となります。
今回のAさんは、Vさんを殴ってけがをさせているため、傷害罪が成立すると考えられるのです。
・少年事件は示談で終わらない?
傷害事件には、今回のVさんのように被害者が存在します。
こうした被害者の存在する事件を起こしてしまった場合、被害者に謝罪し、示談をして事件を終息させたいと思う方も多いでしょう。
実際、成人による刑事事件では、前科前歴ある、余罪が多く存在する、などという特別な事情がない場合には、示談によって不起訴処分となり刑罰や裁判を回避できるケースも多く存在します。
しかし、少年事件の場合、示談をしたからといって事件が終了するというわけではないのです。
少年事件では、原則として最終的に少年に下される処分は、少年の更生のための処分、すなわち、少年が再犯しないようにするための処分となります。
家庭裁判所では、少年自身の性格やその環境などの事情を調査し、少年事件が起こった原因や、再犯しないためにはどうした環境に少年を置くべきなのかといったことが調査されます。
ですから、少年の更生という観点で考えると示談以外の要因、例えば少年の暮らしている周囲の環境の調整など考慮されるため、たとえ被害者と示談が成立していても、それで終わりとはならないのです。
示談をしても、少年の周囲の環境が少年の更生に適する環境となっていなければいけないのです。
しかし、だからといって、少年事件では被害者への謝罪や示談を全く無視していいというわけでもありません。
謝罪や示談ができている、もしくはする準備ができているということは、少年やその家族が事件を真摯に受け止め、反省を深めているということを主張するための事情となりえるからです。
このようにして、少年事件の場合は示談というものの立ち位置は非常に複雑です。
だからこそ、傷害事件等の被害者の存在する少年事件にお悩みの場合は、少年事件を取り扱う弁護士に相談すべきと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が大阪府の少年事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881へお気軽にお問い合わせください。
強盗事件の逮捕で執行猶予を目指す
強盗事件の逮捕で執行猶予を目指す
強盗事件で逮捕され執行猶予を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、生活に困り、大阪市北区にあるコンビニVに入ると店員に包丁を突き付けながら「売上金を渡せ。さもなくば痛い目をみるぞ」と脅し、売上金8万円を奪いました。
店員が大阪府大淀警察署に通報したことで捜査が開始され、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが発覚。
Aさんは、強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの親類は、報道でAさんの逮捕を知り、なんとか力になれないかと大阪府の刑事事件を取り扱う弁護士に相談し、Aさんとの接見に行ってもらうことにしました。
事件の内容を弁護士から報告されたAさんの親類は、Aさんの今後を心配し、執行猶予を目指して弁護活動をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗罪
強盗罪は刑法236条に規定されている犯罪です。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪の「暴行又は脅迫」は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度であることが求められます。
仮に財物を奪うために用いられた暴行や脅迫が相手の反抗を押さえつけるに至らない程度であった場合には、強盗罪ではなく恐喝罪(刑法第249条)となることになります。
また、強盗罪のいう「強取」は、暴行・脅迫によって被害者の反抗を抑圧し、被害者の意思に反して財物の支配を自分(又は第三者)に移すことを指します。
つまり、相手の抵抗を押さえつけるほど強い暴行や脅迫を手段として相手から財物を奪うことで強盗罪が成立するのです。
今回の事例のAさんは、コンビニの店員に包丁を突き付けて脅し、売上金を奪っています。
包丁などの凶器を突き付けられれば、相手に抵抗することは極めて困難になるでしょうから、この行為は強盗罪のいう「暴行又は脅迫」になると考えられます。
これを用いてAさんは売上金という「他人の財物」を奪い取っているわけですから、Aさんには強盗罪が成立すると考えられるのです。
注意すべき点なのは、この強盗罪を犯してしまった際に被害者に傷害を負わせてしまった場合には強盗致傷罪、被害者を死亡させてしまった場合には強盗致死罪が成立するということです。
強盗致死傷罪は裁判員裁判の対象となるため、より入念かつ慎重な対応が求められます。
最初は強盗罪の容疑で逮捕されていても、捜査が進むにつれて被害者の診断書が出てくるなどして強盗致傷罪に引き上げられるということも予想されますから、強盗罪で逮捕されてしまったらそうしたケースも念頭に置きながら弁護活動をしてもらうことが必要です。
・執行猶予を目指す活動
上述のように、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」とされており、罰金刑の規定はありません。
つまり、強盗罪で有罪になってしまえば、執行猶予を獲得しない限り刑務所に行くということになります。
ただし、ここで注意しなければならないのが、執行猶予はつけられる条件が決まっているということです。
執行猶予をつけられる条件として、言い渡された刑罰が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」でなければいけないというものがあります(刑法第25条)。
しかし、見て頂ければわかる通り、強盗罪の刑罰の下限は5年であるため、この執行猶予獲得の条件に当てはまらないのです。
では、強盗罪では執行猶予を獲得することが絶対にできないのかというと、そうではありません。
情状酌量によって刑罰が減軽されれば、言い渡される刑罰が3年以下の懲役となる可能性があるからです。
もちろん、基本的には強盗罪の刑罰は見てきたとおり「5年以上の有期懲役」ですから、執行猶予を獲得できるまで刑罰を減軽してもらうことは非常に難しいことです。
しかし、示談締結や具体的な再犯防止活動、犯行時の事情などを主張することで積極的に執行猶予を求めていくことで、執行猶予獲得や刑罰の減軽の可能性をあげていくことができます。
まずは刑事事件を取り扱う弁護士に相談し、どういった活動が可能なのか詳しく聞いてみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗事件を含む暴力事件のご相談・ご依頼にも対応しています。
お困りの際は、遠慮なく弊所お問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
ナイフで脅迫したら暴力行為処罰法違反?
ナイフで脅迫したら暴力行為処罰法違反?
ナイフで脅迫したら暴力行為処罰法違反になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
さいたま市岩槻区に住むAさんは、隣人のVさんとささいなことからトラブルになり、路上でVさんにナイフを向け、「それ以上口ごたえをするようなら痛い目にあわせるぞ」などと脅しました。
現場近くに居合わせた通行人が埼玉県岩槻警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が帰宅しないAさんを心配して警察署に連絡したところ、どうやらAさんが現行犯逮捕されて警察署に留置されているようだということが分かり、急いで弁護士に相談しました。
そこでAさんの家族は、Aさんの逮捕容疑が暴力行為処罰法違反という耳慣れない犯罪であることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴力行為処罰法とは?
上記事例のAさんの逮捕容疑は「暴力行為処罰法違反」という犯罪です。
しかし、Aさんの家族がそうであったように、この法律・犯罪名はなかなか聞き馴染みのないものでしょう。
通常、人を脅迫したら成立する犯罪といえば脅迫罪という刑法に定められている犯罪です。
刑法第222条第1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
上記事例のAさんは、Vさんに対してナイフを向け、「痛い目にあわせるぞ」などといったVさんの身体を傷つける脅し文句を口にしていますから、「身体(中略)に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」と言えるでしょう。
ですが、実は、犯行形態によって、人を脅迫した場合に脅迫罪ではなく暴力行為処罰法違反が成立する場合があるのです。
暴力行為処罰法とは、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、「暴処法」「暴力行為法」「暴力行為処罰法」などと略されます。
この暴力行為処罰法には、以下のような条文があります。
暴力行為処罰法第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
大正時代の法律であるため、少し読みにくい部分があるかもしれませんが、簡単に言えば、大勢で威力を示したり、凶器を示したり、数人で共同したりして刑法の特定の犯罪を行った場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金というより重い処罰としようということなのです。
今回のAさんが使用していたナイフや包丁といった刃物は「兇器」と判断されうるものですから、これを利用して刑法222条の罪=脅迫罪に当たる行為をすれば、暴力行為処罰法のこの規定に該当する犯罪とされるのです。
なお、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、暴力行為処罰法違反の方が重い刑罰となることが分かります。
刑事事件では、一般になかなか知られていない犯罪の容疑がかかってしまうこともあります。
逮捕容疑が知らない犯罪名であれば、動揺してしまうこともあるでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件の専門知識・経験に富んだ弁護士に相談し、容疑をかけられている犯罪のこと、今後の見通しや手続きのことをきちんと把握しておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在宅事件にも逮捕されてしまっている身柄事件にも迅速に対応できるように弁護士が様々なサービスをご用意しています。
まずはお気軽にご相談ください。
職質から銃刀法違反が発覚
職質から銃刀法違反が発覚
職質から銃刀法違反が発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、神奈川県横須賀市に住んでいる会社員です。
ある日、Aさんが会社から自宅へ帰ろうと神奈川県横須賀市の路地を歩いていたところ、巡回していた神奈川県浦賀警察署の警察官から職質を受けました。
その中で、手荷物検査を求められたAさんは、持っていたカバンを警察官に提出しました。
すると、Aさんのカバンの中からツールナイフが出てきました。
このツールナイフは、Aさんが「何かあったときのために持っておこう」と携帯していたものでした。
しかし、警察官によると、そのツールナイフは銃刀法違反に当たるとのことで、Aさんは後日神奈川県浦賀警察署に呼び出されることとなってしまいました。
不安になったAさんは、銃刀法違反についての相談も受け付けている弁護士の無料法律相談に申込み、弁護士から詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・銃刀法違反
銃刀法という法律名を聞いたことがある方も多いかもしれません。
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前のとおり銃砲や刀剣類の所持や使用等を規制している法律です。
銃刀法では、確かに銃砲や刀剣類の規制を行っていますが、刃が付いているすべての物を刀剣類として規制しているわけではありません。
銃刀法では、以下のように「刀剣類」の定義を定めています。
銃刀法第2条第2項
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
つまり、銃刀法の中で「刀剣類」として規制されるのは、「刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた」と「刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)」というものに限定されているのです。
この「刀剣類」については、銃刀法で、法令に基づき職務のために所持する場合(銃刀法第3条第1項第1号)などに限り所持が認められており、それ以外の場合に所持すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(銃刀法第31条の16第1項第1号)。
しかし、そうすると今回の事例のAさんが所持していたようなツールナイフは「刀剣類」に当たらないように見えます。
ここで、銃刀法は「刀剣類」だけに限って規制しているわけではないということにも注意が必要です。
銃刀法には、「刀剣類」以外の刃物について、以下のような規定があります。
銃刀法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
つまり、たとえ「刀剣類」に当てはまらなかったとしても、刃渡り6センチメートルを超える刃物であれば、「業務その他正当な理由による場合」を除いて持ち歩くことが禁止されているのです。
今回のAさんは、職質中の手荷物検査でツールナイフを発見され、そのツールナイフが銃刀法違反であると言われていますが、おそらくツールナイフの刃渡りが6センチメートルを超えるのものであったのでしょう。
また、Aさんは「何かあった時のために」とツールナイフを携帯していたようですが、これが「業務その他正当な理由による場合」に当たらないとされれば、銃刀法第22条に違反すると考えられます。
なお、銃刀法第22条に違反した場合、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります(銃刀法第31条の17第3号)。
・銃刀法違反に違反しなくても犯罪に?
ここで、「では、『刀剣類』にも刃渡り6センチメートルを超える刃物でもないものであれば携帯できるのか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、銃刀法以外にも、刃物の携帯について規定している法律があることにも注意が必要です。
それは、軽犯罪法という法律です。
軽犯罪法には、以下のような条文があります。
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法では、正当な理由なしに刃物を隠して携帯することを禁じています。
銃刀法と異なり、軽犯罪法では刃物全般を規制しているため、たとえ刃渡りが6センチメートルを超えなくとも軽犯罪法違反となる可能性があるのです。
今回のAさんのように、職質から銃刀法違反事件に発展してしまえば、「銃刀法違反をするつもりではなかった」「どのように対応すべきなのか分からない」とお困りになる方も多いでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談も受け付けていますので、お気軽にご利用いただけます。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。
しつけのつもりが監禁罪に?
しつけのつもりが監禁罪に?
しつけのつもりが監禁罪になってしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都立川市に住んでいる主婦のAさんには、4歳になる息子のVくんがいます。
Aさんは、Vくんがなかなか言うことをきかないことに腹を立て、しつけとしてVくんを物置の中に閉じ込めました。
Vくんは長時間物置の中に入れられたことでパニックになり泣き叫んでいましたが、Aさんは「しつけなのだから嫌がっていないと意味がない」と思い、そのまま何時間も放置しました。
こうしたことが度々起こり、Vくんの泣き声を聞いた近所の人が「ここしばらくずっとVくんがひどく泣き叫んでいるようだ。もしかしたら虐待かもしれない」と警視庁立川警察署に通報。
警視庁立川警察署の警察官がAさんらの自宅に駆けつけ、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されてしまったという連絡を受け、急いで刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・監禁罪
監禁罪とは、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第220条では、「不当に」「人を」「逮捕」又は「監禁」することを禁止しており、このようにして人を「逮捕」した場合には逮捕罪が、「監禁」した場合には監禁罪が成立します。
また、逮捕・監禁罪にあたる行為をして人を死傷させた場合には、逮捕致死傷罪・監禁致死傷罪が成立することになります(刑法第221条)。
では、監禁罪は具体的にどういったことをすると成立するのでしょうか。
まず、監禁罪の「不当に」とは、正当な理由なくという意味です。
例えば、警察官が逮捕状に基づいて行う逮捕は、正当な理由のある「逮捕」と言えます。
そして、「監禁」とは、相手を限られた場所から脱出できないようにする行為を指し、相手の移動の自由を奪う行為を指します。
多くは建物内に閉じ込めるといった手法で監禁行為が行われることが多いですが、オートバイの後部座席に人を乗せ、時速40キロで走行し、その人が降ろして欲しいと言っているのに走行し続けるという場合でも、後部座席からの脱出が著しく困難になっているので監禁罪が成立します。
また、監禁行為の手段として、建物内に閉じ込めて鍵をかけるといった行為以外にも、睡眠薬を飲ませて移動を不能にしたり、「そこを動くと殺すぞ」と脅迫して恐怖心による心理的拘束を加えることで移動を不能にしたりする方法で監禁行為を行っても監禁罪が成立することになります。
監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」となっているため、起訴され有罪判決となれば、執行猶予が付かない限り刑務所へ行くことになります。
こうしたことからも、監禁罪は非常に重い罪であることが分かります。
不起訴や執行猶予獲得のためには、早い段階から弁護士に相談していくことが重要です。
・しつけと監禁罪
親であれば、自分の子供にしつけをするということは自然なことです。
しつけの過程で子供を叱ったり、何らかの罰を与えることもあるかもしれません。
民法でも、親には子供の教育等をする権利と義務が定められており、同時に「懲戒権」という教育等のために子供の不当な行為にたいして罰を与える権利が認められています。
民法第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
民法第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
しかし、民法第822条の規定にもある通り、認められているのはあくまで「監護及び教育に必要な範囲内」での懲戒権です。
しつけだから、しつけのためだからといってなんでも認められているわけではありません。
当然、度を越した行為であればしつけとして済まされることなく、犯罪になってしまいます。
今回のAさんの行為も、Aさんとしては「しつけのためだ」と考えているようですが、何時間も物置に閉じ込めておく行為がしつけの範囲に収まるものではないと判断されれば、監禁罪が成立すると考えられます。
しつけのつもりで監禁事件などの刑事事件に発展してしまった場合、被害者である子供と加害者である親が同居していることが多いです。
そうしたケースでは、被害者と加害者の接触を避けるため、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが少なくありません。
突然の逮捕に困ったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、しつけのつもりの行為で刑事事件に発展した事例についても、ご相談・ご依頼を承っています。
まずはお気軽にご相談ください。
強制性交等罪の否認事件
強制性交等罪の否認事件
強制性交等罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさん(30代男性)は、知人であるVさん(30代女性)と飲み会で意気投合し東京都中央区にあるホテルへ行き、性行為をしました。
すると数日後、警視庁築地警察署から、「強制性交等事件の被疑者として話を聞きたい」と連絡がありました。
AさんとしてはVさんとはお互い合意の上で性行為をしたと思っていたものの、近日中に思い当たる節がなかったため、Vさんとの件ではないかと思っています。
しかし、Aさんはあくまで合意の上での行為であったと思っているため、どのように対応していくべきなのか困ってしまい、強制性交等事件も取り扱っている刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等罪
刑法改正により強制性交等罪が新設されてから3年が経ちました。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、旧強姦罪よりもより重い5年以上の有期懲役という法定刑が定められ、さらにその対象の行為が、性器の挿入を伴ういわゆる「本番行為」だけでなく、肛門性交や口腔性交もその対象とされました。
また、旧強姦罪の被害者は女性に限定されていましたが、強制性交等罪では被害者に男女の限定がなくなりました。
そして、旧強姦罪が親告罪であったのに対して強制性交等罪は非親告罪となり、被害者等の告訴権者が告訴しなくとも起訴することが可能となりました。
・強制性交等罪の否認事件
今回の事例のAさんのように、「お互いの合意の上だ」と思って性行為等を行ったのに相手方はそう思っておらず、強制性交等罪の被害を受けたと被害届や告訴がなされてしまうケースは少なくありません。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではなく合意があったと思って性行為をした、と主張するのであれば、容疑を認めない、いわゆる「否認」をしていくことになります。
強制性交等事件を否認する場合には、ただ「合意の上だと思っていた」と主張するだけではなく、どのような事情があったから合意の上だと思ったのか、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか、などの事情を詳細に検討し整理しておく必要もあります。
また、強制性交等事件に限らず、刑事事件で容疑を否認をする場合には取調べで厳しく追及される可能性があります。
1人で取調べを受ける中で、被疑者として持っている権利や受け答えのポイントを把握せずに対応してしまえば、意図していない自白をしてしまったり誘導に乗ってしまったりする可能性もあります。
取調べで供述したことは後々裁判で証拠として使用される可能性もあるため、否認事件では取調べから対応を注意しなければならないのです。
さらに、否認事件の場合、容疑を認めていない=逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまう可能性もあります。
しかし、「逮捕されたら困るからやっていないけど認めよう」と対応してしまえば、冤罪となってしまいます。
弁護士であれば逮捕をせずに捜査を求める活動や、逮捕後釈放を求める活動をすることができますので、逮捕・勾留のような身体拘束への対応も含めて、まずは弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認事件についてのご相談も受け付けています。
否認事件は対応がデリケートであるからこそ、刑事事件専門の弁護士がお力になります。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
老人ホームでの虐待事件
老人ホームでの虐待事件
老人ホームでの虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、福岡県北九州市小倉北区の老人ホームに勤務しています。
Aさんは、入居者のお年寄りVさんに対し、身体を殴るはたくといった暴行を日常的に行っていました。
しかし、Vさんの家族がVさんの身体にあざが複数あることに気付き不審に思い、福岡県小倉北警察署に相談したことからAさんの行いが発覚しました。
Vさんの家族は福岡県小倉北警察署に傷害罪の被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが傷害罪で逮捕されたとの連絡を受け、まさかAさんが仕事先で虐待行為を行っていたとは思わず、大きく混乱しています。
自分たちでは何をすべきなのか分からず困ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家庭以外での虐待事件
虐待という言葉を聞くと、家庭内暴力(DV)や児童虐待について思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、虐待は被害者が子供の児童虐待や家庭内で起こる虐待だけでなく、上記事例のAさんが起こしてしまったような老人ホームでの高齢者虐待も存在します。
児童虐待も老人ホームでの高齢者虐待も、「虐待罪」というような犯罪が成立するわけではなく、刑法や特別法の中でその虐待行為の態様が該当する犯罪が成立することになります。
例えば、今回のAさんの虐待事件の場合、入居者であるVさんを殴るなどして暴力をふるい、怪我を負わせているようです。
こうしたことから、Aさんには刑法の傷害罪や暴行罪が成立すると考えられます。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪と暴行罪は、人に暴力をふるうという部分については共通していますが、その暴力によって相手が「傷害」されたかどうか、すなわち怪我を負ってしまったかどうかという部分が異なります。
簡単に言えば、暴力をふるって相手が怪我をしてしまえば傷害罪、怪我を負うに至らなければ暴行罪が成立するということになるのです。
今回のAさんの虐待事件では、Vさんは体にあざができていたとのことですから、打撲等の怪我を負っていた可能性が高いでしょう。
そういった怪我の診断書が提出されるなどして、Aさんに傷害罪の容疑がかかったと考えられます。
・虐待事件での逮捕
虐待事件では、加害者である被疑者と被害者が同じ家庭内や同じ施設内にいることも多いです。
今回のAさんの虐待事件でも、Aさんは老人ホームの職員であり、被害者のVさんはその老人ホームに入居しています。
このように加害者と被害者が近い場所にいる刑事事件の場合、お互いの接触を避けるために逮捕・勾留を伴って捜査が行われることも少なくありません。
逮捕・勾留は延長も含めて最大23日間の身体拘束となり、被疑者やその家族は精神的・身体的な負担だけでなく、社会的な負担も負うことになります。
さらに、今回のような虐待事件では被害者が存在するため、被害者に謝罪し、被害弁償することも重要となってきますが、逮捕・勾留されている状態ではなかなかそうした謝罪をすることも難しいでしょう。
被疑者本人に代わってご家族が謝罪をするにしても、捜査機関から取り次いでもらえないことも少なくありません。
だからこそ、虐待事件で逮捕されたら、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が介入することによって、逮捕・勾留されている被疑者に直接取調べ対応等のアドバイスを行うことができ、釈放を求める活動をすることもできます。
そして、被害者への対応にも弁護士が間に入ることによって、謝罪・弁償をする際の被害者側の不安や負担も軽減することが期待できます。
弁護士を介することで、被害者側が直接被疑者やその家族と連絡を取らなくてよくなるため、恐怖や被害感情が強かったとしても安心して話をすることができるためです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、老人ホームでの虐待事件などの傷害事件・暴行事件にも対応しています。
虐待事件で逮捕されたら、まずは弊所弁護士までご相談ください。