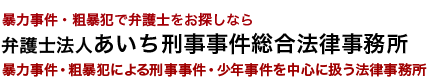未分類
酒に酔っての暴行事件で逮捕
酒に酔っての暴行事件で逮捕
酒に酔っての暴行事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神戸市東灘区の会社に勤務しているAさんは、終業後、飲食店で飲酒をして帰路につきました。
すると、通行人のVさんとすれ違った際に肩がぶつかってしまいました。
Aさんは酒に酔っていたことで気が大きくなっており、Vさんがわざと肩をぶつけてきたのだと因縁をつけ、Vさんの胸倉をつかんだり突き飛ばしたりしました。
それを見ていた別の通行人が兵庫県東灘警察署に通報したことから、兵庫県東灘警察署の警察官が現場に駆け付けましたが、Aさんは「何の用だ。俺は何も悪いことをしていないぞ」などと言って逃げようとしたことから、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、酔いがさめてから事の重大さに気づき、今後自分がどのようになってしまうのか不安に襲われました。
そこでAさんは、逮捕の知らせを受けて家族が接見を依頼した弁護士に、今後の流れや見通し、対応の仕方について詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪・傷害罪
人に暴力をふるってしまえば、刑法の暴行罪や傷害罪に問われることになります。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文にあるように、暴行罪と傷害罪は、人に暴力をふるって怪我をさせてしまえば傷害罪に、怪我をさせるに至らなければ暴行罪になるという関係にあります。
わざと暴力をふるった時点で暴行罪の故意(暴行罪を犯す意思や認識)があることは分かりやすいですが、その暴行で相手が怪我をしてしまえば、たとえ「相手に怪我をさせよう」という認識がなくとも傷害罪が成立することになります。
すなわち、傷害罪の成立には、暴行罪の故意があれば十分なのです。
こういった関係にある犯罪を「結果的加重犯」と呼び、今回の暴行罪・傷害罪でいえば、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるということになります。
暴行事件で注意しなければいけないのは、逮捕されたり任意同行を受けたりした時点では被害者が怪我をしているかどうかが分かっていない場合があり、そうしたケースでは、後から容疑が暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性もあるということです。
捜査が進んだことで診断書などが提出され、罪状が変わるということもあり得るのです。
・酒を飲んで刑事事件を起こし逮捕されてしまったら
酔っ払いのちょっとした喧嘩程度で大事にはならない、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした暴行事件や傷害事件で逮捕されてしまう可能性は十分あります。
今回の事例のAさんのように、事件当時酒に酔って暴れていたり逃げようとしたり、受け答えがはっきりしなかったりといったことがあれば、逮捕されてしまう可能性が出てくるでしょう。
また、酒に酔った末に暴行事件を起こしたようなケースで酒に酔って記憶がない、記憶が曖昧であるという場合には、記憶がはっきりしないことから被疑事実を認めることができないため、容疑を否認している=逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうことも考えられます。
こうした酒に酔って突発的に暴力事件を起こしてしまい逮捕されてしまったケースでは、勾留されずに釈放されることもそのまま勾留がついて身体拘束が続く場合もどちらも考えられます。
被疑者の酔いがさめてきちんと対応ができるようになったり、被害の程度が軽く悪質性が低いと判断されたりすれば、逮捕されていたとしてもすぐ釈放になることも考えられます。
対して、被疑者の記憶がはっきりしないなどの理由から被疑事実を否認し続けているケースや、被害の程度が重く悪質性が高いと判断されたケースでは、逮捕に引き続いて勾留されることも考えられるのです。
では、釈放される可能性もあるのだから放っておいてよいのかというとそうではありません。
たとえ釈放されたとしてもその事件自体が終了したわけではなく、当然事件の捜査は続いていくことになります。
起訴・不起訴の判断をされるときや起訴後にどういった刑罰が適切か判断されるときには、取調べで被疑者が話した内容が証拠として使われる可能性があります。
そのため、その後の刑事事件の流れを考えれば少しでも早く専門家である弁護士からアドバイスをもらって取調べ対応のアドバイスや手続き・流れの把握をしておくことが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、酒に酔って刑事事件を起こしてしまったケースや逮捕にお困りのケースでも刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
0120-631-881では、ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内していますので、まずはお気軽にご連絡ください。
傷害事件で初回接見
傷害事件で初回接見
傷害事件で初回接見をするケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪府堺市にある駅の構内で、肩がぶつかったVさんと激しい口論となり、かっとなってVさんを思い切り殴り、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
通報を受けて現場に駆け付けた大阪府堺警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、どうにかAさんに会えないかと大阪府堺警察署に行きました。
しかし、警察官から「逮捕後の48時間は面会できない」と聞き、困ったAさんの家族は、暴力事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕された直後の接見は重要?
今回の事例でAさんの家族が警察官から言われているとおり、逮捕されてしまったら、逮捕されてから48時間はたとえご家族であったとしても、被疑者本人に会うことはかないません。
一般の方の面会が許されるのは、原則として、逮捕から引き続く身体拘束である「勾留」が付いた場合で、さらに接見等が禁止されていない場合に限られます。
ですから、ご家族が逮捕の知らせを受けてもそこから被疑者本人の状態や事件の事情を把握できるまでには時間を要することになってしまうのです。
しかし、弁護士にはそのような制限なしに被疑者と接見できる権利(接見交通権)があります。
接見交通権は、被疑者・被告人の防御のために重要な権利であるとされており、例えば逮捕直後や夜間、土日祝日など、ご家族が被疑者本人と会えない時間であっても、弁護士であれば接見を行うことができます。
逮捕直後から迅速に初回接見を行うことには、とても大きな意味があります。
例えば、どうして被疑者として逮捕されてしまったのか、どのようなことをしてしまったのか、という事件に関する事情や被疑者の言い分を弁護士を通じて確認することもできます。
さらに、ご家族からの伝言を弁護士が被疑者本人へいち早く伝えることもできます。
そして、取調べが行われる前に弁護士との接見を行うことができれば、弁護士が直接取調べに対する助言をすることができます。
取調べに際して、やってもいないことをやったと言ってしまったり、被疑者自身が不本意な自白をしてしまったりすることのないよう、被疑者自身の主張を確認するとともに、手続きの流れや被疑者の権利について専門家の弁護士から説明を聞いておくことは、刑事事件で適切な処分を求めるにあたって有効であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも弁護士と接見ができる初回接見サービスをご用意しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスとは、弁護士が1回限りの接見=面会を行うサービスです。
先ほど触れたように、取調べ等への対応は弁護士のアドバイスを受けてから臨むことが望ましいですから、初回接見は逮捕から早期に行う方がメリットが大きくなるといえます。
ご家族が傷害事件などの暴力事件で逮捕されてしまってお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で24時間受け付けていますので、遠慮なくお問い合わせください。
傷害致死事件で裁判員裁判
傷害致死事件で裁判員裁判
傷害致死事件で裁判員裁判となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪府茨木市で居酒屋に客として訪れていたのですが、そこへVさんを含む数名の大学生グループが客として訪れました。
Vさんらはひどく酔って店内で騒ぎ暴れる様子であったため、AさんはVさんらに「他の客の迷惑になるからやめなさい」と注意をしました。
するとVさんが「お前に関係ないだろ」などと言ってきたので、腹を立てたAさんはVさんの顔面を握り拳で殴りつけてしまいました。
Aさんはカッとなってつい殴ってしまっただけであったものの、Vさんは、酔っていたこともあり殴られた拍子に大きく態勢を崩し、近くにあった机の角に頭をぶつけてしまいました。
Vさんは頭から流血して動かなくなってしまい、Aさんは驚いてすぐに救急車を呼びましたが、搬送先の病院でVさんの死亡が確認されました。
救急隊と共に現場に駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官により、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、傷害致死罪が裁判員裁判になると知り、今後のことが不安になったため、弁護士に相談して詳しいことを聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害致死罪
今回のAさんには殺意はなかったようですが、Vさんの顔面を殴っているため、少なくとも暴行の故意が認められます。
そしてその暴行によって生じた怪我によってVさんが死亡しているといえるため、Aさんには傷害致死罪が成立することになります。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
・裁判員裁判
裁判員裁判になる事件かどうかは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、通称「裁判員法」により決められています。
裁判員法第2条第1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
第1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
第2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
傷害致死罪は、このうち裁判員法第2条第1項第2号に当てはまるため、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは、通常の刑事裁判とは異なり、刑事裁判の第1審に裁判官だけでなく、一般の市民も裁判員として審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その1つが、公判前整理手続という手続きが必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に検察官や弁護士と裁判官で事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
公判前整理手続はあくまで公判前の準備手続ですが、実際の公判では公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
つまり、裁判員裁判となった場合には、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があるのです。
・裁判員裁判での弁護活動
前述のように、裁判員裁判では裁判員として一般の方が参加します。
ですから、通常の裁判に比べて裁判員裁判ではわかりやすさが重視されると言えるでしょう。
被告人側の事情をどれだけ説得的にかつ裁判員の方々の胸に響くように裁判で明らかにできるかが、最終的な量刑判断に強く影響します。
また、今回の傷害致死事件のように被害者や遺族が存在するケースでは、被害者や遺族との示談交渉を行い、被害者・遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことも考えられます。
しかし、いずれの主張も、先に述べた公判前整理手続で適切に証拠を検討し、必要であれば弁護側からも証拠を提出しておく必要があります。
さらに、裁判員裁判の対象となる事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
そこで、保釈等の身体解放に向けた活動も行っていく必要があります。
早期の身体解放や十分な公判準備のためには、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判を含めた刑事事件の解決事例もございます。
傷害致死事件などの裁判員裁判対象事件にお困りの際は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
タクシー料金の踏み倒しで強盗事件に
タクシー料金の踏み倒しで強盗事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
千葉県流山市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰ろうとしたところ終電の時間を過ぎていたことから、Vさんの運転するタクシーを利用することにしました。
Aさんの自宅に到着したあたりで、VさんはAさんに料金を伝えて支払いを求めましたが、酔っ払っていたAさんは「そんなに高い料金ぼったくりだ。俺は帰るぞ」などと告げ、料金を踏み倒して帰ろうとしました。
驚いたVさんが「困りますよ」とAさんを追おうとしたところ、AさんはVさんを強く突き飛ば市押し倒すなどしてVさんを振り切って自宅へ帰りました。
Vさんがすぐに千葉県流山警察署に通報したことで、警察官が駆けつけ、最終的にAさんは強盗罪の容疑で逮捕されるに至りました。
まさかタクシー料金の踏み倒しから強盗罪になるとは思わなかったAさんは、驚いて接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・タクシー料金の踏み倒しが強盗罪に?
強盗罪と聞くと、目出し帽を被った犯人が店員や銀行員に凶器を突きつけてお金を奪うというシーンが思い浮かぶかもしれません。
しかし、実は強盗罪は金品を奪う行為のみに成立する犯罪ではないのです。
刑法第236条
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
先ほど例にあげたような誰かに凶器を突きつけて脅してお金を奪うという態様の場合には、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」していることから、刑法第236条第1項に規定されている強盗罪が成立すると考えられます。
しかし、刑法第236条第2項に規定されている強盗罪の場合、暴行又は脅迫を手段として用いていることは刑法第236条第1項の強盗罪と変わりませんが、「他人の財物を強取」するのではなく「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」るという部分が異なってきます。
つまり、刑法第236条第2項の強盗罪は、暴行や脅迫によって物理的に金品を奪うのではなく、何か利益を自分や第三者に受けさせるようにすることによって成立するのです。
こうしたことから刑法第236条第2項の強盗罪は「強盗利得罪」などとも呼ばれますが、その法定刑は刑法第236条第1項にある強盗罪と変わらず「5年以上の有期懲役」であり、強盗利得罪になったから重く処罰される、処分が軽くなるといったことはありません。
では、今回のAさんについて考えてみましょう。
まず、結果としてAさんはタクシー料金を踏み倒しています。
タクシー料金を踏み倒すということは、本来払わなければいけない料金の支払いを不正に免れているという「財産上不法の利益を得」ていることになります。
そして、Aさんはタクシー料金の踏み倒しをするためにVさんを強く突き飛ばし押し倒すなどして振り切っていますから、「暴行」を用いていると言えるでしょう。
ここで、強盗罪にいう「暴行」とは、相手の抵抗を抑圧する程度のものが必要とされていますが、今回Vさんは突き飛ばされ押し倒されていることから、Aさんの「暴行」はVさんの抵抗を抑圧する程度の強さだったと考えられるでしょう。
以上のことから、Aさんのタクシー料金の踏み倒し行為は刑法第236条第2項の強盗罪にあたると考えられるのです。
強盗罪は非常に重い犯罪で、刑罰の下限も5年の懲役刑となっていることから、有罪になると情状酌量による刑罰の減軽等がなければ執行猶予をつけることもできません(執行猶予がつけられるのは、懲役刑の場合、3年以下の懲役が言い渡される場合に限られます。)。
ですから、こうしたタクシー料金の踏み倒しであっても、「料金を踏み倒した程度で大したことはない」と甘く考えず、早期に弁護士に相談・依頼することが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、タクシー料金の踏み倒しによる強盗事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
痴話喧嘩が暴行事件に
痴話喧嘩が暴行事件となってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県小川町在住の男性Aさんは、女性Vさんと交際していました。
ある日、AさんとVさんが自動車で出かけている最中、2人はささいなすれ違いから喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんは、AさんがVさんを止めようと身体を押さえたことから「暴力をふるわれる」と勘違いしてしまい、車内から道路に向かって大声で「殴られる!助けて!」などと悲鳴を上げました。
通行人が2人の様子を見て埼玉県小川警察署に通報したことで、警察官が現場に駆け付け、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されてしまったことをVさんからの連絡で知り、急いで弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴話喧嘩から刑事事件・逮捕に発展
今回の事例は、交際相手と喧嘩になってしまういわゆる痴話喧嘩が暴行事件という刑事事件に発展してしまい、逮捕まで至ったという事例です。
たかが痴話喧嘩で刑事事件などという大事になるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、こうした痴話喧嘩から刑事事件へ発展してしまったというご相談が寄せられることもあります。
痴話喧嘩による暴行事件では、痴話喧嘩がヒートアップする中で相手に対する感情が行き過ぎてしまうことが原因となることが多いです。
例えば、今回のAさんのように、カップルが2人だけいる止める人のいない状況(例えば車の中)で感情的になった結果、ついヒートアップしてしまい刑事事件化するというケースも少なくありません。
ここで注意しなければならないのは、痴話喧嘩から発生した暴行事件・傷害事件では、逮捕される可能性が低くないことです。
痴話喧嘩をする関係であるということは、当然被疑者と被害者が交際しているということになります。
となると、被疑者と被害者はお互いが相手の住所や連絡先などを知っているということになり、捜査機関からすれば、被疑者と被害者が接触するリスクがある=証拠隠滅のおそれがあると判断しやすく、逮捕・勾留による身体拘束が必要であると判断しやすいのです。
特に、日常的にお互いの間で暴行が疑われる場合(DVが疑われる場合)、より逮捕・勾留による身体拘束の可能性が高まることになるでしょう。
そのため、痴話喧嘩から暴行事件に発展してしまったケースでは、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放活動や逮捕回避活動を迅速に開始してもらうことが大切です。
加えて、暴行事件ということは、当然被害者が存在します。
今回のような痴話喧嘩から発展した暴行事件では、被害者側も大事になるとは思っておらず、処罰を求める意思がないということもあります。
そうした場合には、被害者の意思を適切に主張していくだけでなく、今後同じことが繰り返されないような具体的な対策を立て、それも主張していくことが求められます。
もちろん、被害者対応や再犯防止活動は被害者の方の処罰感情や事件当時の事情、それまでの経緯などの様々な事情によって異なるものですから、まずは弁護士に相談し、具体的にどういった活動が可能か検討していくことが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴話喧嘩から発展した暴行事件などの暴力事件にも対応しています。
0120ー631ー881では、専門スタッフがご相談者様の状況に合ったサービスをご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
職務質問中に警察官を殴打し逮捕
今回は、職務質問中に警察官を殴打してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都北区に住むAさんは、薬物の常習者です。
薬物常習者に特異な挙動をパトロール中の警視庁赤羽警察署の警察官に見咎められ、停止を求められました。
Aさんはその時覚せい剤を所持していました。
覚せい剤所持が発覚するとまずいと思い、無言で立ち去ったところ、警察官のうち1人がAさんの前に立ち、もう1人がAさんの肩を掴んで止めようとしました。
Aさんは「任意の職務質問を強制する警察官を懲戒する」などと叫び、警察官の額を右こぶしで殴打しました。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~公務執行妨害罪について解説~
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条1項)、及び、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条2項)をいいます。
実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません。
ただし、条文上明らかではありませんが、判例通説によると、本罪の職務は適法でなければなりません。
したがって、Aさんの暴行に先立ってなされた職務質問が、刑法第95条における適法性を有していないのであれば、公務執行妨害罪は成立しません(ただし、暴行罪や傷害罪は成立しうるでしょう)。
ケースにおける職務質問は適法だったのでしょうか。
~職務質問の適法性~
警察官職務執行法第2条1項によれば、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができ」ます。
ただし、同条3項によると、「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とされているので、職務質問は任意処分ということができます。
それでは、警察官がAさんを止めるために行く手を阻んだり、肩を掴んだりする行為は任意処分として許容されるのでしょうか。
判例(最高裁判所第三小法廷昭和51年3月16日決定)は、「任意捜査における有形力の行使は、強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り許容されるが、状況のいかんを問わず常に許容されるものではなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、許容される」としています。
Aさんに①薬物常習者に特異な挙動が認められる点、②職務質問を受けたところ、無言でその場を立ち去ろうとした点は、上記の「必要性」、「緊急性」が肯定される可能性を高める行為ということができるでしょう。
なお、上記判例においては、警察官が、酒酔い運転の罪の被疑者を警察署に任意同行し、呼気検査に応じるよう説得を続けていたところ、被疑者が急に退室しようとしたため、その左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ点が問題となりました。
これに対し最高裁は、「任意捜査において許容される限度内の有形力の行使である」として適法と判断しました。
ケースの警察官はAさんの行く手を阻んでいますが、そもそもAさんに触れたわけではなく、適法に停止させる行為として認定される可能性が高いと思われます。
また、もう1人の警察官がAさんの肩を掴んだ点についても、程度の強いものとは言えず、Aさんの行動を考慮すれば、相当なものとして、任意処分の範疇に属する有形力の行使と判断されるものと考えられます。
職務質問の対象者をいきなり殴打したり、いきなり組み伏せたりすれば、もはや任意処分とはいえないと思いますが、ケースにおける程度の有形力の行使は、殆どの場合、適法と判断されるのではないでしょうか。
~すぐに弁護士を呼ぶ~
逮捕されてしまった事件を有利に解決するためには、早期に弁護士を依頼することが重要です。
ご家族が公務執行妨害事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害事件の身柄解放活動
今回は、傷害事件を起こしてしまった方の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都府中市の繁華街を歩いていた際、Vのさしていた傘が自身に当たったことをきっかけとしてトラブルとなり、腹に据えかねたAさんは、Vの顔面を右こぶしで殴打してしまいました。
Vは顔面打撲の傷害を負っています。
Aさんの犯行は通行人により警察に通報されてしまい、Aさんは、警視庁府中警察署に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~傷害罪について解説~
文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
通常、右こぶしで人を殴打するなどしてケガをさせてしまった場合には、傷害罪が成立することになります。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
なお、銃砲や刀剣類を用いて人の身体を傷害した場合は、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」に違反することとなり、法定刑は1年以上15年以下の懲役となります(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条の2)。
Aさんは素手でVの顔面を殴打し、怪我を負わせているので、通常の傷害罪が成立することになるでしょう。
~早期の身柄解放に着手~
傷害の疑いで現行犯逮捕されてしまうと、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
ケースバイケースではありますが、逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになります。
Aさんが会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、無断欠勤・無断欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続くと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになります。
逮捕されてしまった場合は、可能な限り早く留置場や拘置所の外に出ることが重要です。
逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要です。
逮捕されてしまったケースにおいて、常に勾留決定をすることが許されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(勾留の要件)
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
②(1)被疑者が定まった住居を有しないこと
②(2)被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
②(3)被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
③勾留の必要性が認められること
②(1)~(3)は、いずれか1つ充足すれば足ります。
勾留を阻止するためには、検察官や裁判官に対して、以上の要件を満たさないことを説得すればよいのです。
①については、Aさんが現行犯であることから、これを満たさないと主張することは難しいかもしれません。
②③については、「Aさんに定まった住居や職があること」、「被害者とは特に接点がなく、被害者の住所から離れて生活していること」、「信頼できる身元引受人を用意できること」などを主張し、勾留をしないよう働きかけることになるでしょう。
~勾留されてしまった場合~
勾留されてしまった場合であっても、「準抗告」や「勾留取消請求」などの制度を通じ、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
また、Vと示談をすることも重要です。
示談がまとまれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される可能性があります。
また、検察官がAさんの事件につき、不起訴処分を行う可能性も高まります。
さらに、Vと示談をして、Vに生じさせた損害を賠償することにより、後日、民事事件に巻き込まれるリスクを無くすこともできます。
傷害の疑いで逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。
接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神社の社殿の一部に放火
今回は、複数からなる建造物の一部に放火した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
東京都杉並区に住むAは仕事やプライベートでうまくいかず、ストレスを抱えていたことから、放火をしようと考えていました。
そこで、夜間に自宅から3kmほど離れた場所にある神社を目標に定めました。
そこで、社殿の一部の祭具庫に放火し、祭具庫は全焼しました。
その後、付近をパトロールしていた警察官によって、Aは逮捕されました。
祭具庫は当時、人はおらず、住居に使用するものでもありませんでしたが、その神社は複数の建造物からなり、その一部には人の現在、現住する社務所や守衛詰所があり、それらは木造の回廊でつながっていて一周できる構造になっていました。
それら複数の建造物は日夜、神社職員等によって一体として使用されていました。
(フィクションです。)
-放火罪の種類-
主な放火に関する刑法上の条文には以下のものがあります。
108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
109条
1項(他人所有非現住建造物等放火罪) 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項(自己所有非現住建造物等放火罪) 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
110条
1項(他人所有建造物等以外放火罪) 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2項(自己所有建造物等以外放火罪) 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲又は十万円以下の罰金に処する。
放火して焼損させた対象が、現に住居に使用されているか否か、現に人がいるか否か、建造物等か否か、他人所有か自己所有かによって条文が分かれています。
-建造物としての一体性-
本件では、放火し焼損させたのは社殿内の祭具庫で、建造物にあたるので建造物等以外を対象とした110条が適用から外れますし、Aの自己所有でもないので、自己所有を前提とした109条2項も適用されません。
それでは、残るのは108条と109条1項になり、人の現在性・現住性の有無がどちらの条文に当たるかの成否を分けます。
本件でAが放火し焼損させた祭具庫はどうでしょうか。
祭具庫自体には現住性・現在性はないのですが、ここでは、祭具庫が人の現在・現住する社務所や守衛詰所と建造物として一体といえるかどうかがポイントとなります。
建造物として、一体といえるためには「物理的一体性」と「機能的一体性」が重要といえます。
「物理的一体性」とは物理的にみて、構造上一体といえる状態のことです。
ただし、現住性・現在性部分に対する延焼可能性があってはじめて現住・現在建造物としての物理的一体性が認められます。
なぜなら、現住建造物等放火罪が直接人の生命・身体に危険を及ぼすために重く処罰されていることから、現住・現在部分に対する延焼可能性が全くない場合だと人の生命・身体への危険が認められないからです。
そして、「機能的一体性」とは、使用上の一体性を指します。
現住部分と非現住部分が一体として使用されている場合には、非現住部分にも人が存在する可能性があるからです。
-本件で建造物としての一体性があるといえるか-
本件では、祭具庫と社務所や守衛詰所とが木造の回廊で繋がっているところから、構造上一体であり、延焼可能性もあることから、物理的一体性があるといえます。
また、焼損した祭具庫と社務所や守衛詰所は一体として使用されていたことから、機能的一体性があるといえます。
以上により、本件では祭具庫と社務庁や守衛詰所とが「物理的一体性」と「機能的一体性」が認められることによって、建造物の一体性があるといえます。
よって、Aには108条の現住建造物等放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
-放火事件の加害者になったら-
以上のように、放火罪は複数の条文にまたがっていますし、適用される条文(刑法108条)によっては死刑もあり得るので、事件を解決するにあたっては弁護士の知識・経験が欠かせません。
もし、あなたやあなたの大事な人が加害者として放火の罪に問われそうになったら、是非、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にご相談ください。
土下座を強要し逮捕
土下座を強要し逮捕
今回は、飲食店店員に土下座を強要し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都市下京区内の飲食店で食事をしていたところ、値段に見合った味でないことに腹を立て、責任者を呼び出しました。
Aさんは責任者に対し、「おい、高い金とってこんな料理出すことはないだろ。誠意を見せろ。こういう時やることがあるだろう、土下座だ」などと大声で迫り、イスを蹴り飛ばすなどして土下座を要求しました。
責任者は恐怖を感じ、仕方なく土下座をしましたが、他のお客さんの通報で駆け付けた京都府下京警察署の警察官により、Aさんは強要の疑いで現行犯逮捕されてしまいました(フィクションです)。
~強要罪について解説~
強要罪とは、相手やその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する犯罪です(刑法第223条1項・2項)。
上記の脅迫・暴行をしたが、人に義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害するに至らなかった場合も、未遂犯として罰せられます(同条3項)。
Aさんは、イスを蹴り飛ばすなどして責任者を怖がらせ、土下座をさせています。
この事実関係によれば、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたものということができると考えられるので、Aさんに強要罪が成立する可能性は高いと思われます。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役となっています。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴されると、刑事裁判が始まることになります。
~早期の身柄解放を実現~
早期の身柄解放を実現するためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。
Aさんの身体拘束が長引く要因は勾留されてしまうことにあります。
早期に弁護人を選任すれば、検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを訴えかけ、勾留をしないように働きかけることができます。
勾留されてしまった場合にも、準抗告と呼ばれる不服申し立てなどを行い、釈放を求めることができます。
さらに、被害者と示談を成立させることにより、勾留前であれば勾留されない可能性、勾留後であっても、釈放される可能性を高めることができます。
釈放されれば、普段通りに会社へ出勤することができるので、無断欠勤を続けてしまった日数、周囲の状況、報道の有無にもよりますが、会社に逮捕されたことを知られずにすむことも考えられます。
~不起訴処分の獲得~
Aさんが単に責任者を土下座させてしまった、というだけであれば、円満な示談を成立させることにより、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分を獲得できれば、前科を付けずに事件を解決することができます。
今回は大目に見てもらうということです。
より良い事件解決を目指して、一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強要事件などを起こして逮捕された、取調べを受けたといった場合にはぜひご相談ください。
コンビニで消火器を使用し逮捕
コンビニで消火器を使用し逮捕
今回は、コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、兵庫県淡路市内のコンビニにおいて、目的の商品が無いことに腹を立て、店員に因縁をつけるなどしていました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
Aさんは駆け付けた兵庫県淡路警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~威力業務妨害罪とは?~
文字通り、「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪です(刑法第234条)。
【「威力」とは?】
「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行や脅迫はもちろん、社会的地位、経済的地位、権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、物の損壊など、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力の一切をいいます。
コンビニ店内で消火器の粉末を放射すれば、消火器の噴射自体が人を怖がらせるさせるものである上、粉末が片付くまで営業を中止せざるを得ないと思われるので、「威力」に該当する可能性が高いと思われます。
【「業務」とは?】
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
公務が「業務」に該当するかなど、議論のあるポイントではありますが、コンビニの営業が「業務」に該当することに異論はありません。
【「妨害」に該当するには?】
現実に業務遂行が妨害されることは必要ではなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば足りると解されています。
ケースの場合、消火器の粉末が片付くまでコンビニの営業を中止せざるを得ないと考えられるので、「妨害」に該当する可能性が高いでしょう。
以上の事実関係によれば、Aさんは、威力を用いて(消火器をコンビニ店内で放射して)、他人の業務を妨害したものということができると考えられます。
したがって、Aさんに威力業務妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
~逮捕後の手続~
逮捕された段階で最長72時間、身体拘束を受ける可能性があります。
さらに、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可をすれば、さらに最長20日間、勾留と呼ばれる身体拘束を受ける可能性があります。
裁判が始まる前の捜査段階において、最長23日間、外に出られなくなる可能性があるということです。
その後、刑事裁判が始まると、保釈が認められない限り、さらに身体拘束が続いていく可能性もあります。
~早期の身柄解放と軽い処分の実現~
身体拘束が長引くと、①身体的・精神的に重い負担がかかる、②会社や学校に行くことができず、不利益な処分を受けることになってしまうなどの弊害が生じます。
なるべく早く外に出ることが、円滑な社会復帰のために重要です。
【身柄解放活動のポイント】
①勾留を防ぐ、②勾留後の不服申し立て、③被害者との示談が主なポイントになるでしょう。
逮捕されても、勾留されなければ、72時間以内に釈放されます。
勾留された場合であっても、その取消等を求めて不服申し立てを行うことができます。
ただし、一旦裁判官が勾留を許可しているので、勾留に対する不服申し立てはハードルが高いといえます。
そもそも勾留の決定がされないように迅速な弁護活動を受けることが重要となります。
また、被害者と示談が成立すれば、罪証隠滅・逃亡のおそれがないと判断され、釈放される可能性が高まります。
【不起訴処分の獲得】
検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、その裁量により、Aさんを刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)を行うことができます。
今回は大目に見てもらうということです。
適切な弁護活動を通じ、不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずに刑事手続きが終了します。
不起訴処分は難しくても、公開の法廷での刑事裁判を受けずに、簡易な手続で罰金刑になる略式裁判で済む可能性もあります。
こういった軽い処分を目指すためにも、示談は重要となってきます。
なんら被害者に謝罪・賠償をしない場合と比べると、印象が良くなるわけです。
~弁護士にご相談を~
とはいえ身柄解放に向けた手続きや示談交渉の方法など、わからないことだらけだと思います。
事件解決に向けたアドバイスを致しますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身やご家族が偽計業務妨害などで捜査を受けた場合には、ぜひご相談ください。