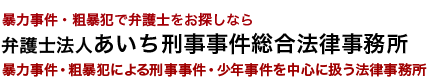Archive for the ‘未分類’ Category
【事例解説】強盗の準備をしていたことが発覚し逮捕(前編)
強盗をする準備をして強盗予備罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは地元の先輩から窃盗をやらないかと誘われ、お金を持っていそうな豪華な外観のVさん宅に、先輩を含めた数名と一緒に窃盗に入ることにしました。
犯行日時や役割分担などを決め、場合によってはナイフで脅して金を奪うという計画まで立てました。
また、ナイフや金目の物を入れるためのバッグも用意しました。
ところが犯行直前になって、臆した仲間の1人が警察署に相談をしました。
その情報をもとに、警察が犯行予定日時にVさん宅周辺に張り込みしていたところ、何も知らないAさんらが現れました。
すぐさま警官が取り囲み、Aさんらは強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【~強盗予備罪とは~】
Aさんたちは、仲間と共に窃盗の計画だけでなく、場合によってはナイフで脅すという強盗の計画まで立てて、ナイフやバッグを用意するなどの準備を行っていました。
まだ窃盗や強盗自体を行ったわけではありませんが、このような準備をした時点で強盗予備罪という犯罪が成立してしまいます。
刑法第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
つまり、
①強盗目的で
②その準備をすると
強盗予備罪が成立します。
①まず、この強盗目的とは、暴行・脅迫を用いて物を奪い取る強盗を最初からするつもりの場合はもちろん、とりあえず空き巣(窃盗)をするつもりだが家主に見つかったら強盗の手段も辞さないという「居直り強盗」の計画がある場合も含まれます。
Aさんたちの場合も、最初から強盗で行こうとはしていませんが、場合によってはナイフで脅して金を奪うという強盗をするつもりであったので、①強盗目的があると言えます。
②次に、強盗の準備としては、強盗に必要な凶器などを調達したり、下見に行ったり、凶器などを持ってどの家に入ろうかと物色・徘徊するような行為が該当します。
Aさんたちは凶器となるナイフや現金を入れるバッグを準備していますし、まさにこれら凶器などを持ってVさん宅の近くまで来たわけですから、②強盗の準備をしたといえます。
以上により①と②両方を満たすので、Aさんたちには強盗予備罪が成立するといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
仮に逮捕されていなかったり、既に釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
逮捕されると手続きも一気に進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】悪口を言われて、コーヒーをかけた男を傷害罪で逮捕
悪口を言われてカッとなった男が、同僚にコーヒーをかけて傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
会社員のAさんは、同僚のVさんと険悪な仲でありながらも我慢して仕事をしていました。
ある日、同僚のVさんがAさんに対して度を越した悪口を言いました。
これに堪忍袋の緒が切れたAさんは持っていた淹れたてのコーヒーをVさんにかけました。
目撃していた同僚たちが警察に通報したことで、Aさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいました。
コーヒーをかけられたVさんは重度の火傷を負っています。
(フィクションです)
・傷害罪とは
刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、Aは持っていた淹れたてのコーヒーをVさんにかけて火傷を負わせたようです。
このAの行為が、生理的機能に障害を加えたと評価され傷害罪が成立する可能性があります。
・逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は会社員です。
逮捕後に勾留された場合、Aは長期間出勤することがしばらくできなくなり解雇される可能性があります。
したがって、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明して勾留を防ぐ必要があります。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。
ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも、A自らVと交渉しようとしても上手くいかない可能性があります。
AとVは元々不仲ということですし、熱湯をかけられたVとしてはAに対して強い処罰感情を有しているでしょうから、交渉決裂となりやすいのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に依頼していれば、長期間の身柄拘束を防ぎ、解雇を防ぐことができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】高校の部活内での後輩に対する暴行事件
高校の部活で後輩に対して暴行した事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事例
高校のサッカー部に所属する高校3年生のAは後輩部員V1,V2,V3に対して、指導という名目で殴る蹴るなどの暴行を加えたとして、Aを暴行の容疑で逮捕されました。
V1らが助けを求めて最寄りの警察署に被害届を提出したことで事件が明るみになりました。
警察はサッカー部の他の部員等にも聞き取りをして、暴行が常態化していたかどうか調べているようです。
(フィクションです。)
・暴行罪と傷害罪
本件では、Aが複数の後輩に対して、指導という名目で、殴る蹴る等の暴行行為をしたようです。
Aの当該行為が、暴行すなわち人の身体に対する不法な有形力の行使にあたる場合には暴行罪が成立します。
さらに、暴行により被害者が出血したような場合には、人の生理機能を侵害したとして傷害罪が成立します。
暴行罪の多くの場合においても、身体に対して不法な有形力の行使があった以上、厳密に言えば(微細な内出血など)何らかの生理機能が侵害されていると言えそうですが、実際には、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかがにより暴行罪になるか傷害罪になるかの分かれ目になることが多いです。
暴行罪の法定刑が「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と重くなっていますから、どちらの罪が成立するかは大きな違いを生みます。
・暴行罪事件の弁護活動
暴行罪または傷害罪に当たるような行為をしてしまった場合、被害者側と示談を成立させるなどして、被害届を取り下げたり、病院診断書の提出を控えてもらうことができるかどうかが重要となります。
ただし、加害者側の人間が直接被害者側と示談交渉を進めることが得策ではありません。
本件のように、被害者が未成年である場合には、被害者側の交渉主体は保護者となります。
保護者は本人以上に、加害者に対して強い処罰感情を有している可能性がありますから、示談交渉自体を拒絶される可能性もあります。
そこで、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
豊富な示談交渉の経験のある弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、被害届の取下げ等の、加害者を許す意思を含む示談を成立させ、不起訴処分や刑罰軽減につながるかもしれません。
暴行事件や傷害事件を起こしてしまった場合、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】スイミングスクールでの暴行でインストラクターの男が逮捕
スイミングスクール内での暴行でインストラクターの男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例
スイミングスクールでインストラクターを務めるAは、熱心な指導と実績で有名であった。
ある日のレッスンで遅刻してきた生徒Vがいたので、みんなの前で注意をしたところ、態度を改めずに反論を続けたため、Aは感情を抑えきれず、Vの顔を殴ってしまった。
殴られたVは倒れこんで顔面に打撲を負い、レッスン途中で家に帰ってしまった。
帰宅したVが怪我をしていることに気づいた両親が、警察署に連絡したところ、Aは逮捕され、傷害罪の容疑で取調べを受けることとなった。
Aは警察の取調べで、「Vの態度があまりにもひどく、感情的になって殴ってしまった。深く反省している」と容疑を認めている。
Vは病院で診察を受けた結果、顔面打撲の他に軽い脳震盪の症状も認められ、数週間の治療を要することが判明した。
(フィクションです。)
傷害罪とは
本件で、スイミングスクールのインストラクターであるAは、態度の悪い生徒Vの顔面を殴ってしまい、傷害罪の疑いで逮捕されるに至ったようです。
刑法204条(出典/e-GOV法令検索)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることとされています。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件Aは、レッスンに遅刻して注意されても反省を色を示さなかったVを殴った結果、顔面打撲と軽い脳震盪で全治数週間の怪我を負わせて、Vの生理的機能に障害を加えたようです。
したがって、Aには傷害罪が成立する可能性があります。
逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
身柄拘束中は、Aは出勤することができなくなります。
この場合には、長期間にわたって出勤できないことを理由に解雇される可能性があります。
したがって、身体拘束の長期化を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないでしょうから、ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は、検察官と裁判官に対し、意見書を提出して、勾留の必要性がないことを説明することができます。
適切なタイミングで説得力のある意見書を提出するためにも、ご家族が逮捕された場合にはできるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、起訴不起訴や量刑の判断において、被害者側と示談を締結できているかどうかが大きな意味を持ちます。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性がありますから、やはりできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
傷害事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間受付中です。
【事例解説】大人しい夫が暴行の容疑で突然逮捕
大人しい夫が暴行の容疑で突然逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
ある日の夜、Bの自宅に警察署から電話があり、夫のAを暴行罪で逮捕したと伝えられました。Bは、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
事件の詳細を知るために、Bは弁護士に初回接見の依頼をしました。
(フィクションです)
暴行罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。
ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。
つまり、Aさんの行ったとされる暴行は、相手に傷害を負わせていない可能性があります。
具体的な弁護活動
繰り返しになりますが、暴行罪の場合、相手に傷害を負わせていないことから、軽い罪になることが多いでしょう。具体的には、罰金刑にとどまったり、執行猶予が付いたり、といった内容です。
ただ、軽い罪と言っても、刑罰である以上、前科が付くことにはなってしまいます。
事件によっては、他人の喧嘩に巻き込まれただけだったなど、暴行の覚えがないにも関わらず容疑を掛けられてしまう場合もあり、このような場合には、冤罪であるとして潔白を主張し,不起訴処分や無罪判決を求めることが考えられます。
他にも、正当防衛で無罪を主張するケースなどもありますが、正当防衛が成立するかどうかは,具体的な事情を細かく考慮する必要がありますので,弁護士に相談したほうがよいでしょう。
検察官に起訴される前に、暴行の相手方と示談を締結することはとても有益です。
相手方と示談することができれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになります。身体拘束されている場合でも,示談をすることで早期に釈放される可能性が高まります。早期に釈放されることは、職場復帰などの観点からも重要です。
弁護士を介することで、被疑者と関係のよくない相手であっても、示談を首尾よく進められることも多いのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴行罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
0120-881-631まで、ぜひ一度,お問い合わせください。
【事例解説】喧嘩の仲裁をしたつもりが傷害で捜査を受けることに
喧嘩の仲裁をしたつもりが傷害で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
Aさんが友人と飲んだ帰りに道を歩いていると、友人と通行人Vの肩がぶつかったようで友人と通行人Vが口論をはじめました。
Aさんはお互いをなだめていましたが、口論がヒートアップして掴み合いに発展し始めたため、友人を守ろうと通行人Vの服を掴んで引き離しました。
それに加えて、Aさんは通行人Vの胸の辺りを押して喧嘩をやめるように伝えました。
通行人Vは相手が2人では分が悪いと考え、その場を立ち去りました。
通行人VがAさんに突き飛ばされて怪我をしたと警察に被害届を出したようで、Aさんは警察から呼び出しを受けることになりました。
Aさんは喧嘩の仲裁に入ったつもりで、仮に自身の行為が傷害に当たるとしても正当防衛だと考え弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「傷害」とは人の生理機能を侵害することであるとされています。
具体例としては、頭を叩いてたんこぶや内出血を負わせること、刃物で切り傷を負わせることなどが上げられます。
事例のAさんは、喧嘩の仲裁のためとはいえ通行人Vさんの服を掴んで引き離したり、胸の辺りを押しているため、これにより通行人Vさんが怪我をしていれば、人の生理機能を侵害したとして傷害行為が認められるかもしれません。
正当防衛について
ある行為が犯罪に当たる行為であっても、それが正当防衛の要件を満たす行為であればその行為の違法性はなく犯罪は成立しません。
正当防衛は刑法36条1項に規定されています。
刑法36条1項(出典/e-GOV法令検索)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
これからすると、正当防衛は、「急迫性」、「不正の侵害」、「自己又は他人の権利」、「防衛するため」、「やむを得ずにした」という要件が必要であることが分かります。
正当防衛が成立する可能性があるか否かは、法律的な判断が必要となりますので、自身で勝手に判断するのではなく法律の専門家である弁護士の見解を聞いてみることをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
暴行罪や傷害罪で警察の捜査を受けることになった方は、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】質店への強盗で男が逮捕
質店への強盗で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
Aさんは、お金欲しさに質店に強盗に入り、現場から逃走しました。
警察が現場に駆け付け付近を捜索していたところ、Aさんは見つかってしまい、Aさんは強盗の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪(刑法236条1項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処すると定められています。
強盗罪は、量刑が5年以上の有期懲役となり、重大犯罪の1つです。
簡単に説明すると、金品等を盗むにあたり、相手を凶器で殴ったり、脅したりして無理やり物を奪うような行為が強盗罪です。
相手を殴るなどの行為は、被害者が怪我をし、場合によっては死亡したりすることが非常に発生しやすい状況のため、危険で悪質な犯罪と言えます。
被害者が怪我や死亡した場合は、強盗よりもさらに重い強盗致傷罪が成立することになるでしょう。
暴行・脅迫とは
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
例えば、殴る・蹴る・凶器で殴る等の行為です。
脅迫とは、相手に対する害悪の告知を意味します。
例えば、「殴るぞ。監禁してやる。ネットに写真をばらまくぞ。」等が該当し、具体的な基準はありませんが、被害者が恐怖するような言動であれば脅迫に該当してしまう可能性が高いでしょう。
暴行・脅迫がどのようにおこなわれたか、日時や場所などを総合的に考慮して判断されることになります。
強盗事件を起こしてしまったら
できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
強盗罪は、5年以上の有期懲役です。
5年以上の有期懲役である強盗罪は、原則執行猶予がつきません。
(執行猶予は3年以下の懲役である必要があります。)
しかし、強盗行為をおこなってしまっても、被害者に真摯に謝罪して示談が成立すれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があります。
この場合には、執行猶予がつく可能性があるため、示談を成立させることができるかどうかが重要となるため、非常に素早い行動が大切になってきます。
そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめいたします。
被害者が被疑者の示談交渉等を拒絶している場合でも、弁護士とであれば連絡を取ることに応じる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗事件について豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】無銭飲食をして逃走の際に店員に暴行
飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件
飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
強盗致傷罪とは?
強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条(出典/e-GOV法令検索)に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
ご覧のように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。
無銭飲食がなぜ「強盗」に?
飲食店での食い逃げ(いわゆる無銭飲食)については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するために最低限必要とされる要件を満たさないことから、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
さて、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。
今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
そして、その際に相手を怪我させてしまうと強盗致傷罪が成立します。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方に対する初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】強盗の準備をしていたとして強盗予備罪で逮捕
強盗をする準備をして強盗予備罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは地元の先輩から窃盗をやらないかと誘われ、お金を持っていそうな外観のVさん宅に、先輩を含めた数名と一緒に窃盗に入ることにしました。
犯行日時や役割分担などを決め、もしVさんに見つかった場合にはナイフで脅して金を奪うという計画まで立てました。
また、ナイフや金目の物を入れるためのバッグも用意しました。
ところが犯行直前になって、臆した仲間の1人が警察署に相談をしました。
その情報をもとに、警察が犯行予定日時にVさん宅周辺に張り込みしていたところ、何も知らないAさんらが現れました。
すぐさま警官が取り囲み、Aさんらは強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗予備罪とは~
Aさんたちは、仲間と共に窃盗の計画だけでなく、場合によってはナイフで脅すという強盗の計画まで立てて、ナイフやバッグを用意するなどの準備を行っていました。
まだ窃盗や強盗自体を行ったわけではありませんが、このような準備をした時点で強盗予備罪という犯罪が成立してしまいます。
刑法第237条(出典/e-GOV法令検索)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
つまり、
①強盗目的で
②その準備をすると
強盗予備罪が成立します。
①まず、この強盗目的とは、暴行・脅迫を用いて物を奪い取る強盗を最初からするつもりの場合はもちろん、とりあえず空き巣(窃盗)をするつもりだが家主に見つかったら強盗の手段も辞さないという「居直り強盗」の計画がある場合も含まれます。
Aさんたちの場合も、最初から強盗で行こうとはしていませんが、場合によってはナイフで脅して金を奪うという強盗をするつもりであったので、①強盗目的があると言えます。
②次に、強盗の準備としては、強盗に必要な凶器などを調達したり、下見に行ったり、凶器などを持ってどの家に入ろうかと物色・徘徊するような行為が該当します。
Aさんたちは凶器となるナイフや現金を入れるバッグを準備していますし、まさにこれら凶器などを持ってVさん宅の近くまで来たわけですから、②強盗の準備をしたといえます。
以上により①と②両方を満たすので、Aさんたちには強盗予備罪が成立するといえるでしょう。
~事件はどう進んでいくのか~
逮捕をされたAさんたちは、最初に最大3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、被疑者段階で最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
勾留がされるか否かは事件次第ですが、前科があったり、今回行った犯罪が重かったり、犯行を否認していると、刑罰から逃れたいとはずだと判断され、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いとして勾留されやすくなる傾向にあります。
また、共犯がいる事例では口裏合わせをする可能性があるなどの理由により、証拠隠滅の可能性があると判断される可能性が高くなる傾向にあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴された場合には、保釈請求をして認められない限り、身体拘束が続くことになります。
そして判決で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
~すぐに弁護士にご相談ください~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、ご不安の点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
仮に逮捕されていなかったり、既に釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
逮捕されると手続きも一気に進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】直接暴行をしていないが取調べを受けることに(後編)
直接暴行をしていないものの傷害の共犯として警察の取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
建築会社で働いているAは、その会社の社員Vとの険悪な仲でした。ある日、同僚のBとVの悪口を話していた際に、Vを痛めつけてやろうという話になり具体的な暴行計画について話し合うことになりました。
AとBの計画では、AがVを尾行してVの位置をBに随時報告し、タイミングを見計らってBがVを後ろから殴り、あとでAも暴行に加わるというものでした。
計画通り、Vに対してBが殴ることに成功しましたが、攻撃を受けたVが大声をあげて周りに助けを求めたため、AとBはその後の暴行をやめて二人で逃走しました。
Vは頭部裂傷と皮下血種の傷害を負いましたが、大事には至りませんでした。
Vの被害供述をもとにBが取調べに呼ばれ、Aの関与を明らかにしたためAも警察から聴取を受けるに至りました。
自身は直接暴行行為を加えていないAは、自分も傷害罪の罪を負うことになるのか気になり弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
今回の事例の場合
Aは、Vに直接暴行行為をしていないため、Aが傷害罪の「正犯」として処罰されるかは、共謀共同正犯が成立するか否かによります。
共謀共同正犯の成立要件を簡単に検討していくと、共謀についてはAとBはVに暴行を加える計画を綿密に立てており、意志の連絡が十分にあるといえます。
また、どちらも自らの犯罪として実行する意思を有しているため正犯意思も認められそうです。
そうすると、共謀は認められそうです。
次に、AとBの共謀に基づいて、BがVに傷害を加えているため、共謀に基づく実行行為も認められるでしょう。
そうすると、傷害行為に加わっていないAについても共謀共同正犯として「傷害罪」の「正犯」としての責任を負うことになるでしょう。