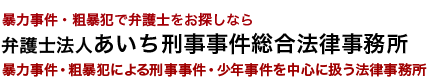【事例解説】直接暴行をしていないが取調べを受けることに(前編)
直接暴行をしていないものの傷害の共犯として警察の取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
建築会社で働いているAは、その会社の社員Vとの険悪な仲でした。ある日、同僚のBとVの悪口を話していた際に、Vを痛めつけてやろうという話になり具体的な暴行計画について話し合うことになりました。
AとBの計画では、AがVを尾行してVの位置をBに随時報告し、タイミングを見計らってBがVを後ろから殴り、あとでAも暴行に加わるというものでした。
計画通り、Vに対してBが殴ることに成功しましたが、攻撃を受けたVが大声をあげて周りに助けを求めたため、AとBはその後の暴行をやめて二人で逃走しました。
Vは頭部裂傷と皮下血種の傷害を負いましたが、大事には至りませんでした。
Vの被害供述をもとにBが取調べに呼ばれ、Aの関与を明らかにしたためAも警察から聴取を受けるに至りました。
自身は直接暴行行為を加えていないAは、自分も傷害罪の罪を負うことになるのか気になり弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
傷害罪の共謀共同正犯について
刑法60条(出典/e-GOV法令検索)は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定めています。
共同正犯は、実行共同正犯と共謀共同正犯に分けられます。
一方の、実行共同正犯とは、共同行為者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言います。
例えば、2人で被害者Vの殺害計画をして、計画に基づきVに2人でそれぞれピストルを発砲し死亡させたような場合です。
このように、2人が共同して実行する意思の下に発砲した場合には、もしいずれの弾が命中したかがわからなくても2人とも実行共同正犯として殺人既遂罪の責任を負います。
他方の、共謀共同正犯とは、2人以上の者が犯罪を実現するための謀議をし、共犯者の一部の者のみが実行行為を行う場合をいいます。
これが認められる場合には、実行行為をしていないものについても共同正犯として発生した犯罪事実すべての責任を負うことになります。
成立要件としては、①共謀、②共謀に基づく実行行為が必要となります。
①共謀とは、共同犯行の合意形成をいいます。これは意思連絡および正犯意思によって判断されます。
簡単にいうと、意思連絡は共同犯行の意識について関与者間に意思疎通があったか、正犯意思は自分たちの犯罪を遂行しようとする意識があったかが問題になります。
②共謀に基づく実行行為は、共謀に基づいて少なくとも共謀者の1人が実行行為があった場合に認められます。